●29日は紀尾井ホールで河村尚子「ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・プロジェクト」Vol.2。ピアノ・ソナタ第18番変ホ長調、第21番ハ長調「ワルトシュタイン」、第24番嬰ヘ長調「テレーズ」、第23番ヘ短調「熱情」の4曲。これぞベートーヴェンという強靭なダイナミズムを堪能。「ワルトシュタイン」はコーナーぎりぎりを攻めて激走するようなスリリングさ。高揚感にあふれた「熱情」も聴きごたえあり。構築美とパッションが完璧なバランスで共存するベートーヴェン。アンコールは「エリーゼのために」。超有名曲だが、ひとつのバガテルとして作品をまっさらな目で見つめ直したような鮮度があった。
●ソナタ第18番は第2楽章にスケルツォが置かれていて、しかも2拍子というのが変わっている。クセのある曲想で、なんとなく具体的なモノとか動きを曲にしているような雰囲気があって、機械の運動っぽい。機関車みたいなイメージなんだけど、1802年にそれはないだろうから、別のなにか動くもの。
2018年11月アーカイブ
河村尚子 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ・プロジェクト Vol.2
デニス・ラッセル・デイヴィス指揮読響のジョン・アダムズ
●28日はサントリーホールでデニス・ラッセル・デイヴィス指揮読響。多様な打楽器群を含む大編成の現代曲2曲の間に、モーツァルトの協奏曲を挟んだプログラム。スクロヴァチェフスキの「ミュージック・アット・ナイト」、モーツァルトのフルートとハープのための協奏曲(エマニュエル・パユ、マリー=ピエール・ラングラメ)、ジョン・アダムズの「シティ・ノワール」。スクロヴァチェフスキは昨年を世を去った読響ゆかりの大指揮者でもある。その「ミュージック・アット・ナイト」とアダムズの「シティ・ノワール」、曲名からしても共通した題材に思えるわけだけど、スクロヴァチェフスキのほうはフェッラーラの古城で思いを馳せた伝説がきっかけ、アダムズのほうはロサンジェルスで起きた猟奇的殺人事件「ブラック・ダリア」由来で「フィルム・ノワール」的な街と時代の雰囲気を描く。
●「シティ・ノワール」はドゥダメルのLAフィル音楽監督就任記念の作品ということで、ドゥダメルが一時盛んに振っていた曲。録音や放送で聴く機会はあったけど、ライブで聴いたのは初めて。4管編成に打楽器群特盛の一大スペクタクルで、エネルギッシュで明快、華麗。洗練された熱狂というべきか。輝かしい音の悦楽。他のアダムズ作品と比べて新味があるかといえば微妙なところなんだけど、聴けばすっかり術中にはまるという巧緻。演奏後、オーケストラを讃えるデニス・ラッセル・デイヴィスの姿が印象的。
●フルートとハープのための協奏曲、モーツァルトにしては例外的にお上品というか、過剰にロココ的(?)というか、微温的というか、クライアントの要求にこたえすぎた作品だと日頃思っているんだけど、パユとラングラメのふたりはそんな先入観を吹き飛ばすようなキレのある冴えたソロ。ソリスト・アンコールは、フルートとハープでイベールの間奏曲。抜群に楽しい。
インフルエンザ予防接種2018

●インフルエンザの予防接種を打ってきた。
●今年のワクチンは、ほどよい刺激の後に柔らかな肌当たりが続くエレガントなフルーティさで、50年に一度の傑作と言われた2013年に匹敵するタフな出来ばえ。
広上淳一指揮NHK交響楽団のアメリカ音楽プログラム
●24日はNHKホールで広上淳一指揮NHK交響楽団のオール・アメリカ・プログラム。これが激しくチャレンジングなプログラムで、バーバーのシェリーによる一場面のための音楽、コープランドのオルガンと管弦楽のための交響曲(鈴木優人)、アイヴズの交響曲第2番。どれもライブではめったなことでは聴けない曲ばかり。さすがに客席の入りは普段通りとは行かないが、エキサイティングなプログラムを聴けたことに感謝するほかない。コープランドの後は鈴木優人さんのアンコールでバッハの「われら苦難の極みにあるときも」BWV641。しみじみとした美しさに浸る。チェロのゲスト首席は辻本玲さん。アイヴズでのソロが絶品。ゲスト・コンサートマスターには白井圭さん。
●アイヴズの交響曲第2番は1902年の完成っていうんだから、作曲年代でいえば相当に古い。混沌とした引用の交錯や最後の痛烈かつ唐突な一撃など、モダニズムの到来以前にポストモダンに走っているというか、先駆的というよりは先走り感が半端ではないが、これが実際に音になるイメージをアイヴズはどれくらい持っていたのだろうか。完成から半世紀も経って初演され、なおかつその時点で作曲者が存命中だったという稀有な交響曲。そして、そんな曲をバーンスタインが初演するという運命の不思議さ。この日の演奏は最後の例の一撃が長くのばされてバーンスタイン風。もっとも、客席の反応に戸惑いや反発などは今や望むべくもないということか、大喝采と無関心のほとんど両極に収束している感。
●コープランドのオルガンと管弦楽のための交響曲、これはNHKホールのオルガンの場所ゆえかと思うのだが、事前に聴いておいた複数音源とはかなり違った印象で、オルガン・ソロがとても間近に聞こえて鮮烈。全般に「春の祭典」風味とかスケルツォでのミニマル・ミュージック先取り風味などを漂わせつつ、オルガンと管弦楽の力強い対話がくりひろげられ、終楽章では怒涛のクライマックスめがけて驀進する。おもちゃ箱をひっくり返した感は、アイヴズ以上かも。終楽章の歪んだ行進曲って、今にも怪獣が出てきそうな感じ。自分にとって20世紀大管弦楽曲に「ぐっと来る」バロメーターのひとつは、内なる中二病を刺激してくれる「怪獣出てきそう感」。その点、この曲は伊福部昭といっしょにゴジラが出てくる様子を連想させる感覚があって、それってなんでだろうと思って気が付いたのがオルガン。はっ。オルガンと言えばキングギドラの鳴き声。これはまさしく「キングギドラ出てきそう」感。伊福部vsコープランドの代理怪獣大戦争がここに(んなわけない)。
ズービン・メータ指揮バイエルン放送交響楽団
●22日は東京芸術劇場でズービン・メータ指揮バイエルン放送交響楽団。当初はヤンソンス指揮でマーラーの交響曲第7番「夜の歌」が予定されていたのだが、健康上の理由によりメータが代役で登場、曲もモーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」とマーラーの交響曲第1番「巨人」に変更になってしまった。75歳のヤンソンスの代役に82歳のメータが登場するのも驚きだが、さすがに「夜の歌」をそのまま振るわけにはいかず。正直なところ、また「巨人」か……と少々落胆していたのだが、これが予想を超えた凄絶な演奏に。長く記憶に残る一夜になった。
●まず、あのエネルギッシュでマッチョなメータが、老巨匠となって杖をついて登場し、晩年のカール・ベームのように椅子に座って棒を振る姿に動揺する。時の流れに思いを馳せずにはいられない。指揮台にはスロープが据えられて、助けを借りながら慎重に上るが、それでも足元にはらはらする。しかし座って棒を構えるとカリスマは健在。やはりメータは大指揮者。小編成、対向配置のモーツァルトでは、弦楽器のなめらかで温かみのある音色に聴き惚れる。「巨人」はまさかの「花の章」入りで第2楽章でびっくり。特にアナウンスされていなかったように思うのだが、プログラムノートにはちゃんとそう書いてあった。スケルツォから次第に火がついて、骨太で句読点を力強く打つメータらしさの片鱗が次第に顔を覗かせる。コントラバスのソロはかつて聴いたことがないほど流麗。終楽章は巨大な音楽になった。小さな身振りだったメータの棒が鋭角的になり、オーケストラが燃え上がる。壮絶なクライマックスを築いて、客席からは盛大なブラボー。アンコールはヨハン・シュトラウス2世の「爆発ポルカ」。ウィーン・フィルの来日中に他の外来オケでシュトラウスのポルカを聴くことになるとは。
●客席はさらに湧き上がり、スタオベ多数。メータは歩行が大変なのでカーテンコールは省略、客席もみんなで集中豪雨的に大喝采して一回で済ませようモードに。が、オーケストラが舞台から去っても拍手は止まず、最後は車椅子に乗ってメータが姿を見せた。客席にはキーシンの姿も。
●完成度でいえば前半のモーツァルトなのだが、何年もして思い出すのは、あのどこへ連れて行かれるか分からないような「巨人」にちがいない。
ニッポンvsキルギス代表@親善試合
 ●ニッポンvsキルギス代表を一日遅れでビデオ観戦。アジア・カップに向けて最後の親善試合は、同じアジアのキルギス代表。例によって欧州勢と対戦できないという事情もあるが、それ以上に本番のアジア・カップの前に中央アジア勢と対戦しておきたいということなんだろう。アジア・カップでは同じグループにウズベキスタンとトルクメニスタンが入っているのだから、これはもう必然のチョイス。会場は豊田スタジアム。
●ニッポンvsキルギス代表を一日遅れでビデオ観戦。アジア・カップに向けて最後の親善試合は、同じアジアのキルギス代表。例によって欧州勢と対戦できないという事情もあるが、それ以上に本番のアジア・カップの前に中央アジア勢と対戦しておきたいということなんだろう。アジア・カップでは同じグループにウズベキスタンとトルクメニスタンが入っているのだから、これはもう必然のチョイス。会場は豊田スタジアム。
●で、予想通り森保ジャパンは先日のベネズエラ戦からがらりとメンバーを変えて、Bチームというか、ほぼJリーグ代表みたいなチームを先発させた。GK:権田-DF:室屋、三浦弦太、槙野(→吉田)、山中亮輔-MF:守田英正、三竿(→柴崎)-伊東純也(→堂安)、原口(→中島)-FW:北川航也(→南野)、杉本健勇(→大迫)。試合は序盤から一方的なニッポンのペース。マリノスのイチオシ、左サイドバックの山中亮輔が代表デビュー。なんと前半2分に左サイドをかけあがって豪快なシュートを放つと、これがポストの右に当たってゴールへ。代表デビュー最速ゴール記録かも。マリノスではいわゆる偽サイドバックというか、攻撃時に中に絞ってプレイする山中だが、代表ではノーマルなサイドバックのポジションをしっかりとこなした。守備でも予想以上のがんばりで、これでポスト長友の一番手に躍り出たのでは。
●前半19分、フリーキックを原口が決めて2点目。しかしこれは相手キーパーのミス。キルギスはほとんどボールを保持できず、まったく攻め手がない。ニッポンは選手交代でAチームの選手を投入する。後半27分、守田が縦に入れたくさびのパスを、北川が技巧的なタッチで横に流して、これを大迫が蹴り込んで3点目。さらに後半28分には南野、堂安、中島の華麗なパス回しから、中島がシュートを放って4点目。相手との差が予想外にありすぎるのも考え物で、アジア・カップ本番で戦うウズベキスタンは到底こんなものではないはず。
●森保ジャパンはここまでが異常なほど順調で、監督本人はむしろ怖いくらいに感じているんじゃないだろうか。これだけチームが機能していると、このまま出来のいい選手をアジア・カップに連れて行くしかない。ほぼメンバーは見えてきたが、正GKはだれになるのか。自分の予想では、この2連戦に起用しなかった東口。あと、柴崎が燃え尽きていないか、気になるところ。
フランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィル&ラン・ラン
●20日はサントリーホールでフランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィル。プログラムはモーツァルトの「魔笛」序曲、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調(ラン・ラン)、ブラームスの交響曲第2番。皇太子殿下ご臨席。先日も書いたように、ラン・ランはこの協奏曲を携えてアジアでウィーン・フィルとベルリン・フィルを掛け持ちする人気ぶり。すっきり痩身になってスターのオーラ全開。細部まで入念に表情を付けたロマンティックなモーツァルトを披露。弱音の繊細な表現が印象的。アンコールにシューマンのダヴィッド同盟舞曲集から第14曲。非常にゆっくりとしたテンポで、美に耽溺するかのよう。
●後半のブラームスの交響曲第2番は、大らかな雰囲気で始まったが、進むにつれて白熱し、雄大な自然賛歌を描く。細部まで作り込んでおいた完成品を再現するというよりは、その場でみんなで作りあげた一期一会の音楽といった感。川崎公演でも感じたけど、ウィーン・フィルの弦楽器は明るくて華やか。終楽章の壮麗さは格別。アンコールはこの日もお家芸のワルツとポルカ。ヨハン・シュトラウス2世のワルツ「南国のばら」、E・シュトラウスのポルカ・シュネル「テープは切られた」。これは鉄道名曲で、ブラシで太鼓の表面を擦って蒸気機関を模したり、角笛みたいなので汽笛を表現したりと、かなり楽しい。
●シュトラウス・ファミリーの音楽がアンコールだと、いかにも「お開き」といった気分になるのだが、この日は拍手が続いて、ウェルザー=メストのソロ・カーテンコールあり。引き続いて皇太子殿下の退場でまた拍手。「殿下が選ぶ記憶に残るコンサート・ベストテン」みたいな記事があったらみんな読みたいと思うのだが、昔から皇室関連記事に強い「音楽の友」あたりでどうか。
映画「私は、マリア・カラス」(トム・ヴォルフ監督)

●プレス向け試写でドキュメンタリー映画「私は、マリア・カラス」(トム・ヴォルフ監督)を観た。えっ、まだカラスの映画が作られるの?とは思ったが、未公開映像がたくさん。監督はロシア生まれフランス育ちの若い映像作家。カラスの歌声に感銘を受け、世界中を飛び回って未公開の資料や映像、音源を探し、さらにはカラスの近親者や関係者たちに60時間以上のインタビューを敢行して、初の長編映画となる本作を作りあげたという。
●一言でいえば、邦題通りの「一人称のドキュメンタリー」とでもいえるだろうか。映像のほとんどはカラス自身を映したもので構成されており、カラスの視点で語られているのが特徴。伝説的なスターとなるが、ローマ歌劇場での途中降板がスキャンダルになり、海運王オナシスと出会い華やかなセレブの生活を送るも、ある日オナシスはジャクリーン・ケネディと結婚してしまう……。プライベートな映像や手紙が公開されていて、かなり赤裸々。そもそもこの時代の人でこんなにプライベート映像が残っているということが驚き。必然的に伝説の歌手というよりはひとりの強くて弱い女としてのカラスに焦点があたる。手紙に「オナシスと9年も付き合っていたのに、結婚を新聞で知りたくなかった」とか書いていて、痛々しい。ニューヨークでの本人のインタビュー映像からも、いろんな葛藤が伝わってくる。あと、今では考えられないことだが、メトの復帰公演のチケットを求めて早朝から若い人々が長蛇の列に並んでいる様子は印象的。
●次から次へと画面上に有名人が出てくるのだが、逐一説明は入らない。メネギーニ(元夫)とか、知らなかったらマネージャーのオッサンくらいにしか見えないと思う、途中までは。
●クラシックの音楽家で死後も延々と語られ続ける双璧はカラスとグールド。いったい本が何冊出ているだろうか。共通項は(ほぼ)みんな生では聴いていないということ。
●12/21(金)よりTOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマほか全国順次ロードショー。配給はギャガ。
ニッポンvsベネズエラ代表@親善試合
 ●この週末のサッカー界は代表ウィーク。ヨーロッパでUEFAネーションズリーグなる代表戦が創設されたおかげで、例によって森保ジャパンは欧州以外の対戦相手を探すしかなく、ベネズエラ代表と対戦。もっとも近年のベネズエラは強い。ベネズエラといえば、以前U-20ワールドカップ決勝トーナメントでニッポンが敗れた相手。その時の監督がドゥダメルだったが、今回のフル代表でもやはりドゥダメル監督なのであった。いまにも「マンボ!」と叫び出しそうな生きのいいサッカーを展開する(←投げやり)。
●この週末のサッカー界は代表ウィーク。ヨーロッパでUEFAネーションズリーグなる代表戦が創設されたおかげで、例によって森保ジャパンは欧州以外の対戦相手を探すしかなく、ベネズエラ代表と対戦。もっとも近年のベネズエラは強い。ベネズエラといえば、以前U-20ワールドカップ決勝トーナメントでニッポンが敗れた相手。その時の監督がドゥダメルだったが、今回のフル代表でもやはりドゥダメル監督なのであった。いまにも「マンボ!」と叫び出しそうな生きのいいサッカーを展開する(←投げやり)。
●で、年明けのアジア・カップに向けて新戦力と旧戦力の融合を進める森保監督だが、だいたい使いたい選手が見えてきた。おそらく今回のベネズエラ戦がほぼAチーム、次のキルギス戦がほぼBチーム的な布陣を組むのだろう、前回招集時のウルグアイ戦とパナマ戦でもそうしたように。GK:シュミット・ダニエル、DF:酒井宏樹、冨安、吉田、佐々木翔-MF:遠藤航、柴崎-堂安(→伊東)、南野(→杉本健勇)、中島(→原口)-FW:大迫(→北川)。フォーメーションは今回も4-2-3-1、攻撃陣はトップに大迫、2列目に堂安、南野、中島という形が森保ジャパンの基本形のよう。前にも書いたけど、2列目の選手が小さい。その分、キーパーとセンターバックは大型化していて、シュミット・ダニエルが197cm、 冨安が188cm、吉田が189cm。まあ、これでも世界基準では大きくはないんだけど。不在の長友の代役は佐々木翔。オフト・ジャパンの頃からニッポンの左サイドバックは層が薄いと言われ続けている気がする。控えにマリノスから山中亮輔が初選出されているのだが、彼の攻撃力は代表でも通用するはず。問題は守備。
●ベネズエラは前線からの守備の意識が強く、前半はニッポンがディフェンスラインからどこにボールを預けるかに苦労していた。普通なら下がって顔を出すのは柴崎の役目かなと思うのだが、もうひとつ受けに来てくれない感。戦術的な理由なのかどうなのか。お互いにチャンスの多い展開になったが、前半39分、フリーキックで中島のクロスからファーサイドに飛び込んだ酒井が足で合わせて先制ゴール。酒井はこれが代表初ゴールなんだとか。後半、ニッポンの中盤のパス回しは機能していたと思うが、追加点には至らず、逆に酒井のファウルからPKを与えて後半36分に失点。酒井は得点も失点も決めるワンマンショー。1対1。ニッポンは後半途中から攻撃陣を一通り入れ替えたが、先発組と控え組に落差を感じる。北川航也はシュート・チャンスを生かしきれず。引分けは妥当な結果。
●キーパーのシュミット・ダニエルは代表デビュー。仙台の選手だが、以前マリノス戦で見たときにセービングの不安定さを感じてどうかと思っていたが、なるほど、この選手は足元の技術がしっかりしている模様。キーパーがビルドアップに参加できるのは心強いが、さてなにを優先するか。アジア・カップで安定感のあるプレイをできればブレイクするかも。
●試合会場は大分スポーツ公園総合競技場。両チームとも大渋滞に巻き込まれて、ウォーミングアップもろくにできないギリギリの到着になるというアクシデント。観客のほうはもっと大変で、チケットは完売だったが、5000人以上が間に合わなかったとか。もともと立地的に渋滞の警戒されるスタジアムだったそうだが、雨や帰宅ラッシュ、事故などが重なって、すさまじい大渋滞が起きたという。こういうトラブルは事前の準備で防げるとも思えないんだけど、どういう対策が正解なんすかね。ググってみた感じでは、電車を使うと最寄駅から徒歩1時間12分。少々遠い。
ミューザ川崎でフランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィル
●15日はミューザ川崎でフランツ・ウェルザー=メスト指揮ウィーン・フィルへ。ベルリン・フィルは日本を素通りしていったが、ウィーン・フィルは来てくれた。ありがとうっ!(ヒシッ)。で、川崎だ。フロンターレ川崎のJリーグ連覇で全市民がフットボール熱に浮かれている川崎だが(←大胆な想像図)、そんな川崎をウィーン・フィルが訪れる。そうだった、ここは、音楽のまち・かわさき、フロンターレのまち・かわさき。
●プログラムは前半にドヴォルザークの序曲「謝肉祭」とブラームスのヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲(ヴァイオリン:フォルクハルト・シュトイデ、チェロ:ペーテル・ソモダリ)、後半はワーグナーの楽劇「神々の黄昏」抜粋(ウェルザー=メスト編、管弦楽のみ)。前回、クリーヴランド管弦楽団との来日公演で聴いたウェルザー=メストだが、ウィーン・フィルを相手にすればまったく違った音楽が生まれてくる。「謝肉祭」のにぎやかな総奏を聴いてウィーン・フィルならではの華やかで豊麗な響きを思い出す。やっぱりこれは至福の響き。白眉はブラームス。ソロもオーケストラもぴたりと一か所に焦点を当てて同じ絵を描く。ウィーン・フィルの「老舗の味」を、ウェルザー=メストが一段ぐっと引き締めてくっきりとしたサウンドに。大編成の「神々の黄昏」は壮麗。金管セクションがまろやか。抜粋といってもコンパクトで後半の尺が短めだなと思ったが、アンコールが2曲。ヨハン・シュトラウス2世のワルツ「レモンの花咲くところ」とポルカ「浮気心」。これはもうお家芸。ウィーン・フィル・スタイルで様式化されている。ワーグナーの荘厳な雰囲気からすごい落差なんだけど、最初が「謝肉祭」だったし、浮かれた気分で始まって浮かれた気分で終わるという趣旨でいいのかも。フロンターレ連覇を祝して(なわけない)。
エフゲニー・キーシン ピアノ・リサイタル
●14日は東京芸術劇場でエフゲニー・キーシンのピアノ・リサイタル。このホールでピアノ・リサイタルを聴く機会は珍しいかも。プログラムは前半がショパンの夜想曲第15番ヘ短調と夜想曲第18番ホ長調、シューマンのピアノ・ソナタ第3番、後半はラフマニノフの前奏曲集で、10の前奏曲op23の第1曲から第7曲まで、そして13の前奏曲op32の第10、12、13番を加えた計10曲。当初はベートーヴェン「ハンマークラヴィーア」が予定されていたのだが、その後、シューマンのピアノ・ソナタ第3番に変更になった。
●シューマンのピアノ・ソナタ第3番はかなり意外な選曲だけど、今シーズンのキーシンは熱心に取り組んでいるよう。昨シーズンもっぱら弾いていた「ハンマークラヴィーア」を、今季用の「新曲」に変更したと解せばいいのだろうか。ソナタとしては大作で、前半から一曲の交響曲を聴き切ったような気分。この曲、もともと、スケルツォ楽章なしの3楽章で「管弦楽のない協奏曲」として発表されたものを、後に初版で削られたスケルツォ(のひとつ)を復活させて4楽章のピアノ・ソナタにしている。そんな成立の経緯を思うと、「管弦楽のない交響曲」みたいな趣きも。作曲者のファンタジーと形式美があちこちで衝突を起こしているようなゴツゴツとした手触りが魅力なのか。鬱屈したポエジー満載。作品規模にふさわしい堂々たる力強い演奏に圧倒されるばかり。
●後半、ピアノの響きはぐっと輝かしさを増して、豪壮なラフマニノフへ。全身で楽器を鳴らし切る。多くの大作曲家たちの名曲は「神への供物」だろうけど、ラフマニノフは楽譜を通じて自身のピアニズムをキーシンに伝授しているかのよう。強靭で、スケールが大きく、情感豊か。
●アンコールは3曲。まずシューマンの「トロイメライ」で客席の興奮を収めて、続くいくぶんモダン風味のタンゴでふたたび会場をわかせる。知らない曲だなと思ったら、キーシン自作の「ドデカフォニック・タンゴ」なんだとか。最後はショパンの「英雄ポロネーズ」で、アンコールにふさわしい勢いと自在さで鮮やかに弾き切った。客席のほとんどがスタンディングオベーションという感動的な幕切れ。
ふたつの王者、Jリーグとアジア・チャンピオンズリーグ

●さて、日本のサッカー・シーズンがまもなく終わろうとしているので、備忘録を兼ねてふたつのチャンピオン・チームが誕生したことを記しておかねば。
●まずはJリーグ。なんと、川崎フロンターレが2連覇を達成してしまった。川崎のみなさん、おめでとうございます。一昨年まではシルバーメダル・コレクターの印象ばかりが強かった川崎。抜群の攻撃力を誇り、スペクタクルを見せてくれるけど、勝負弱い。そんな印象を覆したのが昨季のリーグ優勝。今季は前半戦で広島が独走状態に入るかと思われたが、広島の急激な失速もあって、川崎が連覇を果たした。特筆すべきは(まだリーグ戦は終わっていないが現時点で)リーグ最少失点の守備力。サッカーはやっぱり守りが堅くないと強くなれない。上の写真は昨シーズン終了後に川崎駅に掲げられた看板だが、本当に連覇してしまうとは。
●もうひとつ、アジア・チャンピオンズリーグ(ACL)で鹿島アントラーズがイランのペルセポリスを破って優勝。これは偉業。ホームで2対0とリードして、アウェイに乗り込んだところ、8万人収容のスタジアムはペルセポリス・サポでぎっしり。壮絶なアウェイ・ゲームだが0対0で耐えた。試合の様子をチラ見した限りでは、主審の笛も不安定で鹿島の選手にとってはストレスのたまる状況だったと思うが、これを耐え切ってしまう選手たちの成熟ぶりが印象的。これがジーコイズムなのか。ただ、ペルセポリス・サポはみんなブブゼラを吹いていたのが意外。まだブブゼラって売ってるんだ……。男たちの野太い声で応援されるほうが、プレッシャーはきつかったと思う。
●鹿島のなにがスゴいって、ACL決勝の第1戦と第2戦の間に中二日で迎えたJリーグの柏レイソル戦(アウェイ)を、先発11人総入れ替えのターンオーバーで戦って、しかも勝ってるんすよ。名前も知らない新人選手まで、みんな鹿島の看板を背負って戦う。マリノス・サポとしては、クラブ運営力の差にひれ伏すばかり。どうしてこんなに差が付いちゃったんすかね。
ジャナンドレア・ノセダ指揮N響のプロコフィエフ
●先週末の演奏会はもうひとつ、NHKホールでジャナンドレア・ノセダ指揮NHK交響楽団。前半にラヴェルのピアノ協奏曲(アリス・紗良・オット)、後半にノセダ独自選曲によるプロコフィエフのバレエ組曲「ロメオとジュリエット」抜粋。アリス・紗良・オット、最初に浜離宮朝日ホールで聴いたリサイタル以来、けっこうな回数を聴いていることになる。どんどん垢抜けたおねえさん風に。裸足で登場。クールなラヴェルのあとに、アンコールでねっとり濃厚なサティ「グノシエンヌ」を弾いて、強烈なコントラスト。あの世でサティが地団駄を踏んで悔しがってそうな気もするが、これも再現芸術のおもしろさか。
●後半のプロコフィエフはノセダの面目躍如たる凄演。垂直方向に高速往復運動する棒からエネルギーが噴出する。以前、カセルラの交響曲を指揮してくれたときにも感じたけど、このテンションが高さが最初から最後までまったく弛緩せず続くのがすごい。しかし響きのバランスは保たれていて明瞭。改めてこの曲におけるプロコフィエフの才気煥発ぶりに感じ入る。これだけキャッチーな曲を書けて、しかもオーケストレーションが鮮烈。チャイコフスキーの「くるみ割り人形」級のバレエ音楽の傑作だと思う。
●「野瀬田と申します」「夫です」。なわけない。
ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団の古典派プログラム
●10日は東京オペラシティでジョナサン・ノット指揮東京交響楽団。モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」、ストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲(神尾真由子)、ベートーヴェンの交響曲第4番というプログラム。古典~新古典~古典の変則古典派プログラムというべきか。弦楽器はいつもの対向配置で、モーツァルトではグッっと刈り込んでほとんど室内楽的。ストラヴィンスキーのヴァイオリン協奏曲では切れ味鋭いソロ。以前に聴いたリゲティと同様、ソリストと20世紀音楽の愛称のよさを感じる。カッコよさ、ユーモア、かわいさが一体となった稀有な名曲と再認識。
●圧巻は後半のベートーヴェンの交響曲第4番。これだけ精彩に富んだベートーヴェンを近年聴いたことがあったかなと思うほど。スピード感、ダイナミズム、スリル、今まさにそこで音楽が生み出されているという生々しさ、アンサンブルの愉悦、火花の散るような指揮者とオーケストラのやりとり。まれに聴く名演に心のなかで快哉を叫ぶ。
●ベートーヴェンの交響曲の緩徐楽章のなかでいちばん好きなのは、この第4の第2楽章。奇跡的な傑作。この曲についていつも言及されるシューマンの有名な言葉「ふたりの巨人にはさまれた可憐な乙女」というのは今日あまり共感されないと思うけど、当てはまるとすれば第2楽章だろうか。タン、タタン、タタン、タタンと執拗に刻まれるリズムに不気味さがあって、わりと不穏なタイプの乙女だと思う。精妙絶美、でも微妙に怖くて妖しい。
ベルリン・フィルとウィーン・フィルのアジア・ツアー
●先日、ベルリン・フィル・レコーディングスの記者会見の模様をレポートしたが、東京でベルリン・フィルの演奏会が開かれるわけではないんである。ベルリン・フィルのアジア・ツアー2018は本日、タイで開幕し、23日の北京公演まで続くのだが、今回は日本公演がない。でもアジアまで来るんだったら、東京でリサイタルを開いている内田光子と合流して、レコーディングスのほうの会見だけでも開いておこう、という流れだったのだろうか。ツアーの指揮者はドゥダメル。Twitterのハッシュタグ #BerlinPhilAsia18 で検索すると、今回のツアーの様子が伝わってくる。指をくわえて眺めたい。
●このベルリン・フィル・アジア・ツアー2018最終日の北京公演(23日)のみ、ラン・ランがソリストに招かれて、モーツァルトのピアノ協奏曲第24番ハ短調を弾く。日本にはまもなくウィーン・フィルがやってきて、やはりラン・ランがソリストで同じ曲を弾く。ラン・ラン側から見ると、11月のウィーン・フィルのアジア・ツアーのソリストを務めながら、その合間にベルリン・フィルのツアーにも出演して同じ曲を弾くということになっている模様。スーパースターだ。
グレグレグレの歌スタンプラリー
●昨日書いたように、2019年はシェーンベルクの大作「グレの歌」を首都圏で3つのオーケストラがとりあげるという、まさかの事態になった。読響、都響、東響、3団体の渾身の「グレ」祭り。もうこれはどう考えても「グレグレグレの歌スタンプラリー」をやるしかない。スタンプは作曲者の自画像をモチーフにこんな感じの図案でどうか。
●2019年3月14日 シルヴァン・カンブルラン指揮読売日響、新国立劇場合唱団他(定期演奏会)
https://yomikyo.or.jp/concert/2017/12/586-1.php

●2019年4月14日 大野和士指揮東京都交響楽団、東京オペラシンガーズ他(東京・春・音楽祭)
http://www.tokyo-harusai.com/program/page_6052.html

●2019年10月5日&6日 ジョナサン・ノット指揮東京交響楽団、東響コーラス他(ミューザ川崎シンフォニーホール開館15周年記念公演)
https://www.kawasaki-sym-hall.jp/news/detail.php?id=1015
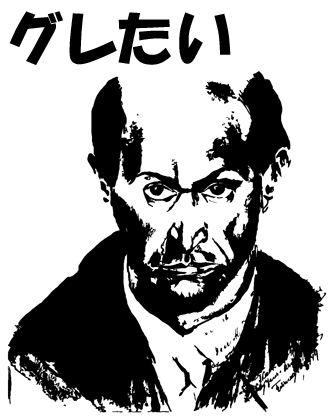
●シェーンベルク、なかなかの男前だぜー。
ジョナサン・ノット&東京交響楽団 Season 6 2019/20年シーズン・ラインナップ記者会見

●6日はミューザ川崎の市民交流室でジョナサン・ノット&東京交響楽団 Season 6 2019/20年シーズン・ラインナップ記者会見。もうSeason 6なのか、と、まずは軽い驚き。本題に入る前に、先日の東京と新潟でのラフマニノフの交響曲第2番の演奏についての話題が出た。大野楽団長「いつまでも終わってほしくないと思うような稀有な演奏会。奏者からも同様の声が聞こえた。ノットは魔法使い」。これを受けて、ノット「6年前、最初の会見で言ったように、これは旅。私たちにはこの旅路についてきてくれる聴衆がいる。終演後に感動を伝えてくれる人々と出会うごとに、この旅でしたかったことがここにあるのだと感じている」。
●で、2019/20年シーズン・ラインナップ(PDF)が発表された。ノットは東京に5回もやってくる。今シーズンも意欲的なプログラムが並んでいるが、一例をあげれば、ヨハン・シュトラウス2世のワルツ「芸術家の生涯」+リゲティの「レクイエム」+タリスの40声のモテット「スペム・イン・アリウム」+リヒャルト・シュトラウスの「死と変容」。人生と死をテーマにした実に凝ったプログラム。東響コーラスにとっての大きなチャレンジでもある。思わず心の「いいね」ボタンを押してしまったのは、アイヴズの「答えのない質問」とシューベルトの「未完成」交響曲の組み合わせ。Unanswered Question に対する答えが Unfinished Symphony 、みたいな。そして、年末の「第九」をノットが指揮するというのも大きな楽しみ。

●また、ミューザ川崎の開館15周年記念公演として、シェーンベルクの「グレの歌」が2公演、開催される。管弦楽150名、合唱250名の計400名規模の大作。節目の年の大作と言うことで、通常ならマーラーの「千人」などがとりあげられそうなところを、あえてシェーンベルクの「グレの歌」。この大作をライブで聴く貴重な機会が到来!……ではあるのだが、あれれ、この曲って東京・春・音楽祭で大野和士指揮都響が演奏するという話をつい先日ここに書いたばかりではないの。そして、3月にはカンブルラン指揮読響も同曲を演奏する。まさかの「グレの歌」首都圏三連発。こんな偶然って、あるんだ。渾身の企画がかぶりまくってグレそうになるところだろうが、こうなった以上は3つの楽団で「グレグレグレの歌」スタンプラリーをやるのが吉。シェーンベルクの自画像モチーフでスタンプの図案とか、作ってみたら楽しそう。
●もうひとつ新しいトピックス。音楽・動画配信サービス TSO MUSIC & VIDEO SUBSCRIPTION がこの日からスタートする。これは定期演奏会をはじめとしたライブ演奏の音声と動画の配信サイト。既発売のCDタイトルの音源も聴ける。株式会社フェイスのFANS(ファンズ)というプラットフォームを利用したサービス。プラットフォームのノリとしては、ファン・サイトみたいな感じで、グッズの販売もある。月額500円。これは期待したい。
ベルリン・フィル・レコーディングス2018秋・冬リリース発表記者会見

●5日はサントリーホールのブルーローズ(小ホール)で、ベルリン・フィル・レコーディングス2018秋・冬リリース発表記者会見。登壇者にはベートーヴェンのピアノ協奏曲全集のソリストである内田光子さんをはじめ、ベルリン・フィルのソロ・チェロ奏者オラフ・マニンガー、ベルリン・フィル・メディア取締役ローベルト・ツィンマーマン各氏。さらに内田さんの対談役としてオランダ・フィリップス・クラシックの元副社長である新忠篤さん、音楽評論家の山崎浩太郎さんと中川右介さんも。全3部にわたる90分超のゴージャスな会見になった。
●まず第1部は、サイモン・ラトル指揮によるマーラーの交響曲第6番「悲劇的」。これはラトルの最終シーズンを締めくくる記念碑的な演奏。今回も「包括的なコンサート体験をセットにしたい」(ツィンマーマン)と考え、パッケージにはBlue-rayディスクに演奏会の映像に加えてラトル時代を振り返るドキュメンタリー、96kHz/24bitのハイレゾ音声を収録し、加えて通常の音楽CD、さらに192kHz/24bitの超高音質音源ファイルのダウンロード・コードが付いてくるという、いつも通りの至れり尽くせり仕様。しかも、今回は1987年にラトルがベルリン・フィルにデビューした際に指揮したマーラーの交響曲第6番のCDも付いてくる。つまり、ラトルはベルリン・フィルのデビューと、首席指揮者としての最後の演奏会で、同じ曲を指揮したのである。
●マニンガー「これは圧倒されるような音楽です。ベルリン・フィルの首席指揮者とお別れするという演奏会をいったいだれが体験できるというのでしょうか。私たちにとって特別な演奏会になりました」「サー・サイモンがベルリン・フィルでの最初と最後の演奏会に同じ曲を選んだことがすごいのではありません。最初にまだ若い指揮者がこんな曲を選んだこと、選ばせてもらえたことが非凡なのです。この曲はむしろ、最後に選ぶのにふさわしい曲です。この間にサー・サイモンは血気盛んな若い指揮者から成熟した指揮者に変わりました。この間になにが起きたか、どれだけサー・サイモンが表現力を増したか、ふたつの録音から感じてほしい」
●第2部は内田光子独奏、サイモン・ラトル指揮によるベートーヴェンのピアノ協奏曲全集。こちらもBlue-rayとCDのセットで、演奏会映像とハイレゾ音源、CD音声、超ハイレゾ音源のダウンロード・コードがセットになっている。インタビュー映像付き。これは2010年2月に3週間にわたって行われた演奏会を収録したものだが、その時点ではこうしてパッケージでリリースする予定はまったくなかったのだとか。ラトルとのベートーヴェンの交響曲全集がリリースされた際に、ピアノ協奏曲もセットにできないかという話が持ち上がり、関係者全員の賛同を得てリリースに至ったという。
●内田「これだって9年も前の録音ですから、最初は嫌だと言ったのですが、とてもいいから本当に聴いてほしいと言われて聴いてみた。そうしたら生の演奏からしか生まれないバイタリティがあった。当時のベルリン・フィル、当時のサイモン、まだ若いなあと思った自分の三者が一体となった演奏だったから、そのときの記念として残したんです。本当は何度も同じ曲を録音して残したいとは思っていません。なんども録り直したけど、最初がいちばんいいということだってよくあること。これはある日の出来事の記念物。私にとってどんな録音にも絶対性はない。絶対性があるのは楽譜だけ」「ベルリン・フィルはいわば怪物。怪物と一緒に弾くという楽しさがある。サイモンが怪物かというと、どうでしょう、ベルリン・フィルのほうが怪物だと思います」。この言葉を横で聴いていたマニンガーが笑っていた。
●第3部は「フルトヴェングラー帝国放送局アーカイブ 1939-45」。マニンガー「ベルリン・フィルが自らキュレーションするアーカイブ・シリーズが、まずフルトヴェングラーで始まる。ベルリン・フィルにはさまざまな記録物があるが、これらを選別し、修復して、歴史的に価値のあるものから優先順位を考えて世に出したい。歴史的素材とどう向き合うかについてはいろいろな考え方がある。傷やノイズを消したほうがいいのかどうか。どちらかといえば、私たちはオリジナル重視の立場で忠実な再現を心がけた」。続いて、山崎浩太郎さんと中川右介さんが対談形式で、この録音の歴史的な背景やその意義、初出の音源などについて、詳細を語ってくれた。たとえば、古い磁気テープで常に問題となるピッチの問題については、当時のベルリン・フィルの438Hz基準でそろえた、等。その場でシュトラウスの「家庭交響曲」から一部が流されたが、なるほど、現代のデジタル編集技術をもってすれば、これくらいなまめかしいサウンドが聴けるのかという驚きがあった。
アラン・ギルバート指揮NDRエルプフィルハーモニー管弦楽団のマーラー、ブラームス他
●ドイツの放送オケの名前がどんどん略号だらけの長い名前に変わってしまい、一気になじみの薄い感じになってしまったが、NDRエルプフィルが次期首席指揮者アラン・ギルバートとともに来日。旧称は北ドイツ放送交響楽団。前回はトーマス・ヘンゲルブロックの指揮で聴いた。北ドイツ放送響とNDRエルプフィルではぜんぜん名前のイメージが違うけど、でもそれくらいイメージを一新させる名前がこのオーケストラにはふさわしいのかも。とても機能的で、豊麗で、くっきりしたサウンドを持つ国際色豊かなオーケストラ。すばらしくうまい。特に弦は強力。こちらもすっかり定着しつつある対向配置。
●プログラムはワーグナーの「ローエングリン」第1幕への前奏曲、マーラーの交響曲第10番よりアダージョ、ブラームスの交響曲第4番。今回のプログラムは前任者のヘンゲルブロックが決めたものなんだけど、これをアラン・ギルバートがそのまま引き継ぐことにしたというのがおもしろい。前半2曲、ワーグナーとマーラーはいかにもそのままつなげて演奏しそうな選曲で、もしそうなら効果抜群だったと思うが、普通に一曲ずつ演奏したのであった。一曲目の時点でハープに奏者が座っていなかったから、まあ、つながるわけがないんだけど(遅刻者も入場させなければならないし)。マーラーは細部まで彫琢されて、恐るべき完成度。ギルバートとNDRエルプフィルの音楽は常に明快、明瞭。その明瞭さを保ったまま、豊かなパッションが注ぎ込まれて、大きなうねりを作り出すところが魅力。後半のブラームスの4番はパッションの比重が一段と高まって、まれに見る熱気にあふれた名演に。どれだけ熱くなっても形が崩れないという安心感。アンコールはブラームスのハンガリー舞曲第6番。自在で遊び心あり。カーテンコールの途中で入ってきた奏者たちから察するに、アンコールはもう一曲、用意していた風でもあったんだけど、この一曲でおしまい。いずれにせよ、本編のブラームスの4番で満ち足りていた。
クリスティアン・ティーレマン指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団のシューマン
●1日はサントリーホールでクリスティアン・ティーレマン指揮ドレスデン国立歌劇場管弦楽団。二日間にわたるシューマン交響曲チクルスの二日目のみを聴く。交響曲第3番「ライン」と交響曲第4番という簡潔なプログラムだが、聴きごたえ十分。オーケストラは伝統の深く重厚なサウンドをこれでもかというくらい心地よく鳴らしてくれる。ティーレマンの指揮棒から少し遅れてズシリとしたサウンドが下から湧き上がってくるかのよう。その一方で、細部までデザインされていて、楽器間の分離も明瞭、輪郭もくっきりしていて、まったく鈍重ではない。説得力は半端ではなく、ひとつの理想形。弦楽器の配置はもはやすっかりおなじみ、コントラバスを下手に並べる対向配置。「ライン」でのホルンは絶品。
●シューマンの交響曲はどれもロマン派屈指の傑作だと信じているんだけど、なにが魅力かといえば、明るい曲調だろうが暗い曲調だろうが、どんなときでも鬱屈した情熱が渦巻いているところ。すごくロマン主義的だと思う。第4番の終楽章なんかが典型で、喜びが弾けているのに、そこにうっすらと憤怒が同居しているというか。この種の楽想の系譜はマーラーの交響曲第9番の第3楽章に受け継がれていると思う。それと、第4番は第2楽章でオーボエとチェロが一緒にソロを弾くじゃないすか。あの重複感が謎。どちらかだけならソロの見せ場なのに、ふたり一緒になるとどっちが主役なんだかわからない。あそこはふたりでぴたりと息を合わせるのが正解なんだろうか。
●あと「ライン」って全5楽章なんだけど、第4楽章を第5楽章に対するウルトラ長大な序奏とみなせば、第2楽章にスケルツォ、第3楽章に緩徐楽章が置かれるタイプの伝統的な4楽章構成になる。「執拗な序奏付きの交響曲」の系譜っていうのがありそう。前説に力が入りすぎて、それ自体がコンテンツとして独立しちゃった感というか。
藤倉大のオペラ「ソラリス」演奏会形式/日本初演
 ●31日、ハロウィンの夜は、東京芸術劇場で藤倉大のオペラ「ソラリス」(演奏会形式/日本初演)。渋谷の喧騒とはうらはらに池袋のこちら側は平和で安堵。これが舞台上演なら、客席も宇宙服コスプレとかソラリスの海コスプレ(ムリ)している人がいても似合ったのかも。で、この「ソラリス」、スタニスワフ・レムの原作は世界40か国語以上に翻訳されており、もはや世界文学の古典といってもいい名作。タルコフスキーとソダーバーグによって二度にわたって映画化されているが、このオペラはそれら映画とは一線を画して、かなりレムの原作のエッセンスに忠実なオペラ化となっている。台本はパリで世界初演された際の演出家でもあるダンサーの勅使川原三郎が日本語で書いたものを英訳。全4幕、休憩なしで90分ほど。
●31日、ハロウィンの夜は、東京芸術劇場で藤倉大のオペラ「ソラリス」(演奏会形式/日本初演)。渋谷の喧騒とはうらはらに池袋のこちら側は平和で安堵。これが舞台上演なら、客席も宇宙服コスプレとかソラリスの海コスプレ(ムリ)している人がいても似合ったのかも。で、この「ソラリス」、スタニスワフ・レムの原作は世界40か国語以上に翻訳されており、もはや世界文学の古典といってもいい名作。タルコフスキーとソダーバーグによって二度にわたって映画化されているが、このオペラはそれら映画とは一線を画して、かなりレムの原作のエッセンスに忠実なオペラ化となっている。台本はパリで世界初演された際の演出家でもあるダンサーの勅使川原三郎が日本語で書いたものを英訳。全4幕、休憩なしで90分ほど。
●開演前から客席の照明が落とされていて、芸劇のオルガンの銀色のモダン面に青白い光が照射されていた。さっそくソラリスの宇宙ステーション感たっぷり。本編に入ってからも照明が効果的に用いられていた。演奏は佐藤紀雄指揮アンサンブル・ノマドで、10数名のアンサンブル、ライブ・エレクトロニクスを駆使。歌手陣は主人公クリス・ケルヴィンにサイモン・ベイリー、ハリーに三宅理恵、スナウトにトム・ランドル、ギバリアンに森雅史、さらにオフステージのクリス・ケルヴィン役にロリー・マスグレイヴが配される。これは主人公クリスの心の声をオフステージで歌うという趣向で、この役の葛藤を表現する妙手。声楽陣は充実。それぞれ役柄にぴったりで、リリカルだが陰のあるクリス、清澄で無垢なハリーの対話は聴きごたえあり。実はこの物語の真の主役は惑星ソラリスを覆う知性体「海」そのものでもあるのだが、オペラという表現形態の性質上、人格も持たなければ音も発しない存在に対して役を与えることはできない。その代わりといっていいのかどうか、「海」の役割をもっぱら担っていたのは管弦楽だったと思う。特に終幕の後半、主人公がソラリスの海とそこから生成されるミモイドと対峙する部分が壮麗で、自分なりにミモイドの形態を想像を膨らませながら聴くことができた。一方、言葉をどう歌にするか、演奏会形式だけにこれだけのセリフ量を舞台装置や演技抜きで音だけで成立させるという点には難しさも感じる。
●で、レムの原作に忠実ではあるとはいっても、これはオペラなのでそれだけで独立して作品であるべきで、もちろんいろんな変更がある。ひとつは登場人物のひとりサルトリウスを割愛していること。それと最初に出現したハリーを脱出用ポッドに閉じ込めて宇宙空間に放出してしまう場面はない(原作では二人目のハリーが出現するんですよ!)。もちろん、ソラリス学を巡って延々と続く観念的な論述もオペラでは再現不可能だ。ソラリスの海という不可知な存在を描くことは潔くあきらめて、一方でハリーが自らの存在を自問自答する部分、クリスとハリーの愛の部分に焦点が当てられている。第4幕で、クリスがソラリスに残る決断をして、海と向き合うのは原作通りなのだが、言葉の選び方などには勅使川原色が出ていて、もう一段エモーショナルというか、レムとはまた違ったテイストが生まれていたんじゃないだろうか。
●ただ、やっぱり演奏会形式の難しさというか、これは古典的なオペラを上演する場合でも同じなんだけれど、言葉のない部分で起きる重大な出来事というのが、客席には伝わりにくい。たとえば、ハリーが最初にパニックになる場面。ハリーが扉の開き方がわからなくて力任せに開けたために大ケガをするのだが、傷がまたたく間に自己回復してしまい、ハリーの非人間性が表現される。これは原作を知らない人には、なにが起きているのか、わからなかったのでは。それと、ハリーが液体窒素を飲んで自己犠牲を図る場面も、やっぱりわらりづらい。古典であれば聴衆がストーリーを知っているという前提で割り切ることも一手だと思うけど、新作の場合はなにか補足的な手段で今なにが起きているかを伝える方法が欲しくなる。じゃあどうすればいいのかとなると難しいんだけど……。レムの名作がオペラになったという大きな喜びを感じつつも、舞台上演で見たいという気持ちも残る。アウグスブルクで上演された際のトレーラーはこんな感じ。