 ●お知らせを。まずは「音楽家の食卓」(野田浩資著/誠文堂新光社)。バッハ、ベートーヴェン、ブラームス、ワーグナーなど大作曲家ゆかりのレシピとエピソードを、六本木「ツム・アインホルン」の野田浩資シェフが綴った一冊。音楽面の記述について監修でお手伝いさせていただいた。料理を中心に美しい写真満載。ページをめくっているだけでお腹が空いてくる。はたして自分でも作れる料理が見つかるだろうかとレシピを眺めるも、ついつい手抜きと材料の代用ばかりを考えてしまうのは困ったもの。
●お知らせを。まずは「音楽家の食卓」(野田浩資著/誠文堂新光社)。バッハ、ベートーヴェン、ブラームス、ワーグナーなど大作曲家ゆかりのレシピとエピソードを、六本木「ツム・アインホルン」の野田浩資シェフが綴った一冊。音楽面の記述について監修でお手伝いさせていただいた。料理を中心に美しい写真満載。ページをめくっているだけでお腹が空いてくる。はたして自分でも作れる料理が見つかるだろうかとレシピを眺めるも、ついつい手抜きと材料の代用ばかりを考えてしまうのは困ったもの。
●もうひとつ。東京・春・音楽祭で毎年書かせていただいている短期連載コラム、今年のテーマはベートーヴェン。「友達はベートーヴェン」第2回「そのコーヒーを飲ませてくれないか」が公開中。ベートーヴェンが一杯あたりのコーヒー豆をきっちり数えていたという逸話はよく知られているが、いったいどうやってコーヒーを淹れていたのか、という話。
●もし現代にベートーヴェンが生きていたら、絶対にコーヒー・ミルにこだわっていたと思う。ワタシはカリタのナイスカットG派。
2020年1月アーカイブ
「音楽家の食卓」(野田浩資著/誠文堂新光社)
エサ=ペッカ・サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団のサロネン&マーラー
●29日はふたたび東京芸術劇場でエサ=ペッカ・サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団。プログラムはサロネンの自作「ジェミニ」とマーラーの交響曲第9番。当初は休憩なしで両曲が続けて演奏されると発表されていたが、予定を変更して休憩ありに。「ジェミニ」はそう短い曲ではないので、ありがたし。もともとはサロネンが自作「ポルックス」を指揮することになっていたのが、2019年10月にLAフィルで初演された新作「カストール」を追加した連作「ジェミニ」として演奏されることになった。カストールとポルックス、といえばラモーを思い出すが、ふたご座(ジェミニ)をなす星。先に演奏されたのは「ポルックス」で、カラフルなオーケストレーションで波打つ海のような響きが作られる。ラヴェルの「ダフニスとクロエ」を思わす官能性も。打楽器セクションのなかに和太鼓が入っているのが目を引く。後半の「カストール」は活発な音楽で、打楽器の執拗なパルスを伴って力強いフィナーレを築く。マーラーの3番のフィナーレを連想。
●後半のマーラーの交響曲第9番は、これまでに聴いた同コンビの演奏では最高度に練り上げられた名演だったと思う。多かれ少なかれ「彼岸の音楽」になりがちなこの曲を、キレッキレの造形と輝かしいサウンドで再現し、ほとんど晴れやかと言っていいほど。生を謳歌するマーラー9。こういうアプローチだと中間楽章により笑いの要素を感じることができる。終楽章はどう聴いても告別の音楽には違いないんだけど、それでもこのコンビが奏でると冒頭は安らかな喜びの音楽であり、最後に残るのは心地よい追憶の手触り。曲が終わったあと、客席に訪れた沈黙はかつてないほどの深さ。この曲やチャイコフスキーの「悲愴」などでは余韻を味わうために間を取られることは珍しくないが、ここまで完璧な静寂が保たれるとは。長い沈黙の後は一転して盛大な喝采、立ち上がるお客さんも多数。芸劇のお客さんはほかの主要ホールより少し若い印象があるんだけど、そのせいもあってか客席の反応が鋭敏な気がする。
●サロネンは長々とカーテンコールをくりかえさないので、さっさとコンサートマスターを連れ立って解散。客席の拍手はまったくおとろえず、指揮者のカーテンコールがあるわけだが、なんと、ソロ・カーテンコールが3回もあった。これも稀有なこと。サロネンは20/21シーズンを最後にフィルハーモニア管弦楽団を退任するので、ひとつの区切りでもある。
●なにが信じられないってサロネンが61歳という事実。風貌もさることながら、腕の動きのシャープさとか身のこなしの軽さが尋常じゃない。あれはどうなってるんすかね。
ゾンビとわたし その40:「ショパンゾンビ・コンテスタント」(町屋良平著/新潮社)
 ●書名からして、自分が読まずしてだれが読むのかという一冊、「ショパンゾンビ・コンテスタント」(町屋良平著/新潮社)。だって、ショパンでゾンビでなんすよ! 同じ著者の芥川賞受賞作「1R1分34秒」を以前に読んで、とても好印象を持っていたのでなおさら。
●書名からして、自分が読まずしてだれが読むのかという一冊、「ショパンゾンビ・コンテスタント」(町屋良平著/新潮社)。だって、ショパンでゾンビでなんすよ! 同じ著者の芥川賞受賞作「1R1分34秒」を以前に読んで、とても好印象を持っていたのでなおさら。
●主人公は音大のピアノ科に入学したものの、すぐに辞めてしまい、ファミレスでバイトをしながら小説を書く若い男。しかし小説も書きあぐね、友人の彼女に片思いをしたまま、煮え切らない日々を送る。時間はたっぷりとあるが、まだ何者でもない若者の不透明な日常が切り取られている。で、登場人物がYouTubeでなんども2015年のショパン・コンクールを見ているのだが(ケイト・リュウやエリック・ルーを見てる)、音楽面の描写に関しては「蜜蜂と遠雷」よりもよほど説得力があり、情景が伝わってくる。しかし焦点はそこに当たっていない。
●で、大事なことを言っておくと、ゾンビは出てこない(えっ!)。出てきません。比喩的な表現としてはともかく。なので老婆心から書いておくと、書名からゾンビ版「蜜蜂と遠雷」みたいなものを期待してはいけない。まさにそこにワタシの勘違いがあったわけで、書名から想像していたのは、たとえば、こんな話だ。
●ワルシャワの聖十字架教会をひそかにポーランドのマッドサイエンティストが訪れる。ここに眠るショパンの心臓からDNAを採取し、ショパンその人のクローンを生み出そうとする。ショパンの音楽を正しく演奏するにはショパンの肉体が必要。オーセンティックな演奏解釈について急進的な思想を持つマッドサイエンティストは、現代にショパンをよみがえらせようとしていたのだ。だが、心臓から肉体を再構築されたショパンはいったんは生命を宿したように見えたものの、再構築時の変成によりゾンビとなって生まれ変わっていた。ガブッ! 噛みつくショパンゾンビ。次々と人を襲いながらショパンゾンビが向かったのはワルシャワ・フィルハーモニー。今まさに開催中のショパン・コンクール本選にショパンゾンビが現われた。あっ、ショパンだ。舞台上で驚愕するコンテスタント。「握手してください」と手を差し出したところ、ショパンゾンビは容赦なくガブリ。そして生前の記憶を留めるショパンゾンビは鍵盤に向かい、やさしいタッチで演奏を始める。これが本当のショパンの音楽だ。一同、演奏に聴きほれるが、ショパンゾンビは納得しない。なんだこのキンキンした音を出す楽器は? エラールはどこだ。プレイエルはないのか。怒り心頭のショパンゾンビは客席に向かう。ガブッ! ガブッ! もはや入れ食い状態、阿鼻叫喚のフィルハーモニー。そして、ワルシャワ発のゾンビ禍は世界へ……。
●と、そんな妄想を爆発させていた自分はどう考えてもまちがっているのであって、このような純度の高い青春小説に対して、まったく申しわけないことである。
録音をなにで聴いているのか問題
●以前は「録音で音楽を聴く」といえば、シンプルにCDプレーヤー(等のプレーヤー)とアンプとスピーカーがあればよかった。もっと簡便にはミニコンポやラジカセという手も。でも今はいろんなスタイルがある。自分は音楽配信時代になってから、PCとオーディオ機器をUSB-DACで結んで、CDもストリーミングも同じ機器で聴く、というスタイルになった。今後はこれが基本形になってくんだろうなと漠然と思ってたけど、よく考えたらPCの存在を前提にしているのって、今どきどうなんだろ。なぜそこにあるスマホを使わないのか。
●そんなわけで、他人がどんな方法でクラシックの録音を聴いているのか、さっぱりわからなくなってしまったので、これをテーマに対談取材をさせてもらったのが、ONTOMOの特集「クラ活」音楽配信とガジェットを語る会。飯田有抄さんと、ONTOMO編集部の川上哲朗さんに参加していただいた。目からウロコの連続。そして、自分以外のふたりが同じWALKMANを使っていたことに衝撃。そ、そこで重なるんだ!?
飯森範親指揮東京交響楽団のラッヘンマン、アイネム、リーム、シュトラウス
●25日はサントリーホールで飯森範親指揮東京交響楽団。とても攻めたプログラムで、前半にラッヘンマンの「マルシェ・ファタール」、アイネムの「ダントンの死」管弦楽組曲 op.6a(日本初演)、リームの「道、リュシール」(日本初演、ソプラノに角田祐子)、後半にリヒャルト・シュトラウスの「家庭交響曲」。冒頭にマエストロと角田さんが登場して、本日のプログラムについてラフなトークあり。本当はラッヘンマンの「マルシェ・ファタール」も日本初演のつもりだったが、カンブルランが西のほうのオーケストラでアンコールに演奏して先を越されたというお話(広島交響楽団のことみたい)。
●前半は破滅プロ。「マルシェ・ファタール」はラッヘンマンの名から想像するような特殊な奏法満載の曲ではなく、本当にその名の通りマーチ。諧謔的な喧噪が続き、やがて同じ場所を壊れたレコードのように(という比喩が死語!)なんども反復する。その間、指揮者は客席に降りてくるなどの演出付き。最後にオチが付いて笑い。直前のトークのネタバレ感がなければもっとウケたはず。曲名は日本語にしづらいところではあるか。PCでのfatal error 致命的なエラーを連想するか、ファム・ファタールを連想するか。でも続く曲を聴くと、「破滅への行進」という文脈が浮かんでくる。アイネムの「ダントンの死」とリームの「道、リュシール」は続けて演奏され、どちらも共通の題材を扱っていて、フランス革命の立役者ダントンの処刑、そしてダントン派のデムーランの処刑を目にしたその妻リュシールの絶望が描かれる。最初にラッヘンマンを聴いた後だと、続く両曲が真摯な曲であるにもかかわらず、どこかパロディ的に聞こえてくるのがおもしろい。
●後半はぐっと日常的な題材になって夫婦や親子の日々の生活を描いた「家庭交響曲」。「ベルサイユのばら」を見てたら次に「サザエさん」が始まったみたいな流れ。この曲、何年か前にも同じコンビで演奏してなかったっけ。たしかマエストロ飯森の「家庭交響曲生オケ付き楽曲解説トーク」があって、「これがリヒャルトで、このテーマが妻パウリーネ、ここは息子のフランツ……」と実際に音を出して説明してくれたような。でもなんど聴いても、この曲は楽しい。なにがスゴいかって、そういった標題性抜きに、なんにも知らずに音だけ聴いても、壮麗なスペクタクルとして堪能できるところ。威勢のよい「家庭」。偶然だけど、同じ週に「英雄の生涯」(ルイージ&N響)も聴けて、「シュトラウスの自画像」シリーズができあがった。
エサ=ペッカ・サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団&庄司紗矢香

●23日は池袋の東京芸術劇場でエサ=ペッカ・サロネン指揮フィルハーモニア管弦楽団。チェロのトゥルルス・モルクが肺炎のため来日中止になり、当初予定されていたサロネン自作のチェロ協奏曲が、シベリウスのヴァイオリン協奏曲に変更。ソリストは庄司紗矢香。前半はラヴェルの組曲「クープランの墓」と、そのシベリウスのヴァイオリン協奏曲。庄司紗矢香のソロにただただ圧倒される。鮮やかなテクニック、音色の豊麗さ、雄弁さ、説得力に満ちていて、おまけに音が驚くほど強くて太い。オーケストラがかなり鳴らしているのに、強靭な音がギュンギュンと客席まで飛んでくる。サロネンの自作曲が聴けなくなったのは残念だったが、まさか曲目変更でこんな名演に出会えるとは。ソリスト・アンコールにパガニーニの「うつろな心」による序奏と変奏曲より。これがまたすごい。あまりに滑らかで、微塵も難度を感じさせない。
●後半はストラヴィンスキーの「春の祭典」。この曲は以前、同じコンビでも聴いているが、断然今回のほうが突き刺さった。フィルハーモニア管弦楽団、公演ごとに波のあるオーケストラという印象だが、これはもうすっかり手の内に入ったレパートリーで、会心の一撃が出た感。パワフルで鮮度マックス、キレッキレのハルサイ。アクセルを踏みっぱなしでコーナーを走り抜けてゆくかのような快感(ゲーセン的なイメージで)。冒頭ファゴットソロの荒ぶる感、第1部「大地の踊り」の爆発的なクライマックス、第2部序奏のトランペットの極端なミュートなど、細部までデザインされた鋼のストラヴィンスキー。最近のオーケストラ公演ではいつもそうだが、ホールの反響板がオルガンを隠す形で降ろされていてステージ上の空間がコンパクトになっていて、轟音が空間を飽和させて窮屈に感じるほど。客席は大いに沸きあがったのだが、サロネンは3回くらいのカーテンコールでさっさとコンサートマスターを引き連れて退出して、解散を促すのが吉。すぐに客席の熱が冷めるはずもなく、サロネンのソロ・カーテンコールが2回あって、盛大なブラボー。テレビ収録あり。
●芸劇の地下で VRサウンド・ステージTokyo というイベントが開催されていた。これはサロネンとフィルハーモニア管弦楽団によるマーラーの交響曲第3番の終盤5分間を、VRヘッドセットとヘッドフォンを装着して、あたかもステージ上にいるかのように体験できるというもの。
ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団のシュトラウス
●22日はサントリーホールでファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団。ウェーバーのオペラ「オイリアンテ」序曲、リヒャルト・シュトラウスの「4つの最後の歌」(クリスティーネ・オポライスのソプラノ)と交響詩「英雄の生涯」。コンサートマスターはライナー・キュッヒルで、キュッヒルの活躍の場がふんだんに用意されたプログラム。
●最近、コンサートの冒頭に序曲を置くパターンが減ってきているせいか、ウェーバーは久々な気がする。やはり名曲。そして、しみじみとした「4つの最後の歌」を艶やかなオポライスが歌う。豊麗なオーケストラのサウンドと歌唱が絶妙のバランスで溶け合う。「英雄の生涯」は聴きごたえ満点のスペクタクル。キュッヒルの存在感が半端ではない。N響の「英雄の生涯」はパーヴォとの精緻な演奏が記憶に新しいところだが、ルイージが率いるとパッションと推進力が前面に出てくる感。ルイージは指揮棒を持たず。後半は持つのかなと思っていたら、最後まで使わなかった。
●ルイージは読響で「英雄の生涯」を指揮したときもそうだったけど、終結部に一般的なバージョンを使わず、静かに消え入るように終わる初稿を用いていた。以前、ルイージが語っていたところによると、「人生を静かに振り返る老人の姿」が描かれるのだからこちらのほうがふさわしいのだとか。納得。同じように「後からより派手な終結部」が作られた例にバルトークの「管弦楽のための協奏曲」があるが、バルトークのほうは初稿だと損した感があるけど(なんだそりゃ)、シュトラウスのほうは初稿でもぜんぜん惜しくない。
Jリーグ新戦術レポート2019(西部謙司著/三栄書房)
 ●これは良書。「Jリーグ新戦術レポート2019」(西部謙司著/三栄書房)。現在のJリーグの戦術のトレンドがチームごとにコンパクトかつ明快にまとめられている。今季はもっとも急進的な戦術を採用するマリノスが優勝したとあって、戦術面で語るべきところの大きなシーズンだったと思う。マリノスのハイライン、ハイプレス、偽サイドバックの超攻撃的サッカーもさることながら、片野坂監督の大分やペトロヴィッチ監督の札幌など非常に多彩。ゴールキーパーにも足元がうまいタイプと、セーブ力を武器とする伝統的なタイプがいて、それぞれにチーム哲学が反映されていたと思う。
●これは良書。「Jリーグ新戦術レポート2019」(西部謙司著/三栄書房)。現在のJリーグの戦術のトレンドがチームごとにコンパクトかつ明快にまとめられている。今季はもっとも急進的な戦術を採用するマリノスが優勝したとあって、戦術面で語るべきところの大きなシーズンだったと思う。マリノスのハイライン、ハイプレス、偽サイドバックの超攻撃的サッカーもさることながら、片野坂監督の大分やペトロヴィッチ監督の札幌など非常に多彩。ゴールキーパーにも足元がうまいタイプと、セーブ力を武器とする伝統的なタイプがいて、それぞれにチーム哲学が反映されていたと思う。
●マリノス以外で印象的だったのは大分。この本では「疑似カウンター」って名付けられていて、なるほど。大分もマリノスと同様に自陣深くでもパスをつないでボールを保持するのだが、狙いはマリノスとぜんぜん違う。ハイプレスをかけてくるチームがボールを奪おうと前がかりになったところで、キーパー高木から正確なキックで前線の藤本憲明(神戸に移籍)につないで、あたかもカウンターアタックのような攻撃を作り出す。「疑似カウンター」というか、「セルフカウンターアタック」というか。最初の対戦でマリノスはまんまと罠にはまった。
●あと、Jリーグで3-4-2-1(3-6-1)がこれだけ広まっていたのも軽い驚き。森保監督も好む布陣で、J1だと広島、大分、札幌、浦和、湘南が採用している(J2ではもっと多いかも)。これに3-5-2のガンバ大阪、神戸、松本を加えた8チームが3バック勢。だいぶ4バックと拮抗している。そう考えると森保監督が3バックを敷くのも無理はないのか。ただし上位5チームはすべて4バックだったことも見逃せない。
●現代のサッカーは、バックラインに相手フォワードがプレスをかけてくるのが前提になっているので、いかに後方から相手のプレスをかわしてビルドアップするか、という点でチームごとになんらかの工夫が必要になる。キーパーを含むバックラインから、中盤の選手に前を向かせるまでのプロセスで、どれだけオートマティズムを持ち込めるか、というのがゲームを支配する鍵。
十二月の十日(ジョージ・ソーンダーズ著/岸本佐知子訳/河出書房新社)
 ●ジョージ・ソーンダーズの新刊「十二月の十日」(岸本佐知子訳/河出書房新社)を読む。多様な奇想で彩られた短篇集なのだが、おおむね共通するのはダメ男たちのストーリーであること。貧乏だったり、賢さが足りなかったりする男たちが、ピンチに直面して悪戦苦闘する。印象的だったのは「センプリカ・ガール日記」。娘が誕生パーティで惨めな思いをしないように、経済的な苦境にある父親が駆けずり回って、一発逆転の華やかなパーティを開く。ところが……。一見普通の現代アメリカの光景のように思えて、読み進める内に庭に設置する「SG飾り」なるものの正体がわかって慄く。笑ったのは「スパイダーヘッドからの脱出」。人間モルモットになって感覚を増幅する薬を投与された若者たちを描く。
●ジョージ・ソーンダーズの新刊「十二月の十日」(岸本佐知子訳/河出書房新社)を読む。多様な奇想で彩られた短篇集なのだが、おおむね共通するのはダメ男たちのストーリーであること。貧乏だったり、賢さが足りなかったりする男たちが、ピンチに直面して悪戦苦闘する。印象的だったのは「センプリカ・ガール日記」。娘が誕生パーティで惨めな思いをしないように、経済的な苦境にある父親が駆けずり回って、一発逆転の華やかなパーティを開く。ところが……。一見普通の現代アメリカの光景のように思えて、読み進める内に庭に設置する「SG飾り」なるものの正体がわかって慄く。笑ったのは「スパイダーヘッドからの脱出」。人間モルモットになって感覚を増幅する薬を投与された若者たちを描く。
●全体に「トホホ」では済まされない、身につまされる話が多い。苦くて、切ない。同時に、多くは救いのある話でもある。孤独ないじめられっ子の少年と自ら命を絶とうとする男の奇妙な出会いを描いた表題作もそうだし、巻頭のモテない少年の「ビクトリー・ラン」や、暴力的衝動に突き動かされる孤独な帰還兵の「ホーム」もそう。ダメ男たちに訪れるささやかな栄光の瞬間、と言えるのか。
クリストフ・エッシェンバッハ指揮N響とツィモン・バルト
 ●17日はNHKホールでクリストフ・エッシェンバッハ指揮NHK交響楽団。ブラームスのピアノ協奏曲第2番(ツィモン・バルト)とブラームス~シェーンベルク編のピアノ四重奏曲第1番のプログラム。「ほとんどピアノ付き交響曲」と「ピアノのないピアノ四重奏曲」という異形の傑作を並べたおもしろさ。
●17日はNHKホールでクリストフ・エッシェンバッハ指揮NHK交響楽団。ブラームスのピアノ協奏曲第2番(ツィモン・バルト)とブラームス~シェーンベルク編のピアノ四重奏曲第1番のプログラム。「ほとんどピアノ付き交響曲」と「ピアノのないピアノ四重奏曲」という異形の傑作を並べたおもしろさ。
●前半はツィモン・バルト・ワールド全開で、まったく独自のブラームス。入念でスケールの大きな表現で、フレーズのひとつひとつに重々しく意味づけするような演奏。古風で大仰ともいえるのだが、冒頭のソロから説得力があってぐいぐいと引き込まれる。エッシェンバッハがかねてより共演を重ねているのも納得。ボディビルダー体形で最強音から最弱音までを自在に繰り出し、余裕で幅広いダイナミックレンジを実現。譜面あり、自分で譜めくり。エッシェンバッハもピアノにぴたりと寄り添い、前へ前へと進むのではなく、一歩一歩立ち止まって考えるような、そして鮮やかではなく鈍色のブラームスを描く。鬱々とした曇天のブラームスは絶品。曇り空を突き抜けて朗々と歌うチェロのソロは辻本玲さん、ホルンは福川さん。強力。
●シェーンベルクは、どうしてブラームスのピアノ四重奏曲第1番を選んだんだろうか。この曲が好きだというシェーンベルク本人の言葉も残っているけど、やっぱりあの強烈な終楽章を編曲したかったんだろうか。三管編成プラス多彩な打楽器を活用したド派手なハンガリー舞曲デラックス。前半とは対照的な開放的なフィナーレに客席はどっと沸いた。
---------
●アシュケナージが引退を発表。もう82歳だったとは。寂しい話題ではあるが、自ら引退すると決めて、それをウェブサイトで発表するというあり方はいいなと思う。大昔、モーツァルトのピアノ協奏曲(たしか第17番)の弾き振りを聴いて大感激したのを思い出す。
カタールU23対ニッポンU23@AFC U-23選手権 グループステージ
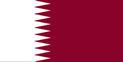 ●東京オリンピック男子サッカーの予選も兼ねたAFC U-23選手権が開催中。当欄では試合を追いかけていなかったが、ニッポンがグループステージで早々に敗退することになってしまったので、第3戦までを振り返っておこう。ここまで2敗1分。アジアの戦いでは近年まれに見る不調ぶりで、森保監督の解任論まで飛び出している模様。
●東京オリンピック男子サッカーの予選も兼ねたAFC U-23選手権が開催中。当欄では試合を追いかけていなかったが、ニッポンがグループステージで早々に敗退することになってしまったので、第3戦までを振り返っておこう。ここまで2敗1分。アジアの戦いでは近年まれに見る不調ぶりで、森保監督の解任論まで飛び出している模様。
●この大会、そもそもニッポンはなんのために参加しているのかという大きな疑問がある。東京オリンピックにはニッポンは開催国として出場できる。だったら、この大会、出なくてもいいのでは。そう言いたくもなるが、これはオリンピック委員会の大会ではなく、AFCのU-23選手権だから不参加というわけにはいかない。だから参加するんだけど、もちろんヨーロッパの選手は呼べない。例外的にスコットランドのハーツから食野が招集されているが、ほかに欧州組の五輪代表候補は8人ほどいる。加えて本大会でオーバーエイジを3人呼ぶとすれば、合わせてちょうど11人だ。ちなみに五輪はワールドカップと違って登録メンバーは18人のみ。となると、この大会のU23でオリンピックに出場できるのは何人いるだろう。なんだか、大人の事情だけでできあがったU23のチームっていう感じだ。
●これというのもFIFA(とAFC)の過密スケジュールのなかに、4年に1回、別団体主催の国際大会を無理やり突っ込んでいるからそうなるのであって、もう男子サッカーはオリンピックに参加しなくてもいいんじゃないだろうか。フルメンバーは無理だからU23という妥協点を見つけたはずが、妥協点としても機能していない。どうしてもやるならオリンピックはU17くらいの大会にしちゃうとか? いや、違うな。O35のマスターズ・サッカーにするのはどうか。中村俊輔やカズの雄姿が見られるぞ!
●カタール対ニッポン戦は主審がひどすぎた。前半48分に田中碧が一発レッドで退場したが、VARで映像を確認できるのに、まさかそんな判定が出るとは。田中碧の足は先にしっかりとボールの上に乗っていた。ファウルですらあったかどうか。盛大に負け惜しみをすると、後半33分のカタールのPKだってかなり怪しい。だいたいカタールはアジア・チャンピオンで、フル代表のメンバーまで参加しているのに、一人少ないニッポン相手にようやく五分の戦いをして1対1で引き分けたわけで、この試合で頭を抱えるべきはカタール。11人と主審が力を合わせて、10人のニッポンとやっと引き分けた末に、オリンピック出場権を逃す始末。ニッポンは第1戦も第2戦も酷い戦いではあったが、この第3戦は胸を張っていい。
●それにしても森保監督は本大会でも3バックを採用するのだろうか。国内では3-6-1のチームがずいぶん増えているようだが、海外組にとってはなじみが薄いはず。
オーケストラ・アンサンブル金沢 ニューイヤーコンサート2020
●15日は紀尾井ホールでオーケストラ・アンサンブル金沢のニューイヤーコンサート2020。指揮は首席客演指揮者のユベール・スダーン(さすがにミンコフスキは出てこない)。親しみやすい小品中心のプログラム構成で、前半はソプラノの森麻季、後半はコンサートマスターのアビゲイル・ヤングがソリストとして活躍。
●前半ではモーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の第1、第2、第4楽章の各楽章とヘンデルのアリアを交互に演奏するという趣向が珍しい。森麻季さんによるヘンデルの「オンブラ・マイ・フ」「涙の流れるままに」他、清澄な声を堪能。後半も、クライスラー「愛の喜び」→シュトラウス兄弟の「ピツィカート・ポルカ」→クライスラー「愛の悲しみ」→ルロイ・アンダーソンの「プリンク、プレンク、プランク」といったように、クライスラーとピツィカートの曲を交互に演奏するなど、曲順が特徴的。ほかにグリーグ「ホルベルク組曲」抜粋、チャイコフスキーの「弦楽セレナード」ワルツ、モンティの「チャールダーシュ」など、耳なじみのいい曲が並んだ。「チャールダーシュ」でそれまでおとなしめだった客席がぐっと沸く。最後にバルトークの「ルーマニア民俗舞曲」。この日の白眉。
●井上道義前音楽監督時代であれば、最後にマエストロのマイク・パフォーマンス(?)が入るところだが、スダーンがマイクを握って出てくるはずもなく、アンコールにクライスラーの「美しきロスマリン」。アビゲイル・ヤングが音楽でしっかり締めてくれた。今回は弦楽器のみの編成だったこともあって、いくぶんしっとりした雰囲気の「ニューイヤーコンサート」に。
 ●左は会場で配布されていた石川県立音楽堂とオーケストラ・アンサンブル金沢の情報誌「カデンツァ」。これが鏡餅。金沢育ちの自分は成人してからかなり経つまで、鏡餅とは全国どこでもこういうものだと信じて疑わなかった。初めて東京のスーパーで「紅白ではない鏡餅」が大量に並んでいるのを目にしたときは、てっきり業者のミスで事故が起きたのだと思ったほど。
●左は会場で配布されていた石川県立音楽堂とオーケストラ・アンサンブル金沢の情報誌「カデンツァ」。これが鏡餅。金沢育ちの自分は成人してからかなり経つまで、鏡餅とは全国どこでもこういうものだと信じて疑わなかった。初めて東京のスーパーで「紅白ではない鏡餅」が大量に並んでいるのを目にしたときは、てっきり業者のミスで事故が起きたのだと思ったほど。
ルーターを新調してパケットさらさら
 ●家でスマホを使っていると、Twitter上の画像や動画の表示、あるいはGmailの添付ファイルを開いたりするのに、妙に待たされることがあった。スマホの性能不足かと思いあまり気に留めていなかったのだが、外出しているときにはそんな現象は起きない。どうしてなのかな、まるでパイプが詰まっていてなにかがつかえているかのような遅さだなあ、光回線の速度は十分出ているはずなのに……と思ったところでハタと気づく。これって、ルーターのせいじゃないの!?
●家でスマホを使っていると、Twitter上の画像や動画の表示、あるいはGmailの添付ファイルを開いたりするのに、妙に待たされることがあった。スマホの性能不足かと思いあまり気に留めていなかったのだが、外出しているときにはそんな現象は起きない。どうしてなのかな、まるでパイプが詰まっていてなにかがつかえているかのような遅さだなあ、光回線の速度は十分出ているはずなのに……と思ったところでハタと気づく。これって、ルーターのせいじゃないの!?
●現行のルーターはずいぶん古い世代の非力な機種。導入当時は主にノートPCをつなげるためのものだったが、今やスマホだタブレットだミニタブレットだKindleだScanSnapだとWi-Fiを使うデバイスが飛躍的に増えている。数えてみたら計10台の機器がルーターにぶらさがっている。これらをいくつも同時に使うことは少ないが、多くの機器はバックグラウンドでアプリを更新したり位置情報をやりとりしたりするわけで、石器時代のルーターには重荷だったにちがいない。
●そんなわけで、おニューのルーターをゲット。機種はなじみのあるAtermからWG1200HS3を選ぶ。導入したところ、それまでがウソのようにヒュンヒュンと処理が軽くなった。排水溝の詰まりにパイプフィニッシュ!みたいなお掃除スッキリ感。パケットがさらさら流れるのが目に見えそう。Twitterもなにもかも高速化。
●ひとつ感動したのは、Atermの「Wi-Fi設定引越し」機能。既存ルーターがWPSに対応していれば、SSIDや暗号化キーをそのまま引っ越せる。おかげでスマホなど各デバイス側はなにも設定を変える必要なし。この簡単さは大吉。
ミーツ・ベートーヴェン シリーズ vol.1 仲道郁代

●10日は東京芸術劇場へ。年末年始は演奏会から遠ざかっていたので久々の公演。芸劇前の広場にグローバルリングができていて、なんだかキラキラしていて、池袋っぽくない。
●この日はベートーヴェン生誕250年企画「ミーツ・ベートーヴェン シリーズ vol.1 仲道郁代」。ベートーヴェンのピアノ・ソナタを2種類のフォルテピアノとモダンピアノで弾くという趣向。全体は3部構成になっていて、第1部は演奏前に20分強のトークが置かれ(急遽入ることになったそう)、平野昭、太田垣至、仲道郁代各氏が登壇。ベートーヴェンの創作期間が楽器の発展と重なっており、曲によって使用音域が違っている等のレクチャー。その後、J.A.シュタイン(1790年モデル/61鍵/米ツッカーマン製)でピアノ・ソナタ第8番「悲愴」とピアノ・ソナタ第14番「月光」第1楽章のみ。10分の短い休憩をはさんで第2部はブロードウッド(1816年モデル/73鍵/ジョン・ブロードウッド&サンズ製)でピアノ・ソナタ第30番。さらに15分の休憩をはさんで第3部はヤマハCFXでピアノ・ソナタ第14番「月光」とピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」。ピアノという楽器のダイナミックな変遷をたどる盛りだくさんの構成。フォルテピアノはいずれも奏者所有。
●はたして東京芸術劇場の大ホールで、フォルテピアノが聞こえるものか。いちばん気になったのはその点なのだが、思ったよりも音はちゃんと届く。2階席だったのでステージからの距離はけっこうあったのだが、音量的な不満はあまり感じない。楽器の後方に透明な反響板あり。ただ、広大な空間と残響のなかに埋もれてしまった要素も少なからずあったんじゃないかなとは思う。ニュアンスというか、身振りというか。
●最大の驚きは、モダンピアノが鳴り響いた瞬間。それまでフォルテピアノの音に順応していたから、「月光」の冒頭が巨大音響の塊として鳴り響く! なんという太い、金属的な轟音なのか。強烈な違和感。ところが、聴いているうちにだんだん慣れてきて、「ワルトシュタイン」が始まる頃にはもうなんの違和感も感じないし、音の強靭さに圧倒されることもなくなる。いつものピアノだ。「月光」冒頭が巨大音響だったのに、「ワルトシュタイン」はごく普通の音に聞こえる。人間の慣れって怖い!
●アンコールがおもしろい。「エリーゼのために」をまずはヤマハで弾き始め、途中でシュタインへ移動、さらにブロードウッドへと楽器を替えながら演奏する。いったん演奏を止めて、しずしずと別の楽器へ歩いてから、また続きを弾き始めるという優雅な聴き比べ。客席の反応は上々。
バレリア・ルイセリ「俺の歯の話」(白水社)
 ●(一昨日から続く)もう一冊は新刊でバレリア・ルイセリの「俺の歯の話」(松本健二訳/白水社)。メキシコ出身ながらスペイン語と英語の両方で小説を書く著者による、パチューカ生まれの競売人のささやかな成功と失敗を描いた物語(パチューカといえば本田圭佑が一時期所属していたクラブだ)。歯小説であり収集癖小説でもありアートギャラリー目録小説でもあるという、まったくオリジナルな作品。中南米出身の作家に対して期待されるような、ローカル色豊かな小さな逸話の集積にもたしかにおもしろさがあるのだが、筆致は至って現代的で、アメリカから遠くに眺めるスペインの風景といった感。いくぶん都会的な線の細さも漂う。
●(一昨日から続く)もう一冊は新刊でバレリア・ルイセリの「俺の歯の話」(松本健二訳/白水社)。メキシコ出身ながらスペイン語と英語の両方で小説を書く著者による、パチューカ生まれの競売人のささやかな成功と失敗を描いた物語(パチューカといえば本田圭佑が一時期所属していたクラブだ)。歯小説であり収集癖小説でもありアートギャラリー目録小説でもあるという、まったくオリジナルな作品。中南米出身の作家に対して期待されるような、ローカル色豊かな小さな逸話の集積にもたしかにおもしろさがあるのだが、筆致は至って現代的で、アメリカから遠くに眺めるスペインの風景といった感。いくぶん都会的な線の細さも漂う。
●著者はてっきり男性だと誤解して読んでいたが、途中で(名前が示すように)女性だと気づいて軽く驚く。スペイン語と英語を自在に行き来する著者だが、自作をスペイン語から英訳する段階で大幅に改稿され、翻訳が再創造になるという創作プロセスが興味深い。
--------
●お知らせを。東京・春・音楽祭のサイトに拙稿掲載。毎年短期連載させてもらっているコラムで、昨年のシェーンベルクに続いて、今年はベートーヴェン。「友達はベートーヴェン」第1回「運命はかく扉を叩くvs鳥のさえずり」。ご笑覧ください。
新国立劇場2020/21シーズンランナップ説明会

●8日午前、新国立劇場の2020/21シーズンランナップ説明会へ。オペラ、舞踊、演劇の三部門の芸術監督がそろって会見する貴重な機会。今回から舞踊は次期舞踊芸術監督の吉田都さんが登壇。写真左より小川絵梨子演劇芸術監督、吉田都次期舞踊芸術監督、大野和士オペラ芸術監督。まず3演目共同の記者会見が開かれて、その後、部門ごとに分かれて懇談会形式で集中的に質疑応答を行ういつものスタイル。
●で、オペラ部門の2020/21シーズンランナップだが、大野体制の3期目ということで、当初の発表通り一年おきに制作される日本人の新作第2弾、およびダブルビル第2弾が新制作に含まれている。新制作は4つ。公演順にブリテン「夏の夜の夢」、藤倉大「アルマゲドンの夢」、ストラヴィンスキー「夜鳴きうぐいす」&チャイコフスキー「イオランタ」のダブルビル、ビゼー「カルメン」。
●まず「夏の夜の夢」だが、演出はデイヴィッド・マクヴィカー。指揮はイングリッシュ・ナショナル・オペラ音楽監督を務めるマーティン・ブラビンス。というか、日本では名フィル元常任指揮者と言ったほうが通りがいいかも。なお、これはモネ劇場のプロダクションを新国立劇場で購入したもの(ケントリッジ演出の「魔笛」と同様のケース)。
●日本人新作は藤倉大「アルマゲドンの夢」。大野さんが「現代に通じるテーマを持った作品を」とリクエストしたところ、藤倉さんが選んだのは、なんと、H.G.ウェルズ原作の短編。ウェルズといえばSF小説の始祖のような存在だが、「マーラーやリヒャルト・シュトラウスの同時代人」と紹介されていて、なるほど。この「アルマゲドンの夢」は従来の邦訳では「世界最終戦争の夢」と題されていると思う。昔は「アルマゲドン」なんていう言葉は日本語では通用しなかったから、「世界最終戦争」と翻訳されていたんだろう。台本はこれまでの藤倉作品で共同制作が多いハリー・ロス。演出はリディア・シュタイアーで、「問題意識の掘り起こし方の深さに定評がある」。英語台本で藤倉大作品ということで、国際的に発信力のある作品になりそう。藤倉大のオペラといえば、以前、東京芸術劇場で「ソラリス」が演奏会形式で上演されたのを思い出すが、「ソラリス」の原作はスタニスワフ・レム。レムの原作はSFの枠を超えた世界文学の名作として広まっているが、今回のウェルズの原作はSFの枠のなかでも歴史に埋もれつつある古い小説。レムに比べると台本や演出で創意を発揮する余地が大いにあるんじゃないだろうか。ちなみにこの作品、もうできあがっているんだとか。オーケストラは三管編成、合唱も入るそうなので、「ソラリス」よりもずっと大きな編成の作品になる模様。
●ダブルビルは「夜鳴きうぐいす」と「イオランタ」。童話オペラを並べていると同時に、以前から大野さんが言っていたロシア・オペラのレパートリーの蓄積もできるという一石二鳥の二本立て。「夜鳴きうぐいす」は「ストラヴィンスキーの作風の変化がひとつの作品に内包されている大変な傑作」。
●「カルメン」の演出はアレックス・オリエ。「トゥーランドット」での大胆解釈が物議をかもしたというか、むしろ物議をかもしきれなかったきらいがあるのだが、さて「カルメン」はどうだろう。「トゥーランドット」での前例を考えると、「だったらカルメンがホセを返り討ちにするのかな」「それとも心中しちゃう?」「案外ふたりとも生き残ったりして」など、いろんな期待を呼ぶ。なお、大野監督は「アルマゲドンの夢」と「カルメン」の2演目を指揮する。
「ミゲル・ストリート」(V・S・ナイポール著/岩波文庫)
 ●年末年始、たまたま続けて強烈な辺境性を宿した新旧ふたつの物語を読んだ。ひとつはV・S・ナイポールの「ミゲル・ストリート」(小沢自然・小野正嗣訳/岩波文庫)。ノーベル賞作家が1959年に書いたデビュー作で。昨年、文庫になった。イギリスの植民地だった頃のトリニダード島の街が舞台で、登場する男たちはだれもかれもダメ男と変人ばかり。ろくに働いていない男だらけで、やたらとラム酒を飲み、子供と奥さんを殴る。どうしようもない連中だが、どんな変人でも共同体の一員として受け入れてしまう南国的な大らかさがあって、だれも飢える者はいない不思議な街。
●年末年始、たまたま続けて強烈な辺境性を宿した新旧ふたつの物語を読んだ。ひとつはV・S・ナイポールの「ミゲル・ストリート」(小沢自然・小野正嗣訳/岩波文庫)。ノーベル賞作家が1959年に書いたデビュー作で。昨年、文庫になった。イギリスの植民地だった頃のトリニダード島の街が舞台で、登場する男たちはだれもかれもダメ男と変人ばかり。ろくに働いていない男だらけで、やたらとラム酒を飲み、子供と奥さんを殴る。どうしようもない連中だが、どんな変人でも共同体の一員として受け入れてしまう南国的な大らかさがあって、だれも飢える者はいない不思議な街。
●おかしな話が満載だが、とりわけ印象的だったのは「機械いじりの天才」の章。クルマをいじられずにはいられないオジサンが、修理するといってはクルマを壊してしまう。わからないのなら触らなければいいのに、どうしてもいじってしまう。なんだか身につまされる。目次を見た時点でわかるように、最後に主人公は教育を受けるためにこの街を後にする。どこか故郷を「見捨てる」ような話の閉じ方が、この連作短編集の肝なんだと感じる。(つづく)
天皇杯は神戸へ。創設以来の初タイトル

●今頃お正月の話題が続くのもなんだが、今年の天皇杯決勝は元旦の新国立競技場が舞台だった。当初のザハ・ハディド案が破棄され、あれやこれやの紆余曲折があって、もはや「サッカー場」としての存在感が意識からすっかり抜け落ちていた新国立競技場だが、はっと気がついたら競技場は完成していて、こけら落としが天皇杯決勝だったんである。チケットは完売。録画をゆるく眺める。
●対戦カードはヴィッセル神戸vs鹿島アントラーズ。常勝軍団の鹿島だが今季はいまだ無冠。といっても、あれだけ主力選手が欧州に移籍しても、リーグ戦は3位だし天皇杯でも決勝まで来ているのが恐るべきところ。試合は18分に神戸がラッキーなオウンゴールで先制(藤本憲明のゴールかオウンゴールかよくわからなかった)、さらに38分にまたしてもラッキーな藤本憲明のゴールで追加点。全般に拮抗した戦いに思えたが、結果は2対0で神戸が完勝。クラブ初のタイトルを獲得した。新しい国立競技場の門出で悲願の初タイトルを手にしたのだから、神戸のファンにとってはたまらない元日決戦だっただろう。
●神戸が楽天化して以来、イニエスタの年俸に3年間で約100億円みたいな、Jリーグの従来の常識では考えられない巨額の予算がつぎこまれるようになったものの、これまで結果が付いてこなかった。ひとりふたりのスーパースターが来ても勝てないのがサッカー。でも気がつくとじわじわとディフェンスの強化も進んでいて、3バックの一角にはフェルマーレンがいるし、酒井高徳の加入も相当に効いている。イニエスタやポドルスキやビジャがいなくても、この調子で堅実に強化していけば安定した強豪チームになりそうなもの。それにしても藤本憲明はJFLからJ3、J2、J1と上がってきて、最後はイニエスタといっしょにプレーしてゴールを決めてタイトルを獲得しているわけで、サッカーマンガを地で行く展開。
●マリノス・ファンとしては、シーズン途中で移籍した飯倉大樹が神戸でタイトルを手にしたことがうれしい。出て行った者も、残った者も、最後は笑ってシーズンを終えられた。
●新国立競技場の歴史に残る最初のゴールがオウンゴールだったことに、サッカーの神様のイジワルさを感じずにはいられない。
ウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサート2020
 ●元旦のウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサートは、お正月モードでテレビをつけっぱなしにしてチラチラと見た。指揮はアンドリス・ネルソンス。ゲヴァントハウス管弦楽団と来日したときにも書いたけど、すっかり恰幅がよくなって視覚的にも巨匠然としている。たまに腕の動きにカルロス・クライバーを連想するが、聴いた感じはメリハリが効いていて、むしろマゼールを思い出す。ロンビの「郵便馬車のギャロップ」では昔取った杵柄でトランペットを披露。
●元旦のウィーン・フィル・ニューイヤー・コンサートは、お正月モードでテレビをつけっぱなしにしてチラチラと見た。指揮はアンドリス・ネルソンス。ゲヴァントハウス管弦楽団と来日したときにも書いたけど、すっかり恰幅がよくなって視覚的にも巨匠然としている。たまに腕の動きにカルロス・クライバーを連想するが、聴いた感じはメリハリが効いていて、むしろマゼールを思い出す。ロンビの「郵便馬車のギャロップ」では昔取った杵柄でトランペットを披露。
●今回はなにかと話題が多かった。ベートーヴェン・イヤーということで「12のコントルダンス」抜粋がバレエ付きで。それとヨーゼフ・シュトラウスの曲がずいぶん多いなあと思ったら、没後150年だった。150は中途半端な気もするのだが、ウィーン・フィルが記念の年だというのなら文句は言えない。ワルツ「ディナミーデン」は昨秋ティーレマン指揮ウィーン・フィルが「ばらの騎士」組曲と並べて演奏していたように、オックス男爵のワルツの元ネタ(らしい)。この曲は「ばらの騎士」との関連を抜きにしても秀作。「ディナミーデン」というのは造語らしいので日本語に訳出されないのはしょうがないんだろうけど、副題が「秘めたる引力」で分子や原子が引き合う力を指しているんだとか。分子運動をワルツに見立てるという意味では、同じヨーゼフの代表作「天体の音楽」で星々の運行をワルツに見立てたのと似た発想。元エンジニアらしいアイディアというべきか。ヨーゼフはワルツ史上もっともミクロな視点によるワルツともっともマクロな視点によるワルツを書いたことになるんじゃないだろうか。
●最後の「ラデツキー行進曲」は「非ナチ化」のために楽譜を一新するというニュースがあったが、ぱっと見ではいつもの恒例「ラデツキー行進曲」の光景。むしろあの手拍子をどうにかしようという指揮者はいないのか。
●来年はムーティが指揮するそう。2018年に続いてまたも。
「いだてん」と国立競技場

●謹賀新年。本年もよろしくお願いいたします。
●録画でようやく大河ドラマ「いだてん」最終回を見たのだが、ドラマ中に登場したかつての国立競技場(国立霞ヶ丘陸上競技場)に度肝を抜かれた。あ、あれはまさにワタシが知ってる国立競技場ではないの! もう存在しないスタジアムが、あそこにある。あれはCGなのか、セットなのか。本当によくできていて一気にいろんな記憶がよみがえってきた。
●あの競技場にはほんの一部しか屋根がなかったので、雨が降れば濡れる。カッパ必須だが、雨と風と寒さが辛すぎて、途中から通路に避難して、たまに試合の様子を覗くなんてこともあった。これは裏技だが、実はスコアボードの真下のあたりに雨宿りができるわずかなスペースがあり、そこに逃れたこともある。
●Jリーグが始まる以前、トヨタカップ(欧州チャンピオン対南米チャンピオンの試合)はここで開催されており、普段はマイナースポーツのサッカーもこのときばかりは客席が埋まった。だが、当時の日本人にはサッカーの応援スタイルがなかった。だから、もっぱら静かに集中して試合を観戦していた、まるでクラシックのコンサートのように。ACミランがやってきたとき、フォワードには当時のスター・ストライカー、ジャン=ピエール・パパンがいた。コーナーキックのボールを取りに来たパパンに対して、近くにいたひとりの客が静けさに耐え切れないというかのように「ジャン=ピエール!」と叫んだ。もちろん、声はピッチに届く。パパンは片腕を挙げて軽くガッツポーズをとってくれた。世界最強チームのスーパースターに対して、だれでも一声かければ声が届く。そんな牧歌的な時代の聖地が国立競技場だった。