
●29日はサントリーホールでサマーフェスティバル2020、第30回芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会へ。芥川也寸志サントリー作曲賞(旧称は芥川作曲賞)は新進作曲家のオーケストラ作品を対象に演奏会形式により公開選考を行うという賞で、受賞作曲家には新作が委嘱され、2年後にその初演が行われる。まずは、その2年前の受賞者である坂田直樹の委嘱作品「手懐けられない光」が世界初演され、続いてノミネート作品である冷水乃栄流(ひやみず・のえる)「ノット ファウンド」、小野田健太「シンガブル・ラブ II - feat. マジシカーダ」、有吉佑仁郎「メリーゴーラウンド/オーケストラルサーキット」の3作品が演奏された。演奏は沼尻竜典指揮新日本フィル。
●演奏後に公開選考会(選考委員は金子仁美、福井とも子、望月京)が開かれ、意見は小野田作品と冷水作品で2対1に割れたが、多数決的に小野田作品の受賞が決まった。なお、公開選考会に先立って聴衆による非公式な投票「SFA総選挙」が行われ、そちらは1位が冷水作品(45%)、2位が有吉作品(28%)、3位が小野田作品(27%)。受賞作への票がいちばん少なかったという結果に。
●3曲について、自分なりに感じたことを以下にメモ。冷水乃栄流の「ノット ファウンド」はベートーヴェンの「第九」を解体再構築したような作品。2019年5月に初演された曲なんだけど、世界観として「合唱(歓喜の歌)不在の第九」が設定されていて、結果的に時宜を得た作品になっている。ウイルス禍で「第九」が歌えるかどうかわからないベートーヴェン・イヤー、という意味で。しかしそういった文脈がなくとも、崩壊し風化した「第九」として純粋に楽しめる。オーケストレーションは精妙で、基本的なトーンは楽しくて明るい。作曲者のプログラムノートによると、文明が退廃した世界での人間活動の痕跡といった視点があるようで、このノリは共感できる。ポストアポカリプス的な世界観、さらに言えば「ポストアポカリプスなんちて的世界観」でもあって、今日のゾンビ禍(ウイルス禍ではなく)を巡る諸々の表現や考察と遠くなく、また最近当欄で紹介したデイヴィッド・マークソン著の実験的小説「ウィトゲンシュタインの愛人」(国書刊行会)とも通底する要素があると思う。ただ、曲を耳にしてすぐにワタシは別の作品を連想してしまって、それはマイケル・ゴードン作曲の「ベートーヴェンの交響曲第7番を書き直す」。ジョナサン・ノット指揮バンベルク交響楽団の録音があるのだが、第7をリライトしたという、いじわるな笑いとカッコよさが同居する曲。あと、曲名の「ノット ファウンド」からは、まっさきに404のエラーメッセージを連想した。サーバー管理者がいなくなって、ドメインの有効期限が切れて 404 Not Found。そういうイメージも共有可。
●小野田健太の「シンガブル・ラブ II - feat. マジシカーダ」も洗練された美しい響きのする曲。マジシカーダとは北米の周期ゼミで、その周期性を持った生態と求愛行動から90年代J-POPを連想し、作曲者が考える「90年代的ダサさ」を曲に潜ませているという。ところが自分は90年代J-POPというものをまったく知らず、その文脈に従ってこの曲を聴くことができない。この日の候補作のなかではもっとも「ネタがわからない」曲。でも聴衆投票で自分はこの曲に票を投じた。というのも、セミ感や夏感は伝わってきて、ノスタルジーという形で明快に感情に訴えかける要素があったから。包装紙や化粧箱みたいな意匠も大事なんだろうけど、箱の中身、つまり聴いてなにか自分の内面に影響を及ぼす要素がなければ、わざわざ遠い場所まで足を運んで音楽を聴こうとは思えないので。
●有吉佑仁郎「メリーゴーラウンド/オーケストラルサーキット」は、舞台上の指揮者を中心にサークル状に奏者を配置して、円の間を音響を移動するというアイディアを持った作品。しかしサントリーホールの豊かな残響のなかでは、音像に定位感は得られず、ステージ上の音はひとつの塊となって響く。舞台上の指揮者の位置で聴けばエキサイティングな体験だったはずだが、客席にいると音が遠い。しかも指揮者も手前側の奏者も背中を向けているので、視覚的な疎外感も味わう。遊園地のメリーゴーランドに乗るのは大好きだが(怖くない貴重な乗り物)、乗らずに眺めているだけだとかなり寂しい。もっとも、このホールを前提に書かれた曲ではないので、聴衆と演奏者が同じ平面にいるような場所であれば話はぜんぜん違ってくる。
2020年8月アーカイブ
サントリーホール サマーフェスティバル2020 芥川也寸志サントリー作曲賞選考演奏会
マスクの夏
●8月もそろそろおしまい。結局、ウイルス禍の酷暑をみんなマスクをしながら過ごしたことになる。屋外では一時的にマスクを外している人もいるが、お店や電車のなかではほぼ全員がマスク着用(少なくとも東京では)。コンビニで買い物をしようと出かけたけど、うっかりマスクを持参するのを忘れて引き返すみたいなこともたびたび。財布を忘れてもSUICAがあれば買い物できるけど、マスクがないと買い物できない時代が到来。真夏のマスクという光景が本当にやってくるとは! マスク、強し。
●一方、カフェなどでは普通にお客さんが入っていて、おしゃべりに興じている様子が目に入ってくる。世間は斑模様。今こそ私語厳禁の名曲喫茶の出番かも。ワタシ自身は緊急事態宣言以降、相変わらず打ち合わせ、会議、インタビュー取材はすべてリモートのまま。
●2週間経って、お盆休みの影響がそろそろ数字に出てもいい頃なので、現状を確認しておこう。都内の新規陽性者数は以下の通り(出典は東京都の対策サイト)。7日移動平均を見ると8月上旬にピークをつけて、その後は緩やかに下がり続けている。今のところお盆休み効果は見られず。
●久々に各国の人口あたり新規感染者数の7日移動平均を見ると、米仏を除いてどこも似たような水準になっている。特にスウェーデンは高齢者を切り捨てる集団免疫路線などと言われつつも、今はその他の欧州やアジアとそう変わらない。
ベルリン・フィルの新シーズン開幕公演、8/29 20時より「時間差再配信」へ
●キリル・ペトレンコ指揮によるベルリン・フィルの新シーズン開幕公演が8月29日に開かれる。もちろん、デジタル・コンサート・ホールでライブ配信されるのだが、今季はなんと、日本時間の20時から「時間差再配信」をしてくれるのだとか。ライブだと日本時間午前2時スタートなので、これまでは数日後にアーカイブに掲載されるのを待つしかなかったが、29日(土)20時ならとても観やすい時間帯。プログラムはシェーンベルクの「浄夜」とブラームスの交響曲第4番。演奏そのものも大いに楽しみだし、ウィルス禍にあってベルリンでは公演がどんな形で開かれているのかという点も気になる。短いプログラムだけど、休憩は?
●「時間差再配信」って新しい言葉だと思う。「ライブ配信」でも「アーカイブ」でもない、その中間というか。よく考えたら公演はすでに終わっているのだから本質的にはアーカイブだと思うんだけど、20時からスタートです!って言われると、ライブに臨むような心持ちになる。
マリノスvs広島 J1リーグ第12節 ようやく今季初連勝
●緊急事態宣言で世の中がストップした分、学校は夏休みを短縮してハイペースで授業を進め、Jリーグは真夏に週に2試合のハイペースで試合を開催している。冬が来るとまたどうなるかわからないから、巻き返せるうちに巻き返しておきたい。そんな気分の2020年夏。
●で、週末のJリーグだ。実は今日も試合があるわけだが、せっかくマリノスが勝ったので軽く振り返っておこう。というか、サッカーファンとしてはどうかと思うのだが、DAZNの生配信では最後の20分くらいしか観てなくて、無事に勝ったとわかってから、残りの70分を再生するという安心観戦。勝つとわかっているゲームを観るのは気持ちが楽だなあ……って、それはスポーツ観戦としておかしいのだが。
●相変わらず試合ごとにころころとメンバーが変わるマリノスだが、この試合はポステコグルー監督の目指すサッカーができたと思う。極端に高いディフェンスライン、精力的なプレッシング、キーパーも含めてディフェンスラインから多数のパスをつないでノンストップで相手ゴールを目指す攻撃的なサッカー。ボール保持率やパスの本数の多さもさることながら、肝はプレイ強度。後半になっても激しさと運動量は衰えず、この部分ではっきりと広島を上回っていた。パススピードも速くて、見ているとなんだかヨーロッパの強豪チームみたいだなと錯覚する……が、現実はこれが今季初の連勝。順位は上がったといっても8位。スタイルは立派でも、結果が伴うかどうかはまた別。実際、広島には序盤から後半までビッグチャンスがいくつもあったので、決めるべきところで決めていればぜんぜん違った試合になっていたはず。マリノス 3-1 広島。
●この試合でも柏からローンでやってきたジュニオール・サントスが大爆発。高い打点からの豪快なヘディング・シュートを決めた。こんなパワフルな選手が昨季までほとんどベンチでくすぶっていたとは信じられないが、オルンガの陰に隠れていたということなのか。ただ粗削りではある。松本山雅からローンの前田大然は遠藤渓太が抜けた左ウイングでプレイ。ポジション的には問題なく、意外と早くチームに適応している。好プレイがいくつもあった。ただ、あと一歩、プレイの確実性がほしいところ。逆に右サイドで復帰した昨季MVP仲川は見せ場を作れず。その分、マルコス・ジュニオールが獅子奮迅の活躍。
●マリノスのみメンバー。GK:朴一圭-DF:小池龍太、實藤友紀、チアゴ・マルチンス、ティーラトン-MF:喜田拓也、扇原貴宏、マルコス・ジュニオール(→渡辺皓太)-FW:仲川輝人(→松田詠太郎)、ジュニオール・サントス(→エリキ)、前田大然(高野遼)。トップチームのスタッフに新型コロナウイルス感染者が一名確認されたが、選手やチームスタッフに濃厚接触者はいなかった。また、これに伴って監督、コーチ、選手、スタッフの計68人のPCR検査を受けて、全員が陰性となっている。
働き方について
●緊急事態宣言の間をどう過ごしていたかといった話題を、ちょうどいま出回っている媒体でいくつか見かけた。中でも驚いたのは、新国立劇場の会報誌 The Atre に掲載されているダンサー・振付家の中村恩恵さんのインタビュー。感染が広がっているのに、医療従事者やライフラインを支える人たちは一生懸命に働いている、なのに踊りだけやってきた自分はなにもできない。そこまではよく聞く話。そこから先が違う。普段買い物をしているスーパーが人手不足で困って募集をしているのを見て、応募して働いているって言うんすよ! ベーカリーでパンを袋詰めにしたり、買い物かごを拭いたり。この話を読んで、ワタシはドカーンと圧倒された。そして、スーパーの人たちは中村さんをどういう方だと認識したのだろうか。
●ANAの機内誌に「翼の王国」がある。今の状況でこの冊子を手にする人は少ないと思うが、自分は機内番組の仕事に携わっているので毎月送ってもらっている。8月号の吉田修一さんのエッセイ「空の冒険」で、ウイルス禍による自粛生活で休み方のコツをつかんだ人が多いんじゃないかと書かれていた。つまり、それまではワーカホリック気味で、仕事をしないと不安になって週末になると「早く月曜日にならないかなあ」と思っていたのだが、いったん休み方のコツをつかめば気分よく休日を過ごせるという話。仕事をしないと不安になる心情は、個人事業主ならみんな覚えがあるはず。ワタシもどちらかといえば月曜日にマイルドなワクワク感を抱くタイプなのだが(今週はどんな仕事をできるのかな~という期待感。ゲームで新ステージに入る感じに似ている)、一方でぐうたらしていたい、怠けたいという気持ちもとても強い。安心して怠けられるのが最強だが、そんな身分は遠い。
●あと、これもびっくりしたんだけど、日経ビジネスの小田嶋隆さん連載「ア・ピース・オブ・警句」。最近の回「君、最近休みをとったのはいつだね?」のなかで、氏はこの30年来、執筆に充てるのは週に3日だけだと書いている(そして経済的不安を感じなかった日々はほとんどないとも)。これはある意味で目から鱗。執筆日は週に3日だけであっても、ネタを考える時間も入れれば「完全な休養日は一年のうちに何日もない」とも見なせるのはよくわかる話。そもそも個人で仕事をしていると、経理や総務や営業もぜんぶ自前でやるので、本質業務に充てられる時間は実は案外少ない。忙しいと神経が参るが、ヒマだと不安になるという真実は、つい最近別の場所でも目にしたけど、だれが書いていたんだっけ。
「ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン」 ジョン・ウィリアムズ指揮ウィーン・フィル
 ●まさかジョン・ウィリアムズがウィーン・フィルを指揮して自作を振ってくれるなんて! もう最高すぎる。なんでこの選曲なの、どうしてあの曲は入ってないの?など、思うところもあるが、これは唯一無二の価値を持ったアルバム。一気に聴くともったいないので、ちびちびと聴いている。配信でも聴ける一方で、パッケージでは「ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン」デラックス盤としてUHQ-CD/MQA+Blu-ray付のバージョンもリリースされている(MQAは対応機器があればハイレゾで聴けて、通常CDとも互換性があるという不思議な規格、らしい)。
●まさかジョン・ウィリアムズがウィーン・フィルを指揮して自作を振ってくれるなんて! もう最高すぎる。なんでこの選曲なの、どうしてあの曲は入ってないの?など、思うところもあるが、これは唯一無二の価値を持ったアルバム。一気に聴くともったいないので、ちびちびと聴いている。配信でも聴ける一方で、パッケージでは「ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ウィーン」デラックス盤としてUHQ-CD/MQA+Blu-ray付のバージョンもリリースされている(MQAは対応機器があればハイレゾで聴けて、通常CDとも互換性があるという不思議な規格、らしい)。
●やはり「スター・ウォーズ」のメイン・タイトルには耳を奪われる。ジョン・ウィリアムズ本人が指揮していても、これはウィーン・フィルの「スター・ウォーズ」。ロンドン交響楽団やハリウッドのオーケストラとは少々趣が異なる、壮麗で格調高い「スター・ウォーズ」。ここにはキレのあるパワフルで突き抜けるようなブラスセクションはないかもしれないが、それに代わる芳醇な響きがある。木目調の「スター・ウォーズ」とでもいうか。ウィーン・フィルには以前ヴェルザー=メストの指揮による同曲の録音があったが、あれはシェーンブルン宮殿の野外コンサートを収録したもので、残響の不足が惜しい録音だった。
●「スター・ウォーズ」のメインタイトルというと、自分は「帝国の逆襲」のロンドン交響楽団による演奏を聴くことが多かったのだが、冒頭での若干歪み気味のめいっぱいの強奏を聴くと、脳内スクリーンには「遠い昔、はるか彼方の銀河で……」のテロップが画面奥へとスクロールしてゆく。しかしこのウィーン・フィルの「スター・ウォーズ」はそうならない。本編から独立した20世紀後半の管弦楽曲として鳴り響くコンサートホールの「スター・ウォーズ」。たぶん、映画「スター・ウォーズ」はこれから忘れ去られることになる。特に最後の3作、エピソード7~9があんなことになってしまった以上、もはや伝説のシリーズとは言えない。でも、曲は残るんじゃないだろうか。マスネのオペラ「タイス」を観たことがなくても「タイスの瞑想曲」は知っているように、あるいはロッシーニのオペラ「ウィリアム・テル」を観たことがなくてもその序曲は楽しめるように、「スター・ウォーズ」のメインタイトルも映画本編より長生きするにちがいない。
●「帝国のマーチ」にもどこかエレガンスを感じる。ハプスブルク帝国の逆襲だ。
25周年

●当サイトは1995年8月21日に開設された。つまり本日、開設から25年が経ったことになる。「え、25年前にインターネットがあったの?」と思われるかもしれないが、あったんである。ただし、そこはまだ開拓時代の荒野のような場所で、とても小さかった。ウソのようなホントの話だが、ワタシが当サイトを作った時点では、GoogleもAmazonもYahoo! Japanもなかったし、日本企業のウェブサイトも珍しかった。日本語サイトといえば大学や個人サイトが大半で、その気になればそのほとんどすべてを目にできるのではないかという小さな村といったイメージ。今、25歳未満の人は、生まれた瞬間からこのサイトがあったんすよ! 笑。しかし25年も続けていて、この進歩のなさはいったいなんなのか。
●目下、このサイトに求められているのはSSL化。つまりhttpsで始まるセキュアなサイトにすること。しかしこれが実はそう簡単な話でもない(一瞬、検討はした)。一から作るのなら容易なんだけど、既存のものを生かすとなるとこれがねえ……。すっかり増改築を繰り返した老舗旅館みたいになってるので、本当は全面的に作り直したい気もするのだがどうしたものか。ここはデザインの面でも技術の面でも手作り要素が強すぎるので、本当は既存サービスを活用して身軽にしなきゃいけない。
●はっ。記念すべき25周年の日に反省ばかり呟いている。まあ、しかたがない。何事も経験を積むにしたがって力不足を感じることが増えてくるもの。無理せず、楽しんで書けるのが第一。
清水エスパルスvsマリノス J1リーグ第11節 クラモフスキー監督とポステコグルー監督の師弟対決
●実のところ今季のマリノスは戦績がさっぱりで、試合を観るのがしんどい。週末のアウェイ大分戦で負けて、週中の水曜日はアウェイの清水戦。清水の監督は昨シーズンまでマリノスでポステコグルー監督の右腕としてコーチを務めていたクラモフスキー監督。オーストラリア代表でもずっとポステコグルーのもとで活躍してきた。ちなみにふたりともオーストラリア国籍だと思うが、ポステコグルーはギリシャ出身、クラモフスキーは北マケドニア系。
●で、クラモフスキー監督率いる清水は、まったくマリノスと同じ哲学に基づく攻撃的なチームに変貌していた。ボールを保持して、自分たちから仕掛けていくアタッキング・フットボール。両者ともに同じような戦術で攻めあった結果、ノーガードの打ち合いみたいな派手な試合に。本来、前線からのプレスも激しくいきたいところだが、夏場とあって選手間の距離は広くなりがちで、前半から攻撃のための十分にスペースは十分。合計7ゴールが飛び出して、清水 3対4 マリノス。かろうじて師匠が面目を保ったものの、ボール保持率もシュート数もほぼ五分五分。中盤で潰し合いをする膠着状態がほとんどなく、スペクタクルの連続という意味では好ゲームなのだが、攻撃がスムーズすぎて微妙に薄味のゲームのようにも。いや、それは2万人収容のスタジアムに3千人しか入っていないという観客席の「疎」のせいなのか?
●マリノスは毎試合メンバーが大幅に変わる。2チーム分どころか3チーム分くらいの戦力でミックスされた混成軍みたいになっている。顔のないチームというか。GK:朴一圭-DF:松原健、チアゴ・マルチンス、實藤友紀、高野遼-MF:喜田拓也、和田拓也(→扇原貴宏)、マルコス・ジュニオール(→渡辺皓太)-FW:仲川輝人(→松田詠太郎)、ジュニオール・サントス(→オナイウ阿道)、前田大然(→エリキ)。2ゴールのジュニオール・サントスは新戦力で柏レイソルからのローン。先制点はハーフライン手前から独走して豪快に決めた度肝を抜くスーパーゴール。とても昨季ノーゴールの選手には見えない。今後は同じポジションをジュニオール・サントスとオナイウ阿道とエジガル・ジュニオの3人で争うのか。ポルトガルから帰ってきた前田大然は松本山雅からのローン。松田詠太郎は19歳の生え抜きで、SC相模原にローンに出していたのだが急遽呼び戻すことになった選手。すごい選手層だが、結果は4勝5敗2分で9位。むむむ……。
「クラシック音楽演奏・鑑賞にともなう飛沫感染リスク検証実験報告書」
●一般社団法人日本クラシック音楽事業協会、公益社団法人日本オーケストラ連盟、公益社団法人日本演奏連盟ほかで構成された「クラシック音楽公演運営推進協議会」が、「クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(PDF)を公開している。これは必見。複数の感染症専門家の協力を得て、演奏会における飛沫感染リスクが実験を通して検証されている。特に奏者間の距離や客席間の距離についての提言は重要で、「演奏者およびマスク着用下の客席において、従来の間隔の場合でも、ソーシャルディスタンスを取った場合と比較して飛沫などを介する感染リスクが上昇することを示すデータは得られなかった」(ホルン、トランペット、トロンボーンについては注釈あり)。感染症対策に限った話ではないが、漠然としたイメージや思い込みだけで議論しても事態は一歩も前に進まないわけで、定量的な議論が不可欠だと改めて感じる。
●この報告書はとても明快に書かれていて、まず最初に「提言のまとめ」があって、それから実験目的と実験概要、実験結果とその考察と続く。今回の実験の限界についてもきちんと記述されている。音楽業界にいるとこういった筋道だったレポートを目にする機会はなかなかない。
●飛沫がどれだけ飛び散るかをどうやって測定しているかというと、大気中の微粒子を排除した高清浄度実験室(クリーンルーム)で実験を行って、各方向に設定した9台のパーティクルカウンターで微粒子数を測定している。「3.2 客席」の項では客席での発声や咳、ブラボーを再現し、各々にマスクありマスクなしでも測定。マスクの効果はとても大きい。今後は客席の間隔よりも、マスクの着用や会話を控えることに焦点が当たることになるのでは。
「八月の光」(ウィリアム・フォークナー著/光文社古典新訳文庫)
●本日、浜松で国内最高の41.1度を記録。35度超の猛暑になると「体温を超えそう」などと話題になるが、これはもはやお風呂の温度に匹敵する。日本の8月はどこまで暑くなるのか。
 ●さて、夏は名作を読む季節、読書感想文の季節。8月でもあるしと手にとったウィリアム・フォークナーの「八月の光」(黒原敏行訳/光文社古典新訳文庫)。さすが20世紀アメリカ文学の大傑作というべきか、なんと翻訳が6種類もある。しかも近年の「新訳」に限っても、岩波文庫版の諏訪部浩一訳があって、この光文社古典新訳文庫版の黒原敏行訳がある。名作オペラが新時代の演出により新たな角度から光を当てられるのと同じように、小説もこのように今の日本語による新訳で作品が生まれ変わってゆく。スゴくないすか、日本人は6種類もの「八月の光」を読めるんすよ。アメリカ人は一種類しか読めないのに!
●さて、夏は名作を読む季節、読書感想文の季節。8月でもあるしと手にとったウィリアム・フォークナーの「八月の光」(黒原敏行訳/光文社古典新訳文庫)。さすが20世紀アメリカ文学の大傑作というべきか、なんと翻訳が6種類もある。しかも近年の「新訳」に限っても、岩波文庫版の諏訪部浩一訳があって、この光文社古典新訳文庫版の黒原敏行訳がある。名作オペラが新時代の演出により新たな角度から光を当てられるのと同じように、小説もこのように今の日本語による新訳で作品が生まれ変わってゆく。スゴくないすか、日本人は6種類もの「八月の光」を読めるんすよ。アメリカ人は一種類しか読めないのに!
●描かれるのはアメリカ南部に生きる疎外された人々、過去に呪われた人々。とても重厚で骨太の群像劇なのだが、意外にも読みやすく、エンタテインメント性に富んでいる。映画になってもおかしくないくらい、だけど今のアメリカではデリケートすぎて到底描けそうもないほど深く人種問題の暗部に踏みこんでいる。主要な登場人物は3人。見た目は白人ながら黒人の血が混じっており「本当は自分は黒人である」という苦悩を抱える孤児院育ちの男ジョー・クリスマス(イエス・キリストと同じイニシャルを持つ)、未婚のまま身ごもり、自分を捨てた恋人をどこまでも追いかける異常に楽天的な若い女性リーナ(オペラにたとえると「カルメン」のミカエラに似て、かわいいようでいて心底邪悪な存在)、狂信的な元牧師であり今は世捨て人として生きる奇人ハイタワー。その他の登場人物も含めて、ほとんどがある種の崖っぷちで生きている。人種問題や奴隷制、南北戦争、キリスト教などといった根幹のテーマを共有していない現代日本のわたしたちが読んでも、十分に共感できる。いちばんぐっとくる人物はハイタワー。あの歪んだ宗教的情熱とその裏にある現実に向き合う勇気の欠如、そして身なりに無頓着な不潔さなどには見覚えがある。
●細かいことなんだけど、「濡れたリノリウムと洗剤の匂いがした」という一文があって、反射的にスティーヴン・キングを思い起こす。キングの小説にはやたらとリノリウムが出てくる。キングの「グリーン・マイル」は、刑務所で死刑囚が電気椅子に向かって歩く通路の床が緑のリノリウムであることにちなんでいるが、この「グリーン・マイル」で冤罪により死刑が下される黒人男性の名がジョン・コーフィ。「八月の光」のジョー・クリスマスと同様、イエス・キリストと同じイニシャルを持っている。
●印象に残ったシーンを引用。日が落ちて夜になるだけの描写なのだが、この色彩感、そして視覚と聴覚に訴えかけてくる空気感と来たら。
そこで簡易ベッドに横になって、煙草を吸いながら、陽が沈むのを待った。開いたドアから見ていると、陽が傾き、大きくなり、赤銅色になった。それから赤銅色が薄れて藤色になり、その藤色が暗みを増してとっぷり暮れた。蛙の声が聞こえてきて、蛍の光が開いた戸口の枠の中をすいすい横切りはじめ、夕闇が濃くなるにつれてその光が明るさを増した。
映画「風の谷のナウシカ」(宮崎駿監督)
 ●いま、映画館はどこも一席空けで、最大でも客席数の半分しか埋められない。現状のままでは持続困難であるという点で、映画業界も音楽業界と似たような危機を迎えている。そして、新作映画が足りない。で、気が付いたらあちこちの映画館で過去の名画を上映している。シネコンが早稲田松竹のようだ。で、ジブリ映画の名作がいくつか上映されているのを見つけて、映画「風の谷のナウシカ」(宮崎駿監督)を観た。実は初見(ジブリはほぼ未見)。でも、「ナウシカ」を映画館で観たことのある人は決して多くないのでは。入場口で体温チェック、手指の消毒があるのはコンサートと同じ。ちなみにお客さんはよく入っていて、ウイルス禍以前に自分が観ていたたいていの新作映画よりよっぽど人がいると思った。
●いま、映画館はどこも一席空けで、最大でも客席数の半分しか埋められない。現状のままでは持続困難であるという点で、映画業界も音楽業界と似たような危機を迎えている。そして、新作映画が足りない。で、気が付いたらあちこちの映画館で過去の名画を上映している。シネコンが早稲田松竹のようだ。で、ジブリ映画の名作がいくつか上映されているのを見つけて、映画「風の谷のナウシカ」(宮崎駿監督)を観た。実は初見(ジブリはほぼ未見)。でも、「ナウシカ」を映画館で観たことのある人は決して多くないのでは。入場口で体温チェック、手指の消毒があるのはコンサートと同じ。ちなみにお客さんはよく入っていて、ウイルス禍以前に自分が観ていたたいていの新作映画よりよっぽど人がいると思った。

●1984年の映画だけに、映像や音声のクォリティは相応に古びてはいるものの、内容的にはまったく古びていないどころか、いま映画館で上映されることに納得。だって、この映画、いきなりマスクをした少女で始まるんすよ! 客席も全員マスクをしてるけど、スクリーンのなかでもマスクをしている。なぜかといえば世界は菌類の森で覆われていて、腐海からの瘴気を吸うと肺がやられるから。文明は崩壊し、大地は腐海と巨大昆虫たちで埋め尽くされている。その片隅で人類は素朴な農耕生活を送っているのだが、なぜか航空機などの高度なテクノロジーは保持しているという設定の黙示録的ファンタジー。ナウシカたちの動きを見ていて思い起こすのは「アルプスの少女ハイジ」と「未来少年コナン」。
●語り尽くされている物語なので、今さら付け加えることはなさそうだけど、この話って最後は強引にハッピーエンドに持っていくじゃないっすか。選ばれし者の自己犠牲ってヤだなと思うんだけど(自己犠牲で許せるのはブリュンヒルデだけ)、生き返ってくれて安堵する。でも世界が抱える問題はなにも解決していない。腐海はそのままだし瘴気も出てるし、人間は巨大昆虫や胞子を恐れながら生きていくしかない。巨神兵に腐海を焼き払わせて元の生活に戻ろうっていうのはダメで、人類は腐海と共生しなければならない。つまり、この話はマスクで始まって、「新しい生活様式」を受け入れるという結末で終わっている。
JFLの今シーズン、東京武蔵野シティフットボールクラブの行方
●J1、J2、J3の下にあるのがJFL。このウイルス禍にあって、日本サッカーの4部リーグがどうなっているのか、関心のある方はほとんどいないと思うが、現状を記しておこう。JFLは第1節から第15節までを中止ということにして、第16節から開幕することになった。東京武蔵野シティの開幕戦は7月19日のアウェイ高知ユナイテッドSC戦で、1対1の引き分け。無観客試合。で、次の試合が8月23日のラインメール青森戦。つまりまだ1試合しかしていないのだ。ホーム初戦はもっと先の話で、ようやく9月6日にソニー仙台戦が武蔵野陸上競技場で開催される。長らくサッカー観戦から遠ざかっているが、そろそろスタジアムに行きたいものである。
●で、その東京武蔵野シティに大きな方針変更があった。これまでJリーグ入りを目指すJリーグ百年構想クラブに認定されていたが、Jリーグ参入を断念し、地域に根ざしたアマチュアクラブとして活動するという。これに伴い運営法人も変更され、一般社団法人横河武蔵野スポーツクラブへの移管が段階的に行われることになった(お知らせ)。もともとこのチームは横河電機のサッカー部として出発して、そこから市民クラブへの道を歩んでいたチーム。巡り巡って落ち着くところに落ち着いたような感もあるが、一方で「東京第三勢力」、つまりFC東京でも東京ヴェルディでもないチームが今後も東京には求められてると思う。「東京都」はひとつふたつのクラブでカバーするにはあまりに大きすぎる……。あ、ごめん、FC町田ゼルビアも東京都だっけ。それとも神奈川県になったんだっけ?(なってません)。まあ、いずれにせよ町田は東京都でも神奈川県でもなく「町田」のクラブとして確固たるアイデンティティを築いている。
●ちなみにその他の東京のクラブでは、南葛SC(葛飾区)、東京23フットボールクラブ(主に江戸川区)、東京ユナイテッドFC(主に文京区)がJリーグ入りを目指している。しかし23区だと適当なスタジアムがないのが問題なんすよね。最新の立派な巨大スタジアムがど真ん中にあるんだけど、だれも使えないという……。トホホ。
灼熱の引きこもり
●今週は夏休み週。当ブログも不定期更新で。しかしウィルス禍にあって、夏休みをどう過ごすのかはなかなかの難問。行先は疎な場所に限られる。屋外なら感染を気にせずに済みそうだが、本日の東京の最高気温は37度。そして山も海も遠い。しかしごく近場となると、この半年くらいの間に行けるところは行き尽くした感もある。自分史上かつてないほど散歩してる。
●最後に遠出をしたのは、2月29日から一泊二日で出張取材に行った沖縄。その時点で「感染が広がりつつあるけど行けるのかな?」と気にしたものの、沖縄ではほとんど感染者が出ていなかったので、行ってしまえばすっかりウィルスのことを忘れて過ごせた。普通にお店で飲み食いできたし、取材先の琉球交響楽団もなんの問題もなく通常配置でリハーサルをしていた(本番は中止になったが)。温暖な沖縄で感染者がほとんどいないということは、インフルエンザと同じように、やがて春が来れば本州でもウィルス騒動は収まるのだろう……などと会話したのを覚えているのだが、現状はこの通り。
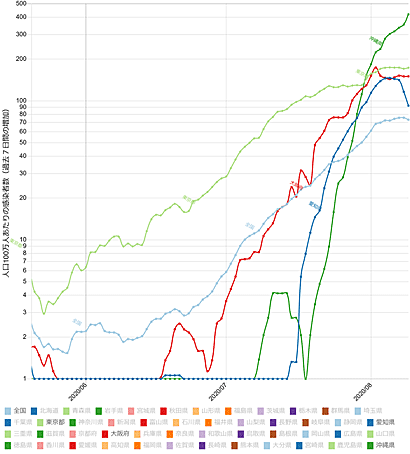
●今、人口あたりの感染者数を見ると(対数グラフ、過去7日間の増加、出典 sapmed.ac.jp)、沖縄(緑)は東京(黄緑)をはるかに上回っている。ちなみに大阪(赤)もすでに東京と大して変わらない。愛知が青、全国が水色。東京は5月27日が底で、そこから7月中旬くらいまではおおむね直線的に(つまり指数関数的に)増えているが、7月下旬からの傾きはずいぶん緩やかになってきている。
「ウィトゲンシュタインの愛人」(デイヴィッド・マークソン著/国書刊行会)
 ●ピンと来るものがあったので読んだ、「ウィトゲンシュタインの愛人」(デイヴィッド・マークソン著/木原善彦訳/国書刊行会)。柴田元幸、若島正両氏の推薦で「アメリカ実験小説の最高到達点」と銘打たれた一冊。登場人物はたったひとりだけ。というか、世界の最後のひとりとして生き残ったのが主人公。しかし世界の終末を描いたものではなく、ひたすら主人公の独白が続くだけの小説だ。彼女は世界中を旅しながら、あちこちで美術館等を訪ね歩いているのだが、すべては主観として語られているのみ。そして、その語り口は端的に言って狂っている。もちろん、世界でただひとりという孤独な状況に陥ればだれもが狂う。漂流するような焦点の定まらない思考が延々と書き留められており、そこで大きな比重を占めるのが美術を巡るトリビアというか、オタトークみたいなもの。美術、さらには文学、そして音楽にもしばしば話題が流れ、特にたまたまそこにあったブラームスの伝記本に異様な執着ぶりを示す。記憶が混濁し、錯誤を含んでいる上に、なんども繰り返しているような話題が結局のところどうでもいいような話だったりする。中心は美術なのだが、ブラームスについて述べた部分をいくつか引用してみる。それぞれぜんぜん違った場所で突然出てきたりする。
●ピンと来るものがあったので読んだ、「ウィトゲンシュタインの愛人」(デイヴィッド・マークソン著/木原善彦訳/国書刊行会)。柴田元幸、若島正両氏の推薦で「アメリカ実験小説の最高到達点」と銘打たれた一冊。登場人物はたったひとりだけ。というか、世界の最後のひとりとして生き残ったのが主人公。しかし世界の終末を描いたものではなく、ひたすら主人公の独白が続くだけの小説だ。彼女は世界中を旅しながら、あちこちで美術館等を訪ね歩いているのだが、すべては主観として語られているのみ。そして、その語り口は端的に言って狂っている。もちろん、世界でただひとりという孤独な状況に陥ればだれもが狂う。漂流するような焦点の定まらない思考が延々と書き留められており、そこで大きな比重を占めるのが美術を巡るトリビアというか、オタトークみたいなもの。美術、さらには文学、そして音楽にもしばしば話題が流れ、特にたまたまそこにあったブラームスの伝記本に異様な執着ぶりを示す。記憶が混濁し、錯誤を含んでいる上に、なんども繰り返しているような話題が結局のところどうでもいいような話だったりする。中心は美術なのだが、ブラームスについて述べた部分をいくつか引用してみる。それぞれぜんぜん違った場所で突然出てきたりする。
ここへ戻る途中、ふと、ブラームスが聞こえた気がした。『アルト・ラプソディ』と言いたいところだが、『アルト・ラプソディ』をちゃんと記憶している自信はない。
『アルト・ラプソディ』を歌っていたのはキャスリーン・フェリアだ。
昨日、キルステン・フラグスタートが『アルト・ラプソディ』を歌うのを耳にしたとき、厳密には私は何を聞いていたのか。
イグニションキーを回したら、ブラームスの『四つの厳粛な歌』が聞こえてきた。ひょっとすると私の頭にあるのは、リヒャルト・シュトラウスの『四つの最後の歌』かもしれない。
残念ながらもう一軒の家には、これに関してもっと詳しく調べられるブラームスの伝記がない。ベートーベンの伝記はおそらく何の役にも立たなかっただろう。ちなみに、もう一軒の家にあったベートーベンの伝記のタイトルは『ベートーベン』だ。私が以前見たブラームスの伝記のタイトルは確か、『ブラームスの一生』だった。これは簡単に確かめられる。
ところで、以前から、ブラームスはあまり好きな作曲家ではない。確かにブラームスの名は、ここに何度も登場しているけれども。でも実は、ブラームスが登場した回数はそれほど多くない。言及した回数が多いのはブラームスの伝記だ。タイトルはおそらく、『ブラームスの一生』か、『ブラームスの生涯』か、ひょっとすると『ブラームス』。
ただしもっと具体的には、私が解きたい謎は、例えば、ベルリオーズ作曲の『トロイアの人々』のことを考えているのに、あるいは『アルト・ラプソディ』のことを考えているのにどうしてヴィヴァルディの『四季』が聞こえてくるのかという問題だ。
それを聞くたびにいつも、聞こえているのは『アルト・ラプソディ』だと考えていたけれども。だから明らかに、私がこれまで『アルト・ラプソディ』と言ったときはいつも、『ブラジル風バッハ』と言うべきだったということだ。
●えっ、「アルト・ラプソディ」の話をなんどもしてたのに、それがヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ」のかんちがいだったっていうの? でもキャスリーン・フェリアが歌ってたのは「アルト・ラプソディ」でしょうが。ブラームスの伝記の書名も混乱してるし……。と、いった調子で、全体にわたってなにが確かでなにが記憶違いで、どこから正気でどこから狂っているのか、まったく客観性のない自意識の移ろいだけで綴られていくのだが、そもそも世界にただひとりしかいないのなら、客観という概念に意味があるだろうか。世界は事実の総体であって、事物の総体ではない。
●意外にもこの小説はとても読みやすい。そして、まちがいなくユーモアがあって、なんどもワタシは大笑いして読んだ。作者はこの原稿を出版社に持ち込んだところ、合計54社もから刊行を断られたという。もし自分が出版社の編集者だったら? うーん、やっぱり断ったにちがいない。
映画「パヴァロッティ 太陽のテノール」(ロン・ハワード監督)
●ウィルス禍で公開延期となっていたパヴァロッティのドキュメンタリー映画「パヴァロッティ 太陽のテノール」が、9月4日(金)からTOHOシネマズ シャンテほかで全国公開されることになった。監督は「アポロ13」「ダ・ヴィンチ・コード」「ビューティフル・マインド」他で知られるロン・ハワード。音楽ドキュメンタリーでは珍しい大物監督による作品だが、中身は正攻法。パヴァロッティはなんといっても声の魅力が圧倒的で、それだけでも最高のテノールだが、加えて人間的な魅力が並外れている。ドキュメンタリー映画の題材にはうってつけ。公開に先駆けてプレス試写を拝見。
●パヴァロッティには、マネージャーだったハーバート・ブレスリンによるめっぽうおもしろい暴露本「王様と私」があるが、あちらがダークサイド寄りだとすれば、この映画は主にパヴァロッティのライトサイドに光を当てている。パヴァロッティの最初の奥さんとその娘さん、愛人だったマデリン・レネ、ふたりめの奥さん、みんな登場して、生前のパヴァロッティについて率直に語る。またパヴァロッティ本人のインタビュー映像(テレビ番組などに出演した際のものらしい)もふんだんに使われている。
●娘さんがパヴァロッティについて「自身と共通点を感じ取っていた役柄はネモリーノ」という話には納得。「愛の妙薬」に登場する純朴な農夫。本人は根っからの善人で、オペラ界でスター歌手になるところまではハッピーだったはず。しかしそこに留まらなかったのがパヴァロッティ。オペラの世界を超えて、ビジネスの世界でビッグスターになってしまったところから、だんだんハッピーに生きることの難しさがにじみ出てくる。ネモリーノも遺産を相続した途端にモテモテになったわけだが……。娘さんの「父は録音で自分の声を聴くのを怖がっていた」という話も興味深い。世界中の人たちが夢中で聴いていたのに!
●マネージャーのハーバート・ブレスリンも出てきて証言する。「レコード会社がパヴァロッティに言った。あなたは善人だから、最高に嫌な人間を雇う必要がある」。それがブレスリンとパヴァロッティの出会い。
●あとパヴァロッティの言葉で含蓄があると思ったのは、「オペラでは偽物が舞台の上で少しずつ本物になる」。実際にはパヴァロッティはどんな衣装を着てなんの役を歌っていても「パヴァロッティ本人」にしか見えなかったことと合わせて考えると味わい深い。
ベガルタ仙台vsマリノス J1リーグ第8節
●週末のJリーグ、マリノス戦を軽く振り返っておきたい。せっかく勝ったんだし。昨季の覇者マリノスだが、先発メンバーを見ると主力がごっそり抜けていてまるで別のチームのよう。チアゴ・マルチンスも仲川もエリキもベンチにすらいない。遠藤はベルリンに旅立った(ウニオン・ベルリンへのローン移籍)。マルコス・ジュニオールはベンチ。なんだか毎試合メンバーが変わるが、いつになっても本来のAチームは姿を見せないみたいな状況になっている。
●ただし、キーパーに朴一圭(パク・イルギュ)が帰ってきた。目を疑うようなプレイを連発。ここまで梶川裕嗣が健闘していたので、自分のなかでは梶川を正キーパーにしていいんじゃないかとすら思っていたのだが、久しぶりに見た朴はぶっ飛んでいた。もうクレイジーなくらいに前にポジションをとる。ことごとく足でボールを処理する。一度など、高くあがったボールに対して足でトラップしたところ、これが後方に流れてあわやゴールに入るかという危険な場面があった。手を使えばなんでもないボールなのに! かと思えば、手によるナイスセーブも披露する。なんという異能の人なのか。昨季は途中まで飯倉(現在は神戸に移籍)が「走るゴールキーパー」という超先鋭的なプレイスタイルを見せていたので、朴のプレイが異常には見えなかったが、今季、梶川というより常識的なゴールキーパーを見た後で朴を見ると、完全にどうかしている。こんな激辛カレーみたいなプレイスタイルを求めるんだったら、たしかにポステコグルー監督は梶川では満足できないだろう。ちなみにこの日の朴の走行距離は7.3km。仙台のキーパー、ヤクブ・スウォビィクは4.8kmだ。ウチのキーパーはメッシ並みに走ってるぜ!
●さて、マリノスはほとんどの時間帯でボールを支配し、チャンスの山を築いていたが、ゴールが遠いという何度も目にした展開。逆に終盤には仙台にいくつも好機があった。一度は扇原のハンドでPKかと思うような場面もあったが、主審はファイルを取らず。これはフットボールの健全さという点では正しい判断だと思うのだが(避けがたいスピードで腕に当たった)、VARを導入していたら主審はPKをとっていたんじゃないだろうか。だって現に当たっているわけだし。ルールの解釈では、現象と文脈のどちらを優先するのかという問題が常にある。もう試合終了と思われた94分、途中出場のマルコス・ジュニオールがタナボタでゴールを決めて、劇的な勝利。仙台 0-1 マリノス。
●ポステコグルー監督は試合後のインタビューでも決して本音を見せない。ポーカーフェイスで淡々と原則論を語って、メディアに余計な情報を与えない。この人は遠からずJリーグからヨーロッパへとステップアップを果たすのだろうか。
●マリノスのメンバーのみ記しておこう。GK:朴一圭-DF:小池龍太、松原健、畠中槙之輔、ティーラトン-MF:扇原貴宏、喜田拓也(→伊藤槙人)、天野純-FW:水沼宏太(→渡辺皓太)、エジガル・ジュニオ(→オナイウ阿道)、仙頭啓矢(→大津祐樹)。本職サイドバックの松原がセンターバックで出場していた。なお、マリノスは松本山雅からポルトガルのマリティモにローン移籍していた前田大然を、やはりローンで獲得した。期待大。
新国立劇場「夏の夜の夢」、東京オペラシティ「B→C」、サラダ音楽祭
●まだまだ先の見通せない音楽界ではあるが、秋以降の公演情報が続々と入ってきた。まずは待望の新国立劇場。10月のブリテン「夏の夜の夢」公演が開催されると発表された。ただし、上演形態はデイヴィッド・マクヴィカー演出による舞台上演から「ニューノーマル時代の新演出版」に変更される。オリジナル演出の舞台装置や衣裳を使用しつつ、新型コロナウイルス感染症対策としてソーシャル・ディスタンスの確保や飛沫感染予防が講じられた形になるという。それ以上詳しいことはわからないのだが、どうなんでしょう、舞台上で歌手が密にならないとか、対面で向き合って歌わないとか、そういうイメージ? ということは、このオペラ、最後はめでたく結婚式で終わるわけだけど、「ニューノーマル時代の結婚式」を目にすることになるんだろうか。演出は演出補として公演に参加予定であったレア・ハウスマンが担当。指揮はマーティン・ブラビンスに代わって飯森範親が登場。なお、1階1列~3列の座席は販売せず。現時点では前後左右をあけた座席配置。
●もし、今のウィルス禍が長く続くのなら、オペラの演出は新様式を一から作り出すことになるのかも。
●もうひとつ、東京オペラシティは中止になっていた3月から6月の「B→C(ビートゥーシー|バッハからコンテンポラリーへ)」公演を、11月以降に新たな日程で開催すると発表。まずは11月10日の景山梨乃(ハープ)公演で再開。11月に感染状況がどうなっているかはだれにもわからないが、予定通りに再開されることを願うばかり。
●もう少し近いところの話題としては、東京都と東京都交響楽団による「サラダ音楽祭」が9⽉5⽇〜6⽇に開催される。会場は東京芸術劇場が中心。こちらは当初4日間で予定していたものを2日間に短縮しての開催。赤ちゃんから入場可のファミリー向けコンサートも含まれているので、客層という点でも気になるところ。
N響 夏のフレッシュコンサート ~音楽でふれあおう~

●2日はNHKホールへ。約半年ぶりにこのホールにやってきた。いつの間にか原宿駅が改装されていて驚く。沖澤のどか指揮NHK交響楽団、石丸幹二(語りと司会)、牛田智大&中野翔太(ピアノ)による「N響 夏のフレッシュコンサート ~音楽でふれあおう~」。例年この時期にはファミリー向けの「N響 ほっとコンサート」が開かれているのだが、感染拡大中とあって家族連れはほとんど見当たらず、しかし定期公演に比べれば若い客層が中心。ヘンデル(ハーティ編)の「王宮の花火の音楽」序曲、オネゲルの「夏の牧歌」、ビゼーの「アルルの女」組曲よりメヌエットとファランドール、そしてサン=サーンスの組曲「動物の謝肉祭」というプログラム。
●休憩なしの約1時間、小編成のプログラムは今のオーケストラの標準仕様。奏者間の距離を広くとっての散開配置。弦楽器、特に第一ヴァイオリンの聞こえ方がずいぶん違って聞こえる。セクション内の濃淡が浮き出るというか。客席は半分よりもはるかに疎、入り口にサーモグラフィあり、入場時に手指アルコール消毒必須、マスク着用、チケットの半券は自分でもぎる方式。ビュッフェの営業はないが、自動販売機があるのはありがたい。感染対策は十分すぎるほど十分。というか、今はどの公演でもそうなんだけど、街中のほうがずっと密で、お店や駅に比べたらコンサートホールは安全地帯と言っていいほど。客席でもみんな静かだし。
●「王宮の花火の音楽」、ハーティ編を聴くのはいったいいつ以来なんだろう。録音でも長く耳にしていなかったが、今聴くと懐かしの「20世紀デラックス」感。これはこれで20世紀前半の歴史的演奏スタイルなのか。白眉はオネゲル「夏の牧歌」。ホルンの深々としたまろやかな音色を堪能。沖澤さんの指揮ぶりはとても明快で、音楽の流れが自然。石丸さんとのなにげないトークから、沖澤さんが「フランスでサン=サーンス先生から石丸さん宛の手紙を預かってきたので読んでほしい」と言い出して、ナレーション入りの「動物の謝肉祭」へとなだれ込む。「動物の謝肉祭」に込められたギャグ(?)にはピンと来るような来ないようなものもあってまちまちだが、「ピアニスト」は若くて華のあるふたりだからこその楽しさ。「化石」は「死の舞踏」の恐竜版だと思って聴く。恐竜の骨がカチャカチャ鳴って踊っているイメージ。
●最初の奏者入場から拍手がわき、最後に全員が退出するまで拍手が続く。これも今の演奏会の光景。