●さて、イェンス=ダニエル・ヘルツォーク演出による新国立劇場のワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」だが、あと一公演を残すところとなったので、そろそろ結末部分について書いておこう。これから楽日をご覧になる方はここまで。
●といっても、大した話ではないのだ。いや、でもこのオペラの根幹にかかわることだから、大事な話なのかな……。まず「ニュルンベルクのマイスタージンガー」というオペラは、伝統的な演出のままでも現代人が鑑賞可能な物語として成立しうるのか、という問題がある。音楽は神の領域だが、ストーリーには難がある。なにせ歌合戦の賞品が花嫁(と財産)なんである。女に生まれたばかりに、エーファは賞品として男たちの前に差し出される。ポーグナーのような成功者のもとに生まれてすら、このような扱いを受けるとは。なんという屈辱。そこで、「これは歴史劇なのだから、しょうがない」とする受け止め方がある。大河ドラマを観て女性の人権についてブツクサ言ってどうする、みたいな感じだ。だが、ヘルツォーク演出は舞台を現代に置き換えているので、今回はそのような見方はできない。だから、どうするんだろうな……と思って観ていた(ゲネプロだったけど。でも本番もきっと同じだったはず)。一応、伏線はいくつか張ってあって、たとえば飾ってあったマイスターたちの肖像がみんな鼻の穴バッチリの下からのアングルで、やたらと傲慢そうなのだ。これはなにかの狙いがあるんだろうとは感じた。
●それでも意外と普通のままに話は進んで、事が起きるのは本当に最後の最後。エーファは肖像を破り捨てて、ヴァルターの手を取って親方たちのもとを去る。ただそれだけなんだけど、話の筋としてはこれ以外にないという結末ではある。だって、この街(演出上は「劇場」)は本当に終わっている。女は所有物として扱われるし、親方たちは全員男ばかり、しかもそのなかでいちばん理性的に見えるオッサンが最後に自国の文化はいいけど外国文化はろくでもないとか説教していて、どう考えてもここには未来がない。エーファでなくても、女ならこの街からどうやって脱出するかを考えるだろう。あるいはこうも思った。この結末がポーグナーの真の狙いだったのかな、と。娘をこの蟻地獄みたいな場所から救い出してやるために、よそ者であるヴァルターに賭けたのかもしれない。演出としての新規性はともかく、エーファにとって希望の持てる結末はこれしかないと思う。
●だから筋だけ追えば納得のエンディングなのだが、そこで厄介なのは音楽との乖離。どう考えたって、ワーグナーの音楽はニュルンベルクを讃えているし、ザックスは立派な人物だし、最後はみんながハッピーエンドを迎えたとしか聞こえない。これと同じようなことはままあって、近年の新国立劇場の演目で言えば、カタリーナ・ワーグナー演出の「フィデリオ」バッドエンド版でも、アレックス・オリエ演出の「トゥーランドット」バッドエンド版でも、最後で話が音楽と噛み合わなくなる。「フィデリオ」でベートーヴェンの音楽は「正義が勝つ」って言ってるのに、演出では「悪が勝つ」。それっておかしくね?ってことなんだけど。
●でももしかしたら、それは音楽の聴き方を固定しているから齟齬が生じているだけなのかもしれない。「ハッピーエンドの音楽」だと思い込んで聴いているけど、これを「ハッピーエンドのパロディの音楽」として聴くべきなのでは?という問いはありうる。でも、これだけ偉大な音楽をそこまでシニカルに聴けるかな。
2021年11月アーカイブ
新国立劇場 ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」イェンス=ダニエル・ヘルツォーク演出 ネタバレあり
マリオ・ヴェンツァーゴ指揮読響のブルックナー
●26日はサントリーホールでマリオ・ヴェンツァーゴ指揮読響によるモーツァルトのピアノ協奏曲第20番(ゲルハルト・オピッツ)とブルックナーの交響曲第3番(第3稿/ノヴァーク版)。これは近年まれに見る快演。ヴェンツァーゴのブルックナー、CPOレーベルでのタピオラ・シンフォニエッタやノーザン・シンフォニアといった室内管弦楽団を起用した録音が目をひいてはいたものの、サイズに制限のない読響との共演となるとはたしてどんな化学反応が起きるのか、あるいは起きないのかと思いつつ足を運んだところ、期待をはるかに上回る充実度。キレと弾力性のあるリズム、澄明な響きに支えられた躍動するブルックナーで、モッサリ感ゼロ。金管楽器のバランスも特徴的で、ときには抑制させ弦楽器に重心を置き、ときには咆哮させる。決して淡白ではなく、随所にグッと来るような「決めポーズ」もあり。湿気がなくカラッとしたシリカゲル入りブルックナーで、なんてカッコいい曲なんだと改めて感心。ヴェンツァーゴは痩身白髪、外見はおじいさん巨匠指揮者風なのに音楽はフレッシュ、キャラも割と明るいっぽい。最後の一音が終わったら一秒と待たずにサッサと手を下ろし、客席に向かって両手を広げてどうだとばかりにポーズ。棒を止めて沈黙を求めないのはひとつの美学だと思う。最強の楽しさだったので、ぜひ次は第5番あたりを希望。
●カーテンコールで早々に席を立つ人も目立ったが、ヴェンツァーゴのソロ・カーテンコール~スタンディングオベーションまで拍手を続ける人も多数。
●後半の印象が強烈すぎたが、前半のモーツァルトも聴きごたえあり。出演者変更により予定外にオピッツを聴くことになったが、20世紀の伝統を格調高く今に伝えるモーツァルト。読響も独奏者に応えて重厚なテイスト。
アレクサンドル・カントロフのブラームス&リスト
●25日はトッパンホールの「エスポワール スペシャル 17」で、アレクサンドル・カントロフのピアノ・リサイタル。2019年のチャイコフスキー国際コンクールで、藤田真央が第2位を獲得した際の第1位がこのカントロフ。ファイナルでチャイコフスキーのピアノ協奏曲第2番を弾いて初めて優勝したことで話題になった。父はジャン=ジャック・カントロフ。フランス出身。
●で、待望の来日リサイタルでどんなプログラムを用意してくれるのかと思えば、ブラームスの4つのバラード、リストの「ダンテを読んで ソナタ風幻想曲」、ブラームスのピアノ・ソナタ第3番ヘ短調。若きスターらしからぬ渋さだが、すさまじく凝縮度の高い2時間だった。ピアノの音がすごい。パワー任せの爆裂サウンドとは違うのだが、鋭く強靭な轟音を持ち、色彩感も豊か。あふれ出るようなパッションの持ち主で、しばしば唸り声というかハミングも漏れ聞こえてくる。ブラームスからリストへと連なる前半は幻想味にあふれ、次第に音楽が白熱して大きなクライマックスを築き上げる。
●後半、ブラームスは異形の大ソナタ。交響曲的な要素とピアニスティックな要素をあわせもつ作品で、これまであまり生で聴く機会がなかったのだが、勢いと熱さのある奏者にふさわしい選曲と納得。シンメトリックな全5楽章で、型に収まらないアンバランスさが魅力。第2楽章はシューマンっぽい。「花の曲」を思い出す。第3楽章のスケルツォはメンデルスゾーンのピアノ三重奏曲第2番終楽章の引用というかリスペクトというか。中間部でコラール主題があらわれるのもメンデルスゾーンゆずりだが、後の交響曲第1番終楽章の歌謡主題を連想させなくもない。第5楽章にもシューマンの香りを感じる。
●アンコールは3曲。ストラヴィンスキー~アゴスティ編の「火の鳥」終曲、ラフマニノフの「楽興の時」第3番ロ短調、モンポウ「歌と踊り」第6番。「火の鳥」は鮮烈。ラフマニノフからタブレット持参。前日にも同一プログラムの公演があったが、両日ともチケットは完売。来年6月にも来日公演があるそうなので、ますます人気が出るかも。
紅葉の季節、波と凪

●この時期の楽しみといえば紅葉。ウイルス禍以来、公園の散策は最大の娯楽になっている……と思ったが、別に以前からそうだったのかも。今はネットで紅葉名所の色づき具合を確認して出かけることができるのが便利。ビバ、予定調和の紅葉体験。
●で、もう過ぎ去ったことのように錯覚してしまいそうになるが、これからどちらの道に進むのだろうか……。あ、新型コロナウイルスの話なのだが。昨日、東京都の新規陽性者数はわずか5名。一時期は5千人を突破していた。多くの専門家が1月に新たな波がやってくる可能性を指摘しているので、どうしても「今のうちに出かけておこう」という気持ちが働きがち。先日、仕事である地方都市に日帰りしてきたのだが、ウイルス禍以来久しく目にしたことがなかった観光客の大集団を見かけて、すさまじい熱気と迫力を感じた。わかる。今なら行ける! もっとも、全員がマスク姿なのは変わらず。
●一方、ヨーロッパではふたたび感染拡大が進み、オーストリアでロックダウンが実施されるなど、状況は厳しい。ワクチンが普及してもやはりロックダウンが避けられないとは。1月以降、日本もヨーロッパの後を追うことになるのだろうか? ふと、ヨーロッパで日本以上にワクチン接種率が高い国はどうなっているのか気になって、毎度おなじみのourworldindata.orgを見てみた。ワクチン接種完了率は、オーストリアが65%。ドイツが68%、フランスが69%。大差はない。アメリカは58%と低いまま。日本は77%と高いがさすがにもう勢いは鈍っている。スペインはなんと80%! これにはびっくり。スペインの状況はどうなっているんだろう。
●そこで各国の人口あたり新規感染者数の7日移動平均を見てみると、オーストリアは突出していて、100万人あたり1500人を突破。ドイツは急上昇中で600人超で、イギリスと同程度。一方、スペインは120人ほど。これだけ見るとワクチン接種完了率と強い相関関係がありそうにも思えるが、しかしスペインの接種率が高いといってもオーストリアとは15%の差で、それがそこまで違いを生み出すものかどうか。そうかもしれないし、そうでないかもしれない。実際には多数の要因が複合的に絡み合って結果に表れているのだろうから、単一の要因で物事を説明しようとする考え方は危ういか。
●ワクチン接種が進めば感染者数が増えても、重症化に至る人は少ないからあまり気にしなくてもいいのではないか、という淡い期待を抱いていたこともあったが、同じデータで犠牲者数を見るとそんな悠長なことを言ってられないことがわかる。ロックダウンももっともな話ではある。
トロールの森 2021

●「トロールの森」は杉並区の都立善福寺公園を中心に西荻窪周辺エリアで展開される野外アート展。昨日で会期は終了したのだが、善福寺公園の展示を見たので振り返っておこう。公園のあちこちに作品が点在しており、展示を目的に来たというよりは、公園に散歩しに来た人たちが「あれ、なんだろう?」と作品を眺める雰囲気。毎年のように足を運んでいるのだが、率直なところ、作品の過半は公園そのものが放つ強烈な輝きの前に霞んでしまっている。それも無理はない話で、草木や花の造形が持つ無限のバリエーションと精妙さ、四方から聞こえる小鳥のさえずり、池に棲息するサギやカワウの優雅さ、数種のカモたちやカイツブリらの興味深い生態といった神々のクリエーションを前にすると、アート、というかアーティフィシャルなもの全般がいかにも脆弱に見えてしまうのはしかたがない。それでも、いくつかこれはと思える作品がある。

●まず、土器文字「スーハー」(小野真由)。土器によるおびただしい数の「スーハー」が地面を覆っている。まるでワタシたちの吐いた息がそこに落下したかのよう。どこにもそうは書いていないけれど、連想させるのはマスク。今、屋外の公園であっても全員がマスクをして散歩している。そんな奇妙な状況が呼吸という行為に意識をフォーカスさせる。今回の「トロールの森」のテーマは「深く息をする」。

●Water Laboratory 「リズム」(栗田昇)。水の流れにより水車が動き、心地よいリズムで音を発する。水車の動きはスムーズでほとんどエレガントといってもよく、発せられる音も公園の風景に無理なくなじむ。軽い作品が多い中で、創意という点で際立っていた。自然に対抗できるのは、自然の模倣ではなく、エンジニアリング。

●「ちゅーリップ」(永林香穂)。このチューリップには口がある。散歩する人間たちがマスクをして、すっかり他人に口を見せる機会がなくなっているなかで、チューリップが唇を堂々とさらしている。「ちゅー」+「リップ」というネーミングもうまい。屋外だとこれくらいポップな表現のほうが、下手に樹木や草花と絡もうとするよりもよほど効果的だと思った。明るさ、開放感が吉。
Windows 11に更新、DeskMini310編

●しばらく躊躇していたのだが、そろそろ大丈夫なんじゃないかとメインのPCをWindows 11に更新した。現在使っているのはサイコムから購入した小型のBTOパソコンで、中身はASRockのDeskMini310。デスクの上にちょこんと載せるサイズ感が気に入っているのだが、購入時の状態ではWindows 11へのアップデート不可と判定されてしまう。というのも、Windows 11にはTPM2.0が必須にもかかわらず、これが標準状態で無効になっていたから。そこで、UEFI BIOSからTPM2.0を有効にしなければならない。正確にはTPM2.0相当のIntel Platform Trust Technologyを有効にする。手順は簡単でここが参考になる。Windows上から設定するのではなく、Windowsが起動する前にF2キー等をトントンして、UEFI BIOSに入る。
●で、Intel Platform Trust Technologyさえ有効にすればそれでいいのかという点が気になっていたのだが、試しにやってみると、何日かしてWindows 11への更新ができますと促されるようになった。ほっ。あとは普通にWindows Updateから更新するだけ。やや時間がかかったが、スムーズにWindows 11が起動した。
●さて、これでなにが変わったのか。正直なところ、スタートメニューの場所とデザインが変わったこと以外は、今のところ大した変化を感じていない。あちこち細かなところが洗練されているとは思うが、今回のアップデートの主眼はセキュアブート周りなんだろう。なお、Windows 11への更新に伴って、タスクバーにピン留めしておいたショートカットはそのまま残っているが、スタートメニューのタイルにピン留めしておいたショートカットは一掃されている。これらをもう一回、新しいデザインのスタートメニューに登録するのが面倒といえば面倒。
●そして、Windows 10でもそうだったのだが、メジャーアップデートの後は老眼対策として「Meiryo UIも大っきらい!!」を用いて、エクスプローラー等のフォントサイズを一括で大きくすることになる。単にフォントサイズを大きくするなら、Windowsの「設定」でもできるのだが、あれは求めるものが違うんである。文字を一律に大きくしてほしいのではなく、エクスプローラーのファイル一覧等、限られた文字だけが小さすぎて読みづらいのをどうにかしたいんである……という話は前にもしたか。Microsoftに45歳以上の人間はいないのだろうか。
ファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団のブルックナー「ロマンティック」
●18日は東京芸術劇場でファビオ・ルイージ指揮NHK交響楽団。2022年9月よりN響首席指揮者に就任するルイージが予定通り来日。隔離期間の関係なのか、先に開かれたAプロはルイージから沼尻竜典に指揮者が変更されたが、この日のCプロと続くBプロは予定通りにルイージが登場することに。
●で、池袋Cプロは変則的で、19時30分開演で休憩なし。プログラムはブルックナーの交響曲第4番「ロマンティック」のみ。開演が遅くても、終演が遅くならないのは救い。これだけだとあっさりしているが、開演に先立って18時45分からN響メンバーによる「開演前の室内楽」がある(15分程度、トーク入り)。この室内楽の演奏中は出入り自由。室内楽から聴く人にとってはふだんの演奏会より開始が早いというのがミソ(って話は先月も書いたか)。
●今回はブルックナーの弦楽五重奏曲から第3楽章を演奏してくれた(宇根京子、大宮臨太郎、佐々木亮、坂口弦太郎、宮坂拡志)。室内楽コーナーであまり聴けない作品を聴けるのは大きな楽しみで、これがあるとないとでは大違い。本編のプログラムと違って、出入り自由のリラックスした環境で聴けるのも吉。ブルックナーの弦楽五重奏曲、第3楽章はアダージョ。そのまま交響曲の緩徐楽章になりそうな深みのある崇高な音楽。そもそもこの曲自体が交響曲的なので、これを交響曲にパワーアップさせることができるんじゃないか……というのはみんな思うだろうし、実際に編曲した人がいたような気がする。
●本編のプログラムは、管楽器が先に座っているところにルイージがひとりで登場して、その後、弦楽器も入場するというウイルス禍の変則仕様。ルイージは棒を持たずに指揮。明るく温かみのあるサウンドによる、しなやかで流麗なブルックナー。いかめしさや宗教的な恍惚感は控えめで、まろやかな響きと歌心にあふれた自然賛歌の音楽。先月のブロムシュテットでも思ったんだけど、N響と芸劇の音響の相性がよくなっているというか、うまく最適化されていると感じる。芸劇は反響板を下ろした状態で、これだとかなりコンパクトな空間になる。本来の本拠地NHKホールとはまるで条件が違う。NHKホールの改修工事が終わったら、もう芸劇は使われないのだろうか。すっかり芸劇の心地よさに慣れてしまった。駅からも直結してるし。
●曲が終わると、すぐに楽員が先に退場して、ルイージがひとり残って喝采を受ける強制ソロカーテンコールに。隔離の都合でしょうがないんだろうけど、個々のプレーヤーを讃える機会がないのは寂しい。
イザベル・ファウスト J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ全曲演奏会 第1夜
●海外からアーティストが予定通りに来日するだけでほっとするのが今。もうしばらくするとこんな時期があったことも昔話になるのだろうか。17日は東京オペラシティでイザベル・ファウストによる「バッハ 無伴奏ヴァイオリン・ソナタとパルティータ全曲演奏会第1夜」。全6曲を二日にわけて演奏、休憩なしというフォーマット。第1夜はソナタ第1番、パルティータ第1番、ソナタ第3番の3曲。正味1時間強のプログラム(プラスしてアンコール一曲。ソナタ第2番の第3楽章アンダンテ)。ファウストのバッハ無伴奏は以前にも聴いたことがあるし、2日間とも通うのは日程的に厳しかったので第1夜のみ参戦したのだが、聴きはじめて激しく後悔。これは両日とも聴くべきだった!
●以前もそうだったが、両面に譜面を貼り付けた大判の厚紙を譜面台に置いて演奏。すっかり手の内に入った作品であっても毎回が新しい体験といわんばかりの鮮度の高さ。ソナタ第3番のフーガは白熱。もともとこの6曲、通しで演奏してストーリーのあるものではないんだから、半分の3曲でも十分に楽しめるはずだと思ったし、事実楽しんだけど、初日だけだとサッカーの試合を前半だけ観て帰るみたいな落ち着かなさを感じる。第2夜のおしまいにパルティータ第2番を聴き終わったときに訪れるはずの、旅の終わりみたいなしみじみとした感慨を想像する。
●前に聴いたときはどうしたんだっけ……と思って調べてみたら、彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールで同日2公演方式だったのだ。午後の第1部で3曲聴いて、夜の第2部で残り3曲を聴くという方式(3曲の分け方は今回と微妙に違ってた)。そういう手もあったか。
オマーン対ニッポン@ワールドカップ2022カタール大会 アジア最終予選
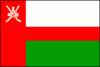 ●16日深夜、ワールドカップ2022アジア最終予選でオマーン対ニッポン。アウェイなのでテレビ中継なし、今回もDAZNの配信を翌朝に時差観戦。今回の最終予選で苦しんでいるのは、もとはといえばホームのオマーン戦に敗れたから。サウジアラビアとオーストラリアがライバルと目されるグループで、オマーン相手にホームで負ける大誤算があった。となればアウェイといえども勝利は必須。で、森保監督はこの試合でもチームの継続性を重んじて、出場停止の守田以外はすべて同じ選手を先発させた。しかも守田の代役は柴崎。一歩逆戻りした感がある。布陣は4-1-2-3、あるいは4-3-3。GK:権田-DF:山根、吉田、冨安、長友(→中山雄太)-MF:遠藤、柴崎(→三笘薫)、田中碧-伊東(→浅野)、南野(→古橋)-FW:大迫(→原口)。
●16日深夜、ワールドカップ2022アジア最終予選でオマーン対ニッポン。アウェイなのでテレビ中継なし、今回もDAZNの配信を翌朝に時差観戦。今回の最終予選で苦しんでいるのは、もとはといえばホームのオマーン戦に敗れたから。サウジアラビアとオーストラリアがライバルと目されるグループで、オマーン相手にホームで負ける大誤算があった。となればアウェイといえども勝利は必須。で、森保監督はこの試合でもチームの継続性を重んじて、出場停止の守田以外はすべて同じ選手を先発させた。しかも守田の代役は柴崎。一歩逆戻りした感がある。布陣は4-1-2-3、あるいは4-3-3。GK:権田-DF:山根、吉田、冨安、長友(→中山雄太)-MF:遠藤、柴崎(→三笘薫)、田中碧-伊東(→浅野)、南野(→古橋)-FW:大迫(→原口)。
●相手のオマーンは4-4-2(あるいは4-3-1-2)。まずは守備ブロックをしっかりと敷いて、少ないチャンスをものにしようという構え。前回の対戦時のような前線からの鋭いプレスはない。そして前のベトナム対ニッポンの試合を観れば当然だが、伊東の前にスペースを与えない。一方のニッポンも積極的な仕掛けがなく、自陣でのボールキープが長い展開。プレスも淡白。ほとんどチャンスらしいチャンスが両者ともないまま膠着状態が続いて、前半終了。またも老いたライオンのような戦いぶりで、継続性重視の選手起用の弊害はこういうところかなと思ってしまう。ニッポンは追う立場なのだから、前からガツガツと行ってほしい。せっかく韓国人主審が試合を止めない笛を吹いてくれているのに。主審は中東のムードに左右されず、国際標準の笛を吹いてくれた。
●森保監督は後半頭から柴崎を下げて、ついに三笘薫を投入。これでチームが一変した。待望の(遅すぎた?)代表デビュー。最初のプレイからいきなりドリブルで仕掛けて左サイドの敵陣深くに侵入。その後もボールを持てば仕掛けるといった様子で左サイドを制圧。初めて対戦した選手に、あの独特の間合いのドリブルは驚きだったはず。三笘に触発されてかハーフタイムに檄が飛んだのか、前線が一気に活性化して、ようやく試合が始まったかのよう。さらに、最近の代表ではコンディションがもうひとつの南野を下げて、前線に古橋を投入、そしてリリーフ投手のように長友を下げて中山を投入するいつものパターン(これならさっさと中山を先発にすればよいと思うのだが、念入りに段階を踏むのが森保流)。古橋は精力的に前線からプレスをかけて、これが効果的。次々とチャンスが作られ、内容はぐっと良くなった。あとは時間との戦いで、ゴールには至らないまま時計の針が進む。ようやく後半36分、三苫が左サイドに侵入して、巧みなクロスを入れると詰めていた伊東が蹴り込んでゴール。残り時間を慎重に守り切って、オマーン 0-1 ニッポン。三苫のおかげ。
●これでベトナム戦、オマーン戦のアウェイ2連戦に連勝。この結果は立派。他会場に目をやると、中立地開催となった中国対オーストラリア戦が引分けた。オーストラリアは先制するも、PKを与えて失点して1対1。ニッポン以外も最終予選では苦労する。これでニッポンはオーストラリアを勝点1上回って勝点12、2位に上昇。追う立場から追われる立場になった。サウジアラビアはアウェイのベトナム戦で勝利して勝点16。無敗のまま独走状態に。
新国立劇場 ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」

●15日は新国立劇場でワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」(新制作)のゲネプロを見学。本番同様、2回の休憩を含めて合計6時間の長丁場。演出はイェンス=ダニエル・ヘルツォーク。ザルツブルク・イースター音楽祭とザクセン州立歌劇場、東京文化会館との国際共同制作で、新国立劇場と東京文化会館による「オペラ夏の祭典 2019-20 Japan ↔ Tokyo ↔ World」の第2弾なのだが、昨年6月に予定されていた東京での公演は中止になってしまい、今回ようやく上演が実現した。
●指揮は大野和士芸術監督。ピットに大野和士が音楽監督を務める都響が入るのが新鮮。ハンス・ザックスにトーマス・ヨハネス・マイヤー、エーファに林正子、ヴァルターにシュテファン・フィンケ、ベックメッサーにアドリアン・エレート、ポーグナーにギド・イェンティンス、ダーヴィットに伊藤達人。合唱は新国立劇場合唱団、二期会合唱団。非常に充実したキャストで、本番は期待してよいのでは。特にアドリアン・エレートのベックメッサーは評判を呼ぶと思う。
●イェンス=ダニエル・ヘルツォークの演出は賛否が分かれるはずだが、方向性としては筋が通っている。第1幕の幕が上がると、舞台奥にもうひとつの舞台があって、手前側には観客席が用意されている。この舞台内舞台で合唱団が衣装を着て歌っており、手前側にはスーツ姿の親方たちがいる。演出の設定として「劇場」が舞台となっている模様。ん、これもメタフィクション仕立てなのかと一瞬思うのだが、そうでもない。現代において昔ながらの靴職人や仕立て屋がいてもおかしくない場所が劇場である、といった程度に解した。設定を難しく受け取る必要はないと思う。第2幕では回り舞台が効果的に使われて、ザックスの家や屋外などスムーズに場面が転換する。しかし、現代において「マイスタージンガー」の物語がはたして成立するのかという根本的な問題がある。歴史劇としてならともかく、今の物語として見れば親方たちの価値観に共感するのは難しい。その点についてヘルツォークなりの答えが用意されている。まだ本番前なので、具体的にはまた後日改めて。
●「マイスタージンガー」は音楽的には空前絶後に最高なんだけど、物語内世界と現代的価値観の衝突、そして長時間座ることによるお尻の痛さという点で観る側にとってもチャレンジングな作品。でもやっぱり観てよかったと思えるし、心底楽しめる(ゲネプロであっても)。このオペラって、言うべきことは第2幕であらかた言ってると思うんすよね。第2幕、夜になってみんなが自分を見つめ直して、少しクレイジーになる。ポーグナーは自分の決断が正しかったのかどうかわからなくなる。ザックスはヴァルターの歌をどう受け止めればいいのか考えこむ。そして、エーファはザックスに会い、一歩踏み込んで思いを吐露する。今回の演出ではエーファのザックスに対する心理的な距離の近さも自然と表現されている。ザックスは世のすべてのオッサンと同様に本質的にカッコ悪い存在だと思うのだが、第3幕で「トリスタンとイゾルデ」の引用を伴って語るように「マルケ王にはならない」賢明さだけは持ち合わせている。そんな互いの間合いを計るような微妙なやり取りから、ベックメッサーの登場を通じてドリフのコント並みのドタバタ劇へとなだれ込んでゆく。この手腕は神技。音楽もここがいちばん楽しい。第3幕は長い長いエピローグみたいなもの、と言っては言いすぎか。
クシシュトフ・ウルバンスキ指揮東京交響楽団の「カルミナ・ブラーナ」
●13日はサントリーホールでクシシュトフ・ウルバンスキ指揮東響。プログラムはシマノフスキのヴァイオリン協奏曲第1番(弓新)とオルフの「カルミナ・ブラーナ」。シマノフスキは当初ボムソリが独奏者に予定されていたのだが入国制限の影響で出演できず、代役に弓新。現在、北西ドイツ・フィル第2コンサートマスターを務める。シマノフスキを曲目変更なしに乗り切れたのはすばらしい。めったに聴けないようでいて、実は東京では案外聴く機会の多い曲という気もするが、それでも感謝するしか。この曲の冒頭、素直に聴けば鳥のさえずりなんだろうけど、なんだか祭囃子的な諧謔味を感じて妙に刺さる。独奏は管弦楽と一体となって作品の魅力を雄弁に伝える。色彩の洪水、濃密なロマンに眩暈。
●後半のオルフ「カルミナ・ブラーナ」はこれまでに聴いたことのないような新鮮な演奏。まず合唱団の人数の少なさにびっくり。これは時節柄による制約だが、P席に陣取った新国立劇場合唱団が総勢で48人。さらにLAブロックを開けて東京少年少女合唱隊が配置されるのだが、こちらは12名ほど。ディスタンスたっぷりの少数精鋭仕様。独唱陣はソプラノに盛田麻央、テノールに彌勒忠史、バリトンに町英和。さすがにここまで合唱が少ないと迫力が不足するか……と思いきや、むしろ少人数ならではの機動力や輪郭のくっきりした表現がウルバンスキの狙いにぴたりとはまった感があった。土の香りや猥雑さを剥ぎ取って現れたのは、清新さとユーモアを身にまとった「カルミナ・ブラーナ」。切れ味鋭く、躍動感と透明感があってみずみずしい。
●第7曲「気高き森」のところだったかな、合唱団が体を左右に揺らしながら歌う演出あり。あと第12曲の「白鳥丸焼きソング」では彌勒忠史がオペラばりの演技付きで舞台袖から登場。手に持っていたのは白鳥のぬいぐるみ? 続く町英和の堂々たる酔っぱらいぶりなど、なんともいえない可笑しみがあって大吉。ウルバンスキ流の洗練あってこそ、ベタな仕掛けがユーモアとして機能するんだと思う。あと、合唱団の人数は多すぎるよりは少ないほうがなにかとよいと確信。終曲で帰ってくる「おお、運命よ」に鳥肌。最後は盛大な拍手から、ソロカーテンコールとスタンディングオベーションへ。忘れがたい公演になった。
ベトナム対ニッポン@ワールドカップ2022カタール大会 アジア最終予選
●ムーティ指揮ウィーン・フィルがアンコールで「皇帝円舞曲」を演奏していた頃、ベトナムではワールドカップのアジア最終予選、ベトナム対ニッポンがキックオフ。時差はきつくなかったがどのテレビ局もアウェイの放映権を獲得しなかったため、DAZNの配信でしか見ることができない。Jリーグに続き代表戦までテレビからネットに移行しつつあるが、この状態が続くとどうなるのだろう。サッカー人気が衰えるのか、あるいは単にスポーツ中継のプラットフォームが変化するだけの話なのか?
 ●で、出遅れたニッポンはアウェイといえどもベトナム戦は必勝。ベトナム代表は史上初の最終予選に臨んでおり、代表を率いるパク・ハンソ監督は国民的な英雄なのだとか。サッカー熱も高まっているようで、かつての日本を思い起こす。この日の試合に向けてもしっかり準備を整えてきておりコンディションではニッポンを上回る。布陣は5バックで守備ブロックを固めてくるのかと思いきや、ラインを高めに敷き、前線からプレスもかけてくる。フィジカルよりも技術とスピードに持ち味のあるチームで、本来ならポゼッション志向は高いのだろう。逆に言うとカウンターアタックの切れ味、競り合いの強度はないので、むしろニッポンにとっては戦いやすいタイプでもある。要注意はUAE人主審、そしてでこぼこした芝。もっともこの芝にはニッポン以上にベトナムも苦しんだのでは。
●で、出遅れたニッポンはアウェイといえどもベトナム戦は必勝。ベトナム代表は史上初の最終予選に臨んでおり、代表を率いるパク・ハンソ監督は国民的な英雄なのだとか。サッカー熱も高まっているようで、かつての日本を思い起こす。この日の試合に向けてもしっかり準備を整えてきておりコンディションではニッポンを上回る。布陣は5バックで守備ブロックを固めてくるのかと思いきや、ラインを高めに敷き、前線からプレスもかけてくる。フィジカルよりも技術とスピードに持ち味のあるチームで、本来ならポゼッション志向は高いのだろう。逆に言うとカウンターアタックの切れ味、競り合いの強度はないので、むしろニッポンにとっては戦いやすいタイプでもある。要注意はUAE人主審、そしてでこぼこした芝。もっともこの芝にはニッポン以上にベトナムも苦しんだのでは。
●ニッポンはオランダ発のチャーター便が給油地ロシアでトラブルに遭い、一部主力選手が機内で長時間足止めを食らうトラブルに見舞われた。全員がそろったのは試合前日。この場合の考え方としては、直前合流組を控えにして先に集まった選手でチームを組むか、あるいは前の試合のやり方をそのまま踏襲するか。森保監督の決断は後者で、ほぼ前のオーストラリア戦と同じメンバー、同じ交代選手を起用して戦った。ただし右サイドバックは酒井ではなく山根。中盤は遠藤がアンカーというよりは、むしろ田中碧、遠藤、守田が3枚並ぶ形。左右は非対称で、守田はかなり左サイドに張り出すポジションをとり、その分、南野は中に入る。右サイドは伊東が張り出してこのエリアを完全に支配、スピード無双で攻守にわたって大活躍。
●前半17分、大迫のポストプレイから南野が抜け出し、中央に入れたクロスを伊東が蹴り込んで先制ゴール。前半40分にはニッポンのカウンターで、自陣から伊東が左サイドを爆走してゴールに叩き込むというスーパー・ゴールが炸裂したのだが、なんと、VARで取消し。シュートの瞬間にオフサイドポジションに選手がいたというのだが、これをオフサイドというのは直感的にはナンセンス。VARで5分以上判定に時間をかけていた点にも強烈な違和感が残る。
●結局、その後ゴールは両者に生まれず、ベトナム 0対1 ニッポンという結果に。後半、交代選手を次々と投入し、ほとんどの時間帯で主導権を握っていた割には決定機の乏しい試合になってしまった。1点差だとなにが起きるかわからない。もっともベトナムも好機の芽をたくさんもらっていたにもかかわらず、本当のチャンスは一度もなし。これはニッポンのディフェンスがよかったというべきか。ベトナムとニッポンはアジア・カップ2019UAE大会の準々決勝でも対戦しており、当時も同じスコアでニッポンが勝った。その試合でもグエン・コン・フオンが鋭い攻撃を見せており、ベトナムはもう大量点を獲れる相手ではなくなっていた。若くて勢いがある。
●ニッポンのメンバーを。GK:権田-DF:山根、吉田、冨安、長友(→中山雄太)-MF:遠藤航、田中碧(→柴崎)、守田(→原口)-伊東、南野(→浅野)-FW:大迫(→古橋)。サウジ戦での出来事があっても柴崎を切り捨てずに挽回のチャンスを与えるあたりが森保監督。惜しいミドルシュートあり。途中出場の浅野はボールが足につかない様子だが、これは芝の影響か。山根は見事に抜擢にこたえた。実は右サイドバックには冨安という選択肢もある。冨安はアーセナルで不動の右サイドバック。欧州ビッグクラブで唯一、試合に出ているのが冨安。ただ、センターバックも層が薄いので、冨安をサイドで使うのはもったいないか。問題の左サイドバックは中山雄太が長友の後継者になるべく、スタンバイ中といった様子。
リッカルド・ムーティ指揮ウィーン・フィルのモーツァルト&シューベルト
●11日はサントリーホールでウィーン・フィルハーモニー・ウィーク・イン・ジャパン2021。今回の指揮はリッカルド・ムーティ。昨年、困難を乗り越えて来日してくれたウィーン・フィルだが、今年もまた来日公演が実現。というか、来日オーケストラを聴いたのって、まさにその昨年のウィーン・フィル以来なのでは(アンサンブル・アンテルコンタンポランを別とすれば)。プログラムはモーツァルトの交響曲第35番「ハフナー」とシューベルトの交響曲「グレイト」。
●春にムーティが単身来日した際も東京春祭オーケストラで同じ「ハフナー」を振ってくれたけど、印象はずいぶん違って、かなり重々しい。年齢を考えれば驚異的に元気なムーティだけど、それでもやはり音楽は年輪を重ねていて、かつての機敏さや弾力性に代わって、重厚さや粘りが前面に出ている。そしてウィーン・フィルの来日公演ではたびたびあるように、最初はどこか散漫な様子で始まるのだが、進むにつれて音楽が生命力を獲得し、最後はウィーン・フィルならではの豊麗な響きが鳴り渡る。ダイナミズムと抒情性に富んだ「グレイト」を堪能。曲が終わると間髪入れずに拍手がわき起こり、客席は大喝采。アンコールはヨハン・シュトラウスの「皇帝円舞曲」。これはもうお家芸。すべてが手の内に入っているといった様子で、ヨハン・シュトラウスのワルツのなかでも屈指の名作を楽しませてくれた。客席ではブラボーと記した幕を掲げる人たちが何人もいて、ムーティもこれに反応するなど、在京オーケストラの演奏会とはまた違った雰囲気。祝祭的なムードのなかで、ムーティのソロカーテンコールが2回。客席はスタンディングオベーション。
ショパン・コンクール優勝者ブルース・リウのリモート記者会見

●現在、ショパン・コンクール優勝者のブルース・リウが来日中。えっ、ついこの前までコンクールに出てたのに!と思いきや、すでにツアーが始まっており最初の訪問地が日本。明日のリサイタル(完売)を前に本日、リモートで記者会見が開かれた。限られた時間を有効に使うために事前に参加者から質問を集めておき、会見冒頭からリウさんがそれに次々と答える方式。もちろん、参加者多数で質問も盛りだくさん。使用ツールはZOOM。
●一問一答みたいなものはすぐにどこかに出ると思うので、自分の印象をつらつらと書くと、リウさん(ってのはヘン?)はオープンで率直な好青年といった様子。おそらく優勝決定の瞬間からありとあらゆるメディアから取材され、コンサートとメディア対応に明け暮れるような日々が続いて相当に疲れもたまっていると思うのだが(そして昨晩はよく眠れなかったようなのだが)、それでも何十回も答えたであろう質問に落ち着いて答えてくれる。この状況ではある意味逆説的だけど、この日の会見でなんども出てきた言葉が「フレッシュネス」。たとえば自身が演奏に臨む姿勢をこう語る。
●リウ「自分にとっていちばん大切なのは新鮮さを失わないこと。ステージに上るまで常に新しいアイディアを探している。練習と同じものを再現しよう、安定した演奏をしようという気持ちはまったくない。その正反対。常に新しいことに挑戦したい、まったく違った演奏をしたいと思っている」
 ●ショパンのイメージについて。リウ「ショパンは肉体的に病弱だけれど、愛国心もあって精神的には強靭。私と正反対でとても内気だった。自分は楽観的で楽しく社交的。ショパンと自分とのバランスをどうとるかをいつも考えている。もちろんショパンの思い描いていたものを伝えることがなにより大切なのだけれど、自分の個性も表現しなければならない。作曲家の意思を尊重しながら、新鮮でみずみずしい演奏をしたい。毎回、新しい発見、新しい喜びがなければいけない」
●ショパンのイメージについて。リウ「ショパンは肉体的に病弱だけれど、愛国心もあって精神的には強靭。私と正反対でとても内気だった。自分は楽観的で楽しく社交的。ショパンと自分とのバランスをどうとるかをいつも考えている。もちろんショパンの思い描いていたものを伝えることがなにより大切なのだけれど、自分の個性も表現しなければならない。作曲家の意思を尊重しながら、新鮮でみずみずしい演奏をしたい。毎回、新しい発見、新しい喜びがなければいけない」
●今後、ショパン以外にどんな曲を弾いていきたいかを尋ねてみた。リウ「ショパン・コンクールに優勝しておいてショパンを弾きたくないというわけにはいかないけれど、今は違う作曲家をもっと弾きたいなという気分。特にラヴェルやラモーなどのフランス音楽。知られざる傑作を発掘していきたいという気持ちも強い。スタンダードな曲ばかりを演奏しているとクラシック音楽が廃れてしまう。ほかにも興味のある作曲家がたくさんいる。モーツァルトやハイドンのような古典派の音楽も弾きたい」
マリノスvsFC東京 J1リーグ第35節、優勝を逃した後のゴールラッシュ
●前節、川崎の優勝が決まってから中二日でマリノスvsFC東京戦。なんとこれが8対0という大勝になった。マリノスとしてはACL出場権を獲得するための試合で、3人のみ選手を入れ替えて臨んだ。東京はディフェンス森重とキーパー波多野の乱調があって、前半から次々とマリノスが得点を重ねる展開に。前半39分に森重が退場して一人減ったこともあり、終わってみれば8ゴール。得点は前田大然、マルコス・ジュニオール(PK)、小池龍太、前田大然(PK)、前田大然、小池龍太、オウンゴール、水沼宏太。マリノスは東京を苦手にしているのだが、たまにはこんなこともある。
●試合後、東京の長谷川健太監督のインタビューが妙にさばさばしていたが、その後、監督辞任のニュースが流れた。最後は負けが込んだが、どんな名監督であっても去り際はそんなもの。これまでの実績を考えれば、近い将来のニッポン代表監督の有力候補だと思う。
●マリノスにとって前田大然は最重要プレーヤーだが、来季もここにいてはいけない。噂ではポステコグルー監督に引っ張られてセルティックに行くことになっているが、スコットランドリーグでいいのかどうか。前田大然ならドイツやイタリアでもプレイできると思っている。
---------
明日の当ページ更新は夕方以降になる予定。
クシシュトフ・ウルバンスキ指揮東京交響楽団のモーツァルト、ベートーヴェン、ブラームス
●6日はミューザ川崎でクシシュトフ・ウルバンスキ指揮東京交響楽団。直近までどうなるかとやきもきしていたが、無事にウルバンスキの来日が実現。プログラムはモーツァルトの「魔笛」序曲、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第2番(児玉麻里)、ブラームスの交響曲第4番。久々に聴くウルバンスキだが意外とクラシカルなプログラム。「魔笛」は序奏と爆速主部のコントラストが鮮やか。「魔笛」もベートーヴェンの協奏曲も、冒頭和音がノンヴィブラートの清澄な音色。ベートーヴェンでは児玉麻里の独奏が歯切れよく推進力にあふれ、ウィットにも富んでいる。硬質なタッチによる鋭敏なベートーヴェンだが、第2楽章での瞑想的な表現も絶美。これは名演。
●後半、ブラームスの交響曲第4番は楽器間のバランスやアーティキュレーション、ダイナミクス等、一般的な解釈とは異なる点が多々あって、古典の再構築感を存分に満喫できるスリリングな演奏。清新さのなかに手に汗握る興奮がある。ドイツの伝統に根差した重厚なブラームスを求める向きにはまったく受けないとは思う。ウルバンスキも最初に聴いた頃から十年以上経っていて、それなりの年齢になっているはずだが、相変わらず細身で、身のこなしは独特。指揮台上の不思議なロボダンス風の動きを目にすると、足を踏み外さないかとドキドキする。
●終演後の客席の反応はまだら模様といったところで、そそくさと退場する方もいれば、舞台上から楽員がいなくなっても熱心に拍手を続ける方もいて、納得の賛否両論。ソロカーテンコールになりそうな様子だったが、分散退場のアナウンスが始まって実現せず。
「ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一年」(ショーン・バイセル著/白水社)
 ●この本は無茶苦茶におもしろいと思った。「ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一年」(ショーン・バイセル著/白水社)。スコットランドのウィグタウンは「本の街」として知られているそうなのだが、この街の出身である著者が帰省中に古書店ザ・ブック・ショップに立ち寄った。本を買いに行ったはずの著者は、なんと、本屋を買ってしまう。リタイアしたがっていた店主から、店を買い取ることになったのだ。そして古書店主として奮闘し、店は街の名物書店となる。この本に記されているのは、そんな店主の一年間の日記。日々、何人の客が来て、いくら本が売れて、どんなことがあったかを書いている。これがおかしい。
●この本は無茶苦茶におもしろいと思った。「ブックセラーズ・ダイアリー スコットランド最大の古書店の一年」(ショーン・バイセル著/白水社)。スコットランドのウィグタウンは「本の街」として知られているそうなのだが、この街の出身である著者が帰省中に古書店ザ・ブック・ショップに立ち寄った。本を買いに行ったはずの著者は、なんと、本屋を買ってしまう。リタイアしたがっていた店主から、店を買い取ることになったのだ。そして古書店主として奮闘し、店は街の名物書店となる。この本に記されているのは、そんな店主の一年間の日記。日々、何人の客が来て、いくら本が売れて、どんなことがあったかを書いている。これがおかしい。
●で、とにかく店主から従業員から客まで、みんな相当にヘンな人たちばかり。店主は古書店に対する最大の敵であるアマゾンを憎悪しており、ショットガンで打ち抜かれたKindleを店に展示している(そういうユーモアのセンスの持ち主)。日本と違って、客はすぐに値切ろうとする(しかもありえないほど大幅に)。探していた本を見つけた客が、店主に値段が高すぎると文句を言う。値引きに応じないと、客は買わずに去る。しかしきっと後でまた戻ってくるだろうと見た店主は、値付けを高くする。思惑通り、その客は戻ってきてしぶしぶ値上げされた本を買う。えー、それってどうなのよ。イヤな客の多さにもびっくり。わざわざ品ぞろえに嫌味を言ってくる客、長時間暖炉のそばで商品の本を何冊も読み続け、それを片付けもせずになにも買わずに出ていく客、こっそり値段を安く書き換える客。そんな客が大勢いる一方、心温まるエピソードも少しはある。今の時代に紙の本を売っていくのは大変なことではあるが、本好きにとってはロマン。ヘンな話も楽しいが、淡々とつづられる日々の業務や店主の本に対する思いなども味わい深い。
●あと、古書文化の厚みという点で、英語圏にはかなわないことも実感。100年以上前の革装の古書が普通に流通しているあたり、活版印刷の歴史の違いを感じる。
●エピローグにしんみりする。
●いつもならこの種の本はKindleで読むのだが、今回はなんだか著者に申しわけない気がして紙の本を買った。ちなみにこの古書店ザ・ブック・ショップのサイトに行くと、破壊されたKindleが店内に飾ってある様子をYouTubeの動画で確認することができる。
J1リーグは川崎フロンターレが2年連続の優勝
●Jリーグは川崎が連覇達成。4試合を残して早々に優勝決定という圧倒的な強さには脱帽するしか。一応、マリノスが2位で追いかけてはいたのだが、背中は遠く、ごく一時期を除いて優勝争いをしていた実感はない。ここまで34試合で勝点85は自身の最多記録を塗り替えたとか。26勝1敗7分は尋常じゃない。
●昨日は川崎が優勝を決める一方、マリノスはガンバ大阪に0対1で屈した。スタッツを見ると、マリノスのボール支配率は75%。相手の3倍、ボールを持っていたことになる。実はシュート数もパス数もマリノスは相手の3倍ほど。しかし、わずか一本打たれた枠内シュートが入ってしまった。ポゼッションの高いチームが負けるのは現代サッカーでは普通のことだが、決定機も多く、ゴールが生まれなかったのはたまたまそういう日だったと解釈できる。こういう敗北はそこまで悔しくない。というのは、まあ、負け惜しみなのだが。来季もマスカット監督でいいのかどうかは考えどころ。どこかでポステコグルーの残像を追いかけるのを止めなければならない。
●今季はJ1、J2ともに降格争いが熱い。なにしろコロナ特例で昨季に降格がなかった分、今季はまとめて4チームずつ落ちるので。J1は現状、下から横浜FC(26)、仙台(26)、大分(28)、徳島(30)が降格圏。これに勝点2の差で清水、湘南(以上32)が続く。この6チームでの争いか。J2はもっと熾烈で、下から松本山雅(31)、北九州(32)、愛媛(33)、相模原(33)が降格圏、そこから勝点4の差で群馬、金沢、大宮(以上37)が並んでいる。名波監督率いる松本山雅の不振は衝撃的。今のところJ1からJ3まで落ちたチームは大分だけだと思うが、どうなるだろう。実はJ3で現在2位の宮崎がJ2のライセンスを持っておらず、このまま2位以上でフィニッシュした場合は、J2からの降格は3チームに減る。このあたりが微妙に効いてくるかも。
「本は読めないものだから心配するな」(管啓次郎著/ちくま文庫)
 ●かねてより名著だと思っていた一冊が文庫化された。「本は読めないものだから心配するな」(管啓次郎著/ちくま文庫)。帯に「読書の実用論」と書かれていて、その通りなのだが、なんの本かを説明するのは難しい。本についての本なんだけど書評では決してなく、かといって読書論と言い切るほど狭くはない。ともあれ、この本は冒頭に置かれたエッセイ「本は読めないものだから心配するな」(そのまま書名にもなっている)が圧倒的にすばらしい。文庫だったら、この数ページのためだけに買う価値がある。こんなふうに始まる。
●かねてより名著だと思っていた一冊が文庫化された。「本は読めないものだから心配するな」(管啓次郎著/ちくま文庫)。帯に「読書の実用論」と書かれていて、その通りなのだが、なんの本かを説明するのは難しい。本についての本なんだけど書評では決してなく、かといって読書論と言い切るほど狭くはない。ともあれ、この本は冒頭に置かれたエッセイ「本は読めないものだから心配するな」(そのまま書名にもなっている)が圧倒的にすばらしい。文庫だったら、この数ページのためだけに買う価値がある。こんなふうに始まる。
本は読めないものだから心配するな。あらゆる読書論の真実は、これにつきるんじゃないだろうか。
みんな覚えがあると思うのだが、がんばって本を読んでも、後からなにかの機会に振り返ってみると、内容をよく覚えていなかったりする。これじゃあ読んだと言えないのでは。そう思うこともしばしば。そして、読むべき本はたくさんあって、いっこうに減らない。さらに再読すべき本もある。いずれこれはもう一度読まねば。そう思っていても読めたためしがない。書店や図書館で読むべき本がずらりと並ぶ書棚を前にすると、どうしようもない無力感に苛まれる。だんだん本の山に対してワクワクする気分よりも、うっすらとした挫折感のほうが大きくなってくる。そういう人間に対して、心配いらないよと言ってくれているのだが、そこで提示される視点に目からウロコが落ちた。
本に「冊」という単位はない。あらゆる本はあらゆる本へと、あらゆるページはあらゆるページへと、瞬時のうちに連結されてはまた離れることをくりかえしている。
この一文で「あああっ!」と膝を打つ、全力で。さらにもう一か所引用する。
本に「冊」という単位はない。とりあえず、これを読書の原則の第一条とする。本は物質的に完結したふりをしているが、だまされるな。ぼくらが読みうるものはテクストだけであり、テクストとは一定の流れであり、流れからは泡が現れては消え、さまざまな夾雑物が沈んでゆく。本を読んで忘れるのはあたりまえなのだ。本とはいわばテクストの流れがぶつかる岩や石か砂か樹の枝や落ち葉や草の岸辺だ。流れは方向を変え、かすかに新たな成分を得る。
引用し始めるとずっと続けたくなるが、ぜんぶ書き出すわけにもいかない。しびれるような名文だと思う。
クラシック・キャラバン2021 ストラヴィンスキー「兵士の物語」他
●29日は浜離宮朝日ホールで「クラシック・キャラバン2021 クラシック音楽が世界をつなぐ ~輝く未来に向けて~ 兵士の物語」。一般社団法人クラシック音楽事業協会の主催で、北海道から沖縄まで全国各地を巡る「クラシック・キャラバン2021」の一公演。「クラシック・キャラバン2021」にはオーケストラ公演も室内楽公演もあるのだが、この日は室内楽公演でストラヴィンスキー「兵士の物語」中心のプログラム。
●といっても、前半は珠玉の小品集と言った趣で、多数の出演者が次々と登場する。18時30分開演で、終演は21時を過ぎる長丁場。最初の挨拶ではじまって曲ごとに司会が入るスタイル。司会は朝岡聡さん。ふだんクラシックの公演には足を運ばない層にも楽しんでもらおうという趣旨の公演なので、こういうフォーマットになるのだろう。前半は千住真理子、梯剛之、水谷川優子、⼭⼝佳⼦、岡昭宏、向野由美⼦、小堀勇介らが出演。もっとも印象に残ったのは千住真理子で、隅々まで磨き上げられたエルガーの「愛の挨拶」とモンティの「チャールダーシュ」を披露。レジェンドのオーラ。
●後半はお目当ての「兵士の物語」。垣内悠希指揮、寺下真理子のヴァイオリン、加藤雄太のコントラバス、イシュトヴァーン・コハーンのクラリネット、廣幡敦子のファゴット、高見信行のトランペット、加藤直明のトロンボーン、野尻小矢佳のパーカッション、高橋克典の語り。特異な編成のアンサンブルだが響きのバランスは理想的で、キレもあってスマート。高橋克典の語りは秀逸。単なる朗読者ではない、役者の語りとはこういうものなのかと感銘を受ける。兵士役と悪魔役の語り分けもわざとらしさがなく、さすが。
●「兵士の物語」の原作はロシア民話「脱走兵と悪魔」だが、「兵士の物語」は原作にはない「望郷」や「物質的な富の空虚さ」といったテーマを盛り込んでいるところが実に20世紀的。この話は以前、ONTOMOに書いた。あと「兵士の物語」初演後にストラヴィンスキーらがスペインかぜに感染したという話題を、東京・春・音楽祭のコラム「好き!好き!ストラヴィンスキー」で書いている。こちらは全部ストラヴィンスキーが自伝に書いている事柄。