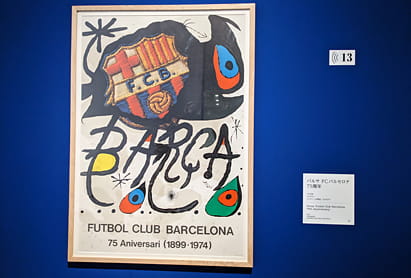●少し遡って25日、ミューザ川崎の市民交流室でフェスタサマーミューザ KAWASAKI 2025 ラインナップ記者発表会。登壇者は写真左より、廣岡克隆東京交響楽団専務理事・楽団長、望月正樹日本オーケストラ連盟専務理事、オルガニストの松居直美ホールアドバイザー、福田紀彦川崎市長、ピアニストの小川典子ホールアドバイザー、ピアニスト・ヴォーカリスト・作編曲家の宮本貴奈ホールアドバイザー。こうして記者発表会に出席すると、チーフ・ホールアドバイザーだった秋山和慶さんの不在を感じずにはいられない。全18公演からなるフェスタサマーミューザ KAWASAKI 2025のラインナップが発表された。
●中心となるプロ・オーケストラの公演では、首都圏10団体に加えて今年は九州交響楽団が招かれる。首席指揮者の太田弦の指揮でショスタコーヴィチの交響曲第5番他。なにせ遠方なので、首都圏で聴ける機会は貴重。ホスト・オーケストラとも言うべき東京交響楽団は、オープニング、フィナーレ、出張サマーミューザ@しんゆり!の3公演で、それぞれジョナサン・ノット、原田慶太楼、ユベール・スダーンが指揮。ノットのオープニングコンサートで、ワーグナー~マゼール編のニーベルングの指環管弦楽曲集「言葉のない指環」が演奏されるのが楽しみ。原田慶太楼指揮のフィナーレはニールセンの「不滅」ほか、意欲的なプログラム。期待の若手指揮者たちも目をひく。都響を熊倉優、N響を松本宗利音、九響を太田弦が振る。
●オーケストラ公演以外では、今年も小川典子のこどもフェスタ2025「イッツ・ア・ピアノワールド」や、徳岡めぐみのオルガンに隠岐彩夏ら声楽陣が加わる「真夏のバッハⅩ」、宮本貴奈らの「サマーナイト・ジャズ」など。

●21回目を迎えてキービジュアルが一新された。浮世絵とクラシックを組合わせたイラスト。新キービジュアルにちなんで、期間中に浴衣で来場すると特製ステッカーがもらえるそう。


 ●25日は
●25日は