●27日はブロムシュテット&N響へ(NHKホール)。ブラームスのヴァイオリン協奏曲(フランク・ペーター・ツィンマーマン)と交響曲第4番ホ短調。3公演にわたるブラームス・シリーズ、どれもすばらしかったけど、この日がもっとも強烈な印象を残してくれた。オケの音がぜんぜん違う。渋みのある音色だけど、透明感があって手前から奥までビシッとピントが合っているイメージ。ロマン的豊満さを削ぎ落とした後に残る音楽の骨格だけですべて語り尽くせてしまうような、緊迫感にみなぎるブラームス。協奏曲はF.P.ツィンマーマンのソロも鬼神。第2楽章のオーボエ・ソロも冴えていた。嘆息。オーケストラの最高到達点の高さを思い知らされる気分。ブロムシュテットのときは客席も特別な雰囲気になる。
●28日は彩の国さいたま芸術劇場音楽ホールでベルリン・フィルハーモニー木管五重奏団。88年からある団体で、メンバーはハーゼル(fl)、ヴィットマン(ob)、ザイファルト(cl)、マックウィリアム(hrn)、マリオン・ラインハルト(fg)。つまり首席奏者はいない。フルートのパユは同じ会場で昨年聴いたレ・ヴァン・フランセで演奏しているし、ホルンのドールは来週公演があるアンサンブル・ウィーン=ベルリンのほうに入っている。が、ファゴット以外は全員カラヤン時代から在籍してベルリン・フィルの屋台骨を支えてきた人たちなわけで、ある意味ベルリン・フィルの名を冠するにもっともふさわしいメンバーとも。特に後半、イベールの3つの小品、ミヨー「ルネ王の暖炉」、ヒンデミット小室内音楽op24-2の精緻なアンサンブルは圧倒的。全員で融け合った一つの音色を作るための微細なコントロールが徹底している。木管五重奏団ってこんなに美しい響きが作れるのかと思うくらい。
●会場には10代、20代の女子が大勢。レ・ヴァン・フランセのときもそうだったけど、オケ公演とは平均年齢が20歳以上は違ってそう。拍手の音から違うんすよ、動きにキレがあるから。
News: 2013年9月アーカイブ
ブロムシュテット&N響のブラームス、ベルリン・フィル木管五重奏団
「レヴィ=ストロースと音楽」(ジャン=ジャック・ナティエ著/添田里子訳/アルテスパブリッシング)
 ●リーバイ・ストラウス、じゃないや、「レヴィ=ストロースと音楽」(添田里子訳/アルテスパブリッシング)。著者は「音楽記号学」のジャン=ジャック・ナティエ。音楽と神話は言語が生んだ兄弟であるとして、音楽と神話にホモロジー(相同性)を見出すレヴィ=ストロース。いくつかの章を拾い読んだところだが、さすがにレヴィ=ストロースが音楽について語った部分はおもしろい。なにしろラヴェルの「ボレロ」を「平らになったフーガ」(!)として構造化されているっていう人なんだから。
●リーバイ・ストラウス、じゃないや、「レヴィ=ストロースと音楽」(添田里子訳/アルテスパブリッシング)。著者は「音楽記号学」のジャン=ジャック・ナティエ。音楽と神話は言語が生んだ兄弟であるとして、音楽と神話にホモロジー(相同性)を見出すレヴィ=ストロース。いくつかの章を拾い読んだところだが、さすがにレヴィ=ストロースが音楽について語った部分はおもしろい。なにしろラヴェルの「ボレロ」を「平らになったフーガ」(!)として構造化されているっていう人なんだから。
●とはいえレヴィ=ストロースの言葉だけ拾ってると必然的にぜんぶ孫引きになってしまうわけで、だったら原典を読めばいいじゃないの、これナティエの本なのにそれってどうよってことになりかねないわけだが、それでも堂々と拾ってしまおう、ナティエの読者じゃないから。この本のカバー自体にも「音楽じたいが人文科学の最後の謎となり、人文科学はそれに突き当たっているので、この謎が人文科学の進歩の鍵を握っているのである」(レヴィ=ストロース『生のものと火を通したもの』より)と引かれていることだし。
●ワーグナーの「ニュルンベルクのマイスタージンガー」と「パルジファル」の比較について。
どうして「パルジファル」の第3幕が「マイスタージンガー」のヴァリアントであることを疑えるだろう。どちらも歳をとった経験豊かな男(グルネマンツとザックス)が、なみはずれて才能にめぐまれたひとりの青年にみずから称号を与え、引き下がるのである。どちらも、二人の長い対話のあとに祝典の行進がつづき、この二つの場面のあいだには沈静の場面があって、一体性がとり戻される(「聖金曜日の奇蹟」または「五重唱」)。この一方をしかるべく分析するには、もう一方を知って、介在させなければならないだろう」(p.47 構造主義者レヴィ=ストロース)
●おお。ワーグナーをもう一丁。レヴィ=ストロースはワグネリアンであり、トリオやオペラの序曲の作曲に挑み、作曲家にならなかったことを後悔したという。
レヴィ=ストロースは、愛の断念のモティーフの二度目の出現を分析にとりあげるとき、どんな意味を与えているだろうか。それは「ワルキューレ」の第2幕第2場で、ヴォータンが「わたしはだれよりも惨めだ」と叫ぶときに現れる。「音楽のモティーフの回帰は、愛にまかせて自由な人間を生んだヴォータンの失敗と、愛のない結婚によって自分の意思に隷属する人間を生んだアルベリヒの成功とのあいだに、相関と対立の関係があることを強調している。それゆえジークムントとハーゲンは、たがいに対称でしかも逆転しているようにみえるのである。(…)ジークムントは失敗した試みとして、ジークフリートを先取りしている」(p.70 レヴィ=ストロースとワーグナー)●実に切れ味鋭いっすよね。「指環」における人物相関を、ヴォータン/アルベリヒ組、ジークムント/ハーゲン組、ジークフリート/グンター組と配置して見せる。特に「アルベリヒの成功」と「ヴォータンの失敗」という対照には思わずポポポーンと膝を打つ。
●引用魔になった勢いで、本書でも言及されている「悲しき熱帯」のマト・グロッソでショパンの練習曲作品10-3(「別れの曲」のことだが)のメロディを思い出すシーンを引っ張っておこう。こっちは「悲しき熱帯」から直接引用。
なぜショパンだったのだろう? ショパンが特に私の好みという訳でもなかったのに。ワグナー崇拝の中で育った私は、ドビュッシーを見出したのも極くあとになってからのことだった。(…)だが、私がフランスを去る時には、私の必要としていた精神の糧を与えてくれたのは、「ペレアスとメリザンド」だった。それなのになぜショパンが、それも彼の作品としても、最も凡庸なものが、荒れ野の中で私に取り付いたのだろう? 本来しているべき観察に精を出すよりもこの問題を解くのに心を奪われていた私は、ショパンからドビュッシーへ移るということのうちにあった進歩が、逆向きに起こる時には、おそらく拡大されるのだろうと思ってみたりした。私にドビュッシーを好きにさせたあの悦楽を、そのとき私はショパンのうちに、はっきりとは自覚されない、まだ不確かな形のまま味わっていたのであろう。(「悲しき熱帯」II 第9部 回帰/川田順造訳/中公クラシックス)
●このショパンにドビュッシーを聴くってのは、ボレロに平らになったフーガを聴き、「マイスタージンガー」に「パルジファル」を見るってのと一脈相通じるところがある。でも、ここまで来ると、いいじゃん、実はショパン大好きでしたでも、と思わんでもない(笑)。
アシュケナージ&OEK、ブロムシュテット&N響
●20日はアシュケナージ指揮オーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)東京公演へ(オーチャードホール)。辻井伸行独奏でグリーグのピアノ協奏曲、ベートーヴェンの交響曲第6番「田園」他。久々に対向配置ではないOEKを聴いたかも。このホールに室内オケは辛いかなと思いきや、オケは明快によく鳴っていた。くっきりと鮮やかなグリーグとベートーヴェン。
●珍しいことに楽章間に拍手が起きた。グリーグのピアノ協奏曲の第1楽章の後に出たときは、辻井伸行渾身のソロに対して思わず出てしまったのか微妙なところだったが、「田園」の第1楽章の後、さらに第2楽章の後にも律儀に拍手が起きた。ぜんぜん悪いことではないはず。作曲当時の聴衆もそのように拍手していたことだろう。そして、このときほどグリーグやベートーヴェンが後半の楽章をつなげて書いていることに納得できたことはない。作曲家はきちんと客席をコントロールしている。
●21日はブロムシュテット&N響(NHKホール)。12日に続いてブラームス・ツィクルスで、この日は交響曲第2番と第3番。前半第2番、後半第3番という2曲だけの短めのプログラムだけど、内容的には猛烈に密度が濃い。ロマン的豊潤さとは別種の、体脂肪率5%くらいの純度の高い峻厳なブラームス。特に第3番では何者かが降臨していた。指揮者、オケ、客席全体が一体感に包まれて特別な雰囲気が生まれる、ブロムシュテットのときは、いつもおおむね。
告知系、いくつか
●自分関係の告知をいくつか。
●まず本日、FMヨコハマさんの番組「DOCOMO presents いつもふたりで・・・」(19:00~20:00)にゲスト出演します。パーソナリティは渋谷亜希さん。毎週さまざまな角度から「ふたりで過ごす」をテーマにゲストを招いてトークするという番組で、今週は「芸術の秋」にちなんで「クラシック音楽を楽しむ」。渋谷亜希さんが激しく素敵な方だったので、思い切り鼻の下を伸ばしていっしょに写真に写ってしまった……。ドコモダケと執事のひつじくんと共演できたのも嬉しい! って、共演じゃないか。
●23時からは毎週恒例、FM PORT「クラシックホワイエ」。新潟県内およびauのLISMO WAVEユーザーの方はぜひ。
●USENさんの会員向け会報誌 WithMusicで新連載「五線譜のウラガワ」をスタート。一般向けのエッセイで、第1回のテーマは「第九」について。
●オーディオの総合月刊誌「STEREO」10月号(音楽之友社)の特集「スリム&スマート!」にて、マイクロハイエンド・コンポの取材にお招きいただきました。ホスト役はオーディオ評論の鈴木裕さん。ピュアオーディオの雑誌だけど、USB接続でPCオーディオも楽しむ設定で、音源はCDとmp3と両方を用意して、いろんな機材の組合せを試聴取材。ワタシの役どころはピュアオーディオ素人のコンサートゴアーが率直な感想を述べるといったところか。オーディオ機器の試聴に対する自分の基本姿勢は「人間の耳はいとも簡単に騙されるので、聴感上の微細な差異は可能な限りネグレクトしたい、聴覚よりも理論や測定値を優先したい」というオーディオ専門の方からは叱られそうなものなので、「こんな自分で大丈夫かなあ」と心配しながら取材に臨んだんだけど、鈴木裕さんのスマートで的確なナビゲートに助けていただいた。深く感謝。
ゼッダ→園田隆一郎&東フィル
●19日はオペラシティで東フィル。アルベルト・ゼッダが体調不良により来日できなくなったため、急遽代役として園田隆一郎が指揮を務めることに。プログラムはそのまま、すなわちヴィヴァルディ「四季」とR・シュトラウスが若き日に書いた交響的幻想曲「イタリアより」。
●が、前半の「四季」は指揮者を立てずに、ヴァイオリン独奏の三浦文彰が小編成の弦楽アンサンブル(+チェンバロ)をリードする形に。ソリストが真ん中に一人で立って、後ろに弦楽合奏がみんなで座って控えるという、久々のモダン・オケ版「四季」。ソリストとコンサートマスターが父子共演というシチュエーションになぜかドキドキ。切れ味鋭く鮮やかな、なおかつ豊満で重戦車級推進力を有するモダン・ヴィヴァルディ。もう「四季」はあらゆる流儀を包摂可能な超越的名曲ってことでいいと思う。
 ●後半から指揮者登場。シュトラウスの「イタリアより」なんて振ったことのある人はめったにいないわけで、困難な条件のなかで大奮闘、「フニクラフニクリ」で華やかなクライマックスを築いて、客席の喝采を浴びた。ちなみにこの曲って、ピアニストのリヒテルのお気に入りで、特に第1楽章「カンパーニャにて」がもっとも美しい楽章だって言ってるんすよね。インパクトでは断然終楽章だけど。
●後半から指揮者登場。シュトラウスの「イタリアより」なんて振ったことのある人はめったにいないわけで、困難な条件のなかで大奮闘、「フニクラフニクリ」で華やかなクライマックスを築いて、客席の喝采を浴びた。ちなみにこの曲って、ピアニストのリヒテルのお気に入りで、特に第1楽章「カンパーニャにて」がもっとも美しい楽章だって言ってるんすよね。インパクトでは断然終楽章だけど。
●で、これで終わりかと思いきや、まさかのアンコールで、ロッシーニの「チェネレントラ」序曲。これはもう水を得た魚。生気にあふれ、淀みなく音楽が流れる。先に席を立ったお客さんもいたみたいだけど、最後まで座っていてよかった!
「レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー」(ジョナサン・コット著/山田治生訳)
 ●読了、「レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー」(ジョナサン・コット著/山田治生訳/アルファベータ)。これはバーンスタインでなければ成立しなかったであろう特別なインタビュー本だ。著者は初対面で午後の2時から午前2時までバーンスタインと過ごし、12時間をかけてインタビューしている。たった1回のインタビューから1冊の本を作ったのだから、恐ろしく効率がいいわけだが、しかし12時間のインタビューなどというものも普通はありえない。常人は1時間も話したらネタも燃料も尽きる。
●読了、「レナード・バーンスタイン ザ・ラスト・ロング・インタビュー」(ジョナサン・コット著/山田治生訳/アルファベータ)。これはバーンスタインでなければ成立しなかったであろう特別なインタビュー本だ。著者は初対面で午後の2時から午前2時までバーンスタインと過ごし、12時間をかけてインタビューしている。たった1回のインタビューから1冊の本を作ったのだから、恐ろしく効率がいいわけだが、しかし12時間のインタビューなどというものも普通はありえない。常人は1時間も話したらネタも燃料も尽きる。
●亡くなる一年前のバーンスタインが語ったことに、いくつもの興味深い話が散りばめられているのはもちろんだが、なによりインパクトが強いのはその百科全書的饒舌ぶり。あたかもトマス・ピンチョンの小説でも読んでいるのではないかと錯覚するほど、文脈から自由に言葉がほとばしり、次々と新奇な対話の情景を見せてくれる。バーンスタインの人物像を浮かび上がらせるために、これ以上適切な手段はないと思うほど。
●どんな12時間だったのだろう。たぶん実際には意外と寡黙な12時間だったんじゃないだろうか。インタビュアーは手練手管を心得ている。しかしバーンスタイン家のディナーに招かれて、チキンが出てきたからって「菜食主義者だから食べられません」と答える間の悪さと来たら! おまけに12時間も話し込んでおいて、最後に「あなたのいちばん好きなアルバムは?」みたいな質問を発する蛮勇にもくらくらする。卓越したインタビュアーになるためには嫌なヤツにならなきゃいけないのかも。読んでおもしろいインタビューって、だいたいインタビュアーにイライラするものだし。到底マネできない。
ミラノ・スカラ座来日公演で「リゴレット」
●先週13日はミラノ・スカラ座来日公演で「リゴレット」へ(NHKホール)。今回スカラ座はこの一日のみ足を運んだ。ハーディング指揮の「ファルスタッフ」にも大いにひかれたが、ともあれドゥダメルの指揮は聴いておきたいな、と。しかしこの日を選んだのはどうだったんだろ。期待していたような精彩に富んだヴェルディとはいかず。客席の反応も薄め。
 ●とはいえ「リゴレット」、改めてこの作品はよくできているなと再認識。リゴレットって男の二面性についての物語なんすよね。女の両極に娼婦と聖女があるように、男の両極にはリゴレット(道化)とマントヴァ公爵(色男)がいる。そして、これはリア充とモテない男の話でもある。でも、まちがえてはいけない。リア充がリゴレットで、モテない男がマントヴァ公爵。
●とはいえ「リゴレット」、改めてこの作品はよくできているなと再認識。リゴレットって男の二面性についての物語なんすよね。女の両極に娼婦と聖女があるように、男の両極にはリゴレット(道化)とマントヴァ公爵(色男)がいる。そして、これはリア充とモテない男の話でもある。でも、まちがえてはいけない。リア充がリゴレットで、モテない男がマントヴァ公爵。
●リゴレットはせむし男という設定のために見逃されがちだけど、彼にはそんな自分を本心から愛してくれる妻がかつていたんすよ。しかもとびきりの美女(娘の美貌から察するに)。二人の間には娘が生まれ、娘ジルダは美しい女性へと育った。リゴレットは愛に恵まれた人生を送ってきた男だといえる。一方、マントヴァ公爵のほうは相手に不足していないというだけで本物の愛情に恵まれてはいない。やっと見つけた本当に愛せる女性がジルダだったのに、そのジルダも己の関知しないところで命を落とす。彼は本当はモテない男だ。「女心の歌」でどう歌っているか。
風に舞う羽のように女心は気まぐれ。
言うことも変われば、思いも変わる。
いつも愛らしくて優しくて、
でも泣くのも笑うのもみんな嘘。
これって、ふられた男の泣き言としか思えないもの。リゴレットの奥さんはリゴレットに対して気まぐれなんかじゃなかったと思うぞ。
●でも恐るべきは呪いの力。モンテローネの呪いによって、リゴレットは最愛の娘ジルダを失う。モンテローネはマントヴァ公爵も呪っている。マントヴァ公爵は本来なら殺し屋の手にかかるはずだったが、ジルダの自己犠牲によって救われたということになる。ジルダの不条理な行動がなければ、リゴレットは娘を失わずに済み、マントヴァ公爵は命を落とす。二者択一だ。モンテローネは一度に二人を呪ったが、そうはいかないようだ。人を呪わば穴二つ。穴のひとつは自分用なので、もう一つの穴に入れられるのは一人だけということか。
大井浩明/ベートーヴェン:ピアノソナタ全32曲連続演奏会~第1回
●16日は台風で大雨。昼間の公演はそれぞれ主催者側は難しい判断を迫られたと思う。が、夕方からはすっきりと晴れて爽やかな気候に。秋。
●で、夜は淀橋教会で「大井浩明/ベートーヴェン:ピアノソナタ全32曲連続演奏会~様式別・時代順のフォルテピアノ(古楽器)による~」の第1回。単に古楽器によるベートーヴェン演奏というだけではなく、作曲年時点ですでに存在していたタイプの楽器を用いて、作曲者の先進性をあらわにしようというシリーズ。したがって、今回は1790年頃のアントン・ヴァルターを用いていたが、シリーズが進むと使用楽器も変わる。以前に京都で開かれた同様企画の東京公演。
●よく考えてみると不思議な気もするんだけど、ベートーヴェンを古楽器オーケストラやモダン・オーケストラのピリオド寄り演奏で聴く機会はそれなりにあるのに対して、ソナタをフォルテピアノで聴く機会ってそんなにはないんすよね。オケのほうが興行的に大仕掛けなのに。なので、気分としては見たことのある光景を違う遠近法で見るような気分。モダンピアノ基準で眺めると、外枠であるキャンバスのサイズはうんと小さく見える。逆にキャンバスのなかに描かれた絵のサイズはうんと大きく見える。作家はキャンバスいっぱいいっぱいの枠を使ってはみ出さんばかりに絵を描いている。普段リサイタルの前菜にように配置されるベートーヴェンの初期ソナタが、巨大な楽想を持った作品として迫ってくる。ソナタ第3番ハ長調が熱かった。こんなド派手な曲だったの、的な。逆に比較的聴く機会の多い第1番ヘ短調は拡大鏡を用いない原寸の手ざわり。
●第2回は9/23で第5番から第8番「悲愴」まで、第3回は10/14で第9番から第11番(+第19番と第20番のソナチネ)と続く。淀橋教会のチャペルはなかなか居心地いいっすよ。
新日本フィル記者発表会にメッツマッハーとハーディング

●13日、インゴ・メッツマッハーの新日本フィル コンダクター・イン・レジデンス就任記者発表会が開かれた(東武ホテルレバント東京)。ちょうどスカラ座公演のために来日中であるミュージック・パートナー・オブ・NJPのダニエル・ハーディングも会見に臨席して、豪華な顔ぶれに。メッツマッハーは「これからの活動をとても楽しみにしている。ハーディングと一緒にこのオーケストラのために尽力したい」と抱負を語ってくれた。写真は左からハーディング、メッツマッハー、ソロ・コンサートマスターの崔文洙さん。
●で、型通りのあいさつや新シーズンへの展望はさらりと終わって、自然と話の流れのなかでメッツマッハーとハーディングの間で日本人の西洋音楽への接し方のような話題になっていったのがおもしろかった。大まかにこんな感じ。
●メッツマッハー「日本の聴衆はクラシック音楽への理解が深い。日本社会にこれだけ西洋の文化が受け入れられているということに感動する。ダニエルと話していて思うのは、ときには日本は西洋音楽という異文化に対してリスペクトを持ちすぎているのではないか、ということ。異質なものとしてではなく、自分たちの文化と同じように向かってきてほしい。西洋音楽に対してもっと身を委ねることが大切ということで見解は一致している。新日本フィルは技術的にはなんでもできるし、改善するところはほとんどない。だから客観的に接すべき作品に対しては申し分ない。しかし作品に深く入り込むタイプの音楽には、もっと体ごとぶつかって、献身してほしい。受け身ではなく、強い姿勢で向かっていくような音楽を作り出せるよう二人で考えていきたい」
●ハーディング「日本に来ると、われわれヨーロッパ人は野蛮人が文明社会に迷い込んだような気分になることがある。日本人は西洋音楽に対して礼儀正しすぎることがある。イギリスからやってきた私のようなブタは(笑)オーケストラに対して『もっと、もっと!』というと、オケは『まるで獣みたいですね』という。そう、獣だ。リスペクトは大事だけれど、手を汚さずに獲物を手に入れることはできない。音楽は神棚に飾っておくものじゃない。盆栽みたいに外から『ああ、美しいですねえ』と眺めていてはつまらない」
●ハーディングは自分たちのタイトルについても率直に話していた。「二人の指揮者がいっしょにオーケストラにかかわるのは奇妙な状況であるという感は拭えない。でも二人ともオーケストラに対して強い気持ちで向かって、貢献したいと思っている。オーケストラにハードワークさせたい。私たちは現代の家族らしい、ハードワークする家族になる。ミュージック・パートナーというタイトルがなにを意味するのか、実はいまだによくわからない(笑)。でも、この状況を楽しんでいる」
●と、こんな感じで就任記者発表会の雛壇でする話とは思えない感じのやり取りになった。この二人だからでもあるだろうし、楽団のキャラクターが出ていたという感も。
インキネン&日フィルの「ワル1」へ
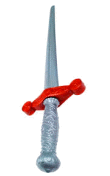 ●先週末の「ワルキューレ」第1幕祭は6日のインキネン&日フィルへ(サントリーホール)。エディス・ハーラー、サイモン・オニール、マーティン・スネルの歌手陣が超強力。演奏会形式ではあるが、演技も入り(なので暗譜)、字幕もあったので、オペラ「ワルキューレ」をがっつりと満喫した手ごたえあり。もともとこの第1幕って動きのない対話劇だから、これだけで十分かと思うくらい。そしていかに演奏会形式であっても、字幕の効力は絶大と認識。これって主人公が生き別れになった妹が結婚して暮らしている家庭に迷い込んでしまい、喜びのあまり妹に嫁になれって言って駆け落ちするカオスな話なんすよね。字幕を読んで「はあああ?」って(心のなかで)ツッコミ入れるのも「ワルキューレ」の(てか、オペラの)醍醐味。
●先週末の「ワルキューレ」第1幕祭は6日のインキネン&日フィルへ(サントリーホール)。エディス・ハーラー、サイモン・オニール、マーティン・スネルの歌手陣が超強力。演奏会形式ではあるが、演技も入り(なので暗譜)、字幕もあったので、オペラ「ワルキューレ」をがっつりと満喫した手ごたえあり。もともとこの第1幕って動きのない対話劇だから、これだけで十分かと思うくらい。そしていかに演奏会形式であっても、字幕の効力は絶大と認識。これって主人公が生き別れになった妹が結婚して暮らしている家庭に迷い込んでしまい、喜びのあまり妹に嫁になれって言って駆け落ちするカオスな話なんすよね。字幕を読んで「はあああ?」って(心のなかで)ツッコミ入れるのも「ワルキューレ」の(てか、オペラの)醍醐味。
●オニールは「ヴェーーーーーーールゼ!」をいったい何秒伸ばしたんだか。伸ばしたいだけ伸ばす。爽快すぎてもう笑うしか。
●インキネンのワーグナーは流麗で抒情的なワーグナーというか。個人的にはもっと彫の深いワーグナーを期待したいんだけど、これだけ歌手陣が盛りあげてくれれば言うことなし。客席は大ブラボー大会。こんなにテンションのあがる音楽はない。ノートゥングを振り回しながら森を駆け抜けるジークムントになった気分で家路につく、右手に折り畳み傘を握りしめながら。
メッツマッハー&新日フィル vs インキネン&日フィル
●本日と明日は新日本フィルと日本フィルがともにワーグナー「ワルキューレ」第1幕(演奏会形式)を演奏する特異日。ワーグナー生誕200周年ということで、演奏会形式で上演しやすい(歌手が3人いればいい)「ワルキューレ」第1幕を取りあげるのは納得だが、まさか同じ2日間にぶつかるとは。
●プログラムの組み方は対照的。新日フィルはメッツマッハーが指揮、「ワルキューレ」第1幕の前に、R・シュトラウスの交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」を置くという重量級。山で暮らして町に下りてきたツァラトゥストラと、山に囚われて愛を知るワルキューレ(ブリュンヒルデ。第1幕じゃそこまで話は進まないけど)。昨日の午前中、すみだトリフォニーホールで公開リハーサルが開かれたので、足を運んだ。リハ3日目ということで、公開時間は主に「ツァラトゥストラはかく語りき」を練習。鋭敏でメリハリの効いたシュトラウスになりそう。「ワルキューレ」の歌手陣はミヒャエラ・カウネ、ヴィル・ハルトマン、リアン・リ。
●日フィルのほうはフィンランドのインキネンが指揮。インキネンにとって、たぶんワーグナーはシベリウスよりもずっと振りたいレパートリーなのでは。オール・ワーグナー・プロで前半に「ジークフリート牧歌」と「トリスタンとイゾルデ」より前奏曲と「愛の死」を置く。歌手陣はエディス・ハーラー、サイモン・オニール、マーティン・スネル。
●明日になれば、両方聴いた人たちの感想がたくさんネット上にあらわれるにちがいない。対決、新日vs全日。じゃない、新日フィルと日フィルだ。ちなみにN響も昨年の11月にエド・デ・ワールト指揮で「ワルキューレ」第1幕を演奏している。「ワル1」密度はそれくらいの高さ。
カンブルラン&読響の「シンフォニア・ダ・レクイエム」「詩編交響曲」他
●3日はカンブルラン指揮の読響定期へ(サントリーホール)。シーズン初っ端から最高水準のコンサートに出会えるとは。プログラムは前半にブリテンの弦楽とヴィオラのための「ラクリメ」(鈴木康浩独奏)、「シンフォニア・ダ・レクイエム」、後半にウストヴォーリスカヤ(ウストヴォルスカヤ)のコンポジション第2番「怒りの日」、ストラヴィンスキーの「詩篇交響曲」という見事な構成の「祈り」プロ。
 ●「シンフォニア・ダ・レクイエム」も「詩篇交響曲」もこんなに美しい曲だったのかと認識を改める。ブリテンって個人的にはずっと肌の合わない作曲家だと思ってたんだけど、昨年の新国「ピーター・グライムズ」といい、この「シンフォニア・ダ・レクイエム」といい、ライブで聴いたときの鳥肌立ち具合がスゴい。「詩篇交響曲」は新国立合唱団が歌った。精妙さでも抒情性という点でも、今までに聴いた「詩篇交響曲」はなんだったのというくらいの水準。弦楽器がチェロとコントラバスだけなので、オーケストラの配置は通常ヴァイオリンが並ぶ左端からピッコロ、フルート……と指揮者を囲む。鈍色の響きに合唱が溶け合う。あ、ヴァイオリンが他の楽器より先に帰れるオケのプログラムって他にあるのかなあ。ブランデンブルク協奏曲第6番? そんな曲で終わるモダンオケの演奏会なんてないか。
●「シンフォニア・ダ・レクイエム」も「詩篇交響曲」もこんなに美しい曲だったのかと認識を改める。ブリテンって個人的にはずっと肌の合わない作曲家だと思ってたんだけど、昨年の新国「ピーター・グライムズ」といい、この「シンフォニア・ダ・レクイエム」といい、ライブで聴いたときの鳥肌立ち具合がスゴい。「詩篇交響曲」は新国立合唱団が歌った。精妙さでも抒情性という点でも、今までに聴いた「詩篇交響曲」はなんだったのというくらいの水準。弦楽器がチェロとコントラバスだけなので、オーケストラの配置は通常ヴァイオリンが並ぶ左端からピッコロ、フルート……と指揮者を囲む。鈍色の響きに合唱が溶け合う。あ、ヴァイオリンが他の楽器より先に帰れるオケのプログラムって他にあるのかなあ。ブランデンブルク協奏曲第6番? そんな曲で終わるモダンオケの演奏会なんてないか。
●「ラクリメ」は鈴木康浩さんのヴィオラがすばらしい。普段からこのオーケストラのヴィオラ・セクションは光彩を放っている。ウストヴォーリスカヤは怪作。木製の箱(木槌でガンガン叩く)とピアノとコントラバスのみという簡素な編成で、凄烈な打撃音が連続する。怒りというかもう怨念こもってますみたいなドロドロっぷり。完全にフォースのダークサイドに堕ちそうなところをカンブルランのスマートな指揮が救ってくれた。
アンコールに「ディアベリ変奏曲」
●武蔵野文化事業団のTwitterアカウントによれば、1日、武蔵野市民文化会館小ホールで開催されたジョルジュ・プルーデルマッハーの演奏会で、アンコールとしてベートーヴェンの「ディアベリ変奏曲」が演奏されたとか。まさかの大曲、約50分。
https://twitter.com/musashino_bunka/status/374173816508784640
●ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏会のシリーズ最終日ということで、第32番ハ短調op111の後に、アンコールで「ディアベリ変奏曲」。このボーナスステージ突入感はスゴい。超お得というか、イヂワル?というか……。
●大曲のアンコールといえばルドルフ・ゼルキンのエピソードを思い出す。彼がまだ17歳だった頃、共演者のアドルフ・ブッシュになにかアンコールを弾くように促された。ゼルキンは「でも、なにを弾けば?」と尋ねると、ブッシュは「バッハのゴルトベルク変奏曲」と答えた。ゼルキンはこれを真に受けてステージに戻り、おそらくは小一時間ほどかけて、大作ゴルトベルク変奏曲を弾き切った。本人談によれば「演奏が終わったころにはホールには知人と共演者しかいなかった」。
●武蔵野のお客さんは最後まで堪能したにちがいない。トイレが気になる人を除いては。